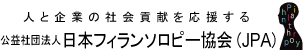< 表紙と目次
Date of Issue:2024.10.1
◆ 巻頭鼎談/2024年10月号

本屋と語る「本のチカラ」
本屋 Title 店主
辻山 良雄 さん(写真右)
株式会社隆祥館書店 代表取締役
二村 知子 さん(写真中)
<司会>
京都橘大学客員教授・公益社団法人日本フィランソロピー協会理事
京都橘大学客員教授・公益社団法人日本フィランソロピー協会理事
河野 通和(写真左)
活字離れ、人口減少、電子書籍の普及など、本を取り巻く環境は厳しさを増している。書店の閉店も相次いでいる。2024年3月、経済産業省が「文化創造基盤としての書店の振興プロジェクトチーム」を立ち上げ、新たな支援策を検討することになった。すでに車座ヒアリングなども実施し、今後の対策への期待感も高まっている。
本屋としての矜持を抱き、本のチカラを信じ、読者と作家の紐帯を強めてきたお二人の書店主に、本屋を営む醍醐味と決意を聞いた。
本屋としての矜持を抱き、本のチカラを信じ、読者と作家の紐帯を強めてきたお二人の書店主に、本屋を営む醍醐味と決意を聞いた。
河野 きょうは、二村さん、辻山さんと一緒に、改めてまちの本屋さんがなぜ大切なのかということの意味を考える機会にしたいと思います。まずは、お二人がどういう経緯で本屋さんになられたのかをお聞かせください。
父が興した書店を継ぐ

https://ryushokanbook.com/
二村 隆祥館(りゅうしょうかん)書店は、1949年に私の父・二村善明が創業しました。場所は大阪市中央区で、最寄り駅は大阪メトロの「谷町6丁目」です。大阪で海抜が一番高い上町台地に位置しており、中沢新一さんの『大阪アースダイバー』によれば、縄文人が住んでいた海進期でも陸地だったそうです。作家・直木三十五(なおき・さんじゅうご)ゆかりの地で、記念館もあります。
父が創業したころは、本が一番の娯楽という時代で、仕入れから帰ってくると、近所の子どもたちが待ちかねていて、幼児誌や学年誌に付録をはさむのを手伝ってくれたそうです。経済も右肩上がりでしたから、文学全集や百科事典などもたくさん売れました。
私が手伝い始めたのは、1995年です。創業当時は25坪でしたが、1992年に相続税対策としてテナントビルを建てることになり、建ぺい率の関係で現在の13坪になりました。1日の平均客数は170人ほどでしたが、大手のナショナルチェーン店やネット販売の攻勢を受けて、徐々に経営も厳しくなりました。
そんなときお客さんから、作家に直に話を聞いてみたいと言われたことがきっかけで、2011年の秋から「作家と読者の集い」というイベントを始めました。13年目になりますが、参加者は毎回40~50人、読者の反応がダイレクトにわかってありがたいと、作家からも好評です。こうした取り組みができるのも、まさにまちの本屋ならではです。本の良さを直接伝えられることは、すごくうれしいですね。
父が創業したころは、本が一番の娯楽という時代で、仕入れから帰ってくると、近所の子どもたちが待ちかねていて、幼児誌や学年誌に付録をはさむのを手伝ってくれたそうです。経済も右肩上がりでしたから、文学全集や百科事典などもたくさん売れました。
私が手伝い始めたのは、1995年です。創業当時は25坪でしたが、1992年に相続税対策としてテナントビルを建てることになり、建ぺい率の関係で現在の13坪になりました。1日の平均客数は170人ほどでしたが、大手のナショナルチェーン店やネット販売の攻勢を受けて、徐々に経営も厳しくなりました。
そんなときお客さんから、作家に直に話を聞いてみたいと言われたことがきっかけで、2011年の秋から「作家と読者の集い」というイベントを始めました。13年目になりますが、参加者は毎回40~50人、読者の反応がダイレクトにわかってありがたいと、作家からも好評です。こうした取り組みができるのも、まさにまちの本屋ならではです。本の良さを直接伝えられることは、すごくうれしいですね。
自分の時間を生きるために本屋を始める
辻山 私は書店勤めを経て、自分で本屋を始めました。本屋に行くのが好きで、人に本を勧める仕事が向いているのではないかと思い、大学卒業後に株式会社リブロに就職して18年勤めました。
全国に支店があるのですが、最初に勤務したのは練馬区大泉学園の小さな店舗でした。人文系の作品や芸術関係の本を置いて、かっこいい店づくりを目指していましたが、実際には、おじいさんとお孫さんが一緒に来て、『コロコロコミック』を買ったり、新学期になると『ジーニアス』などの辞書がどんどん売れる。年齢層も求める本もいろいろなのだということがわかりました。その後は九州、広島、名古屋に転勤して、最終的には池袋本店に6年ほど勤めて、閉店を機に辞めました。
ちょうどそのころ母が病気になって、看病のために神戸の実家に帰っているときに、時間の流れ方が違うことに気づいたんです。東京ではせわしなく仕事をしているけれども、母の横にいると時間がゆったりと流れている。自分の時間を生きてみたいと思いました。
池袋は大きな街ですから、リブロが閉店してもほかの書店がある。でも書店がない地域の人はどうすればいいのか。小さくても自分の責任でやりたいと思い、2016年1月に東京・荻窪で Title という本屋を始めました。15 坪ほどの広さに1万冊ほど、奥に5席ほどのカフェ、2階はギャラリーにしています。
全国に支店があるのですが、最初に勤務したのは練馬区大泉学園の小さな店舗でした。人文系の作品や芸術関係の本を置いて、かっこいい店づくりを目指していましたが、実際には、おじいさんとお孫さんが一緒に来て、『コロコロコミック』を買ったり、新学期になると『ジーニアス』などの辞書がどんどん売れる。年齢層も求める本もいろいろなのだということがわかりました。その後は九州、広島、名古屋に転勤して、最終的には池袋本店に6年ほど勤めて、閉店を機に辞めました。
ちょうどそのころ母が病気になって、看病のために神戸の実家に帰っているときに、時間の流れ方が違うことに気づいたんです。東京ではせわしなく仕事をしているけれども、母の横にいると時間がゆったりと流れている。自分の時間を生きてみたいと思いました。
池袋は大きな街ですから、リブロが閉店してもほかの書店がある。でも書店がない地域の人はどうすればいいのか。小さくても自分の責任でやりたいと思い、2016年1月に東京・荻窪で Title という本屋を始めました。15 坪ほどの広さに1万冊ほど、奥に5席ほどのカフェ、2階はギャラリーにしています。
コロナ禍での経験
河野 コロナ禍では本屋さんも大変でしたよね。

近著に『しぶとい十人の本屋―生きる手ごたえのある仕事をする』(朝日出版社)。
https://www.title-books.com/
辻山 開店から1年ほどでWEB SHOPを始めていたのですが、2020年にコロナ禍で緊急事態宣言が発令されたときに店を閉めたら、とたんに全国からWEBで注文が入り始めて、月の店頭売りと同じぐらいの売り上げがありました。書店の近所にお客さんがいて、それが膨らんで商圏やコミュニティになるという構造は昔も今も同じですが、WEBで購入する人や、SNSで同じような本好きの人ともゆるやかにつながるコミュニティも同時に存在している。そういう重なりの中で支えられて今があるなというのが実感です。
二村 うちもオンラインショップをやっています。京都や奈良から来ていたお客さんから、「行けないので本を選んで送ってほしい」という要望をいただき、ちょうど「一万円選書」をやってみようかなと考えていたので、お客さんから背中を押されて始めました。
熱量をかけると本は売れる
河野 品ぞろえについては、どんなことを意識されていますか。
二村 社会問題に関心が高いお客さんが多いので、ノンフィクション作品を豊富に置いています。それから、私は30代のころにパニック障害になって、地下鉄にも乗れなくなるような精神状態だったのですが、たまたま出合った星野富弘さんの『愛、深き淵より。』に救われたんです。そんな体験もあって、人がもう一度生き直せるような、そのことを感じられるような本も意識して置いています。私自身が、本に囲まれている空間にいることでほっとするんですよ。
辻山 人それぞれ、求める本は違いますが、読み継がれていく本、ロングセラーはどのジャンルにもあります。本は人をつくるものだと思っているので、いい加減なものは置けません。例えばビジネス書ならドラッカーのような名著、年齢層も幅広いので、絵本も含め、各世代向けのおすすめ本も置いています。
河野 辻山さんのお店に行くと、気持ちがとても落ち着くのと、商いの光景がまたいいですね。子どもが『コロコロコミック』を買いに来て、握りしめていた小銭を大事そうに辻山さんに渡している(笑)。
辻山 職場と自宅以外の、自分に戻れる場所になれたらいいですね。毎日200冊ほど出る新刊の中から、自分が選んだ本をSNSで発信すると、Title の空間が広がって、誰かに届く。それを受け取った人が本を求めて来る。本屋はそうやってでき上がっていくと思います。
二村 不特定多数には来てもらえないかもしれませんが、父の代から長くお付き合いしてくださるお客さんもいますから、教えていただくことは多いです。
辻山 本屋を始めて発見したのですが、置き方や並べ方を工夫したり、POPをつくったり、SNSで紹介するとか、何かしら熱量をかけると売れるんですよ(笑)。
二村 私もそう思います。不思議ですよね。
本を媒介にして心の回路が開かれる
河野 本を間に挟んで話をすると、家族や職場の人には普段あまり話せないようなことを口にしたり、聞いたりすることがありますね。本を媒介に心の回路が開かれるというか…。

二村 お母様を介護されていたお客さんに、久坂部羊さんの『老乱』をおすすめしたら、「すごくよかった。読んでから腹が立たないようになった」と言われました。また、春日武彦さんの『屋根裏に誰かいるんですよ。』をどうしても読みたいというお客さんがいたのですが、すでに絶版で、どうにかできないかと版元に相談したら、こっそり全ページをコピーして送ってくれました。出版社もうちも一銭にもならないのですが(笑)。後日その方が、自分で表紙に厚紙を貼って製本して持ってきてくれたのです。あちこちに付箋が貼ってあって、線や文字がびっしり書き込まれていました。お役に立てていることがうれしかったですね。
辻山 コロナ禍の話ですが、「ずっと家にいて悶々としていたけれども、本屋に来て、気持ちが落ち着いて自分に戻れた気がします」と言われたこともあります。ほかにも、夕方の4時ごろから本を眺めたり、立ち読みしている大学生ぐらいの男性がいました。不安を抱えていて行き場がないのかなと思ったのですが、聞くわけにもいかず、8時近くになって「そろそろ閉店します」と声をかけたら、「あ、ごめんなさい」と言って、文庫本を何冊か買って帰られた。元気かなと時折思い出すことがあります。
最近、うちの営業担当になった女性は、「通学途中に立ち寄っていて、本が好きになったので出版社に就職しました。担当になれてうれしいです」と言ってくれました。もしここに本屋がなかったら、彼女は別の人生を歩んでいたかもしれない。本が彼女の人生に作用したんだなと思いました。
最近、うちの営業担当になった女性は、「通学途中に立ち寄っていて、本が好きになったので出版社に就職しました。担当になれてうれしいです」と言ってくれました。もしここに本屋がなかったら、彼女は別の人生を歩んでいたかもしれない。本が彼女の人生に作用したんだなと思いました。
二村 私も、3時間ぐらいいらした方に、「何かお探しですか」と声をかけたら、「実は私、鬱なんです」とおっしゃるんです。レジから離れて、別の棚の前で「私でよかったら何でも言ってくださいね」と言ったら、話をしながら涙をこぼされて、思わず抱きしめました。彼女の気持ちに寄り添う本が並んでいたのかもしれませんが、本屋が救われる場所だったのかな、と。
河野 森林浴じゃないけれど、本の気を浴びているだけで気持ちが落ち着きます。私には、時々足を向けたくなる好きな神社の森があるのですが、それに似たような空気性を感じます。
辻山 独立研究者の森田真生さんは、「書店は低エントロピーの場所だ」と言っています。例えばスーパーマーケットは、商品が機能的に配列されているが、その分画一的で、エントロピーが高い。本屋は、並んでいる本一冊一冊に手をかけることでエントロピーが下がって、落ち着いた場所になる。まちに低エントロピースポットがあるのは、人が人として生きていくうえで必要だ、と。
文脈を考えながら本を並べる
河野 お二人はどんなふうに本を並べておられますか? ジャンル別、著者別、大きさ、色合いとか、いろいろ意識しておられるでしょうが。
二村 文脈と言いますか、この本の横にはこれを置いておいたらいいかなというのは考えながら並べていますね。例えば、堀川惠子さんの『永山則夫 封印された鑑定記録』は、罪を犯した永山について、そうならざるを得なかった背景もきちんと書いていますが、その横には同じく、犯罪を犯した側の意志と経緯を描いて、連続企業爆破事件の真実を書いた松下竜一さんの『狼煙を見よ』を並べて置いたりしています。
辻山 本棚の前に立った時に、一冊一冊のタイトルが目に飛び込んでくる場合と、壁画や一枚の絵のようにしか見えない場合があります。ルール化しているわけではありませんが、同じ色合いのものを並べると、シームレスな流れの気持ちよさが生まれることもある。壁画のように見えた文庫本のシリーズから一冊抜いて、同じジャンルの単行本の間に挟むと、際立って見えることもありますね。
二村 私も虹のように色で並べることもあります(笑)。ジャーナリストの稲垣えみ子さんが、うちの本棚を見て「本が主張していますね」と言われました。店主の思いというか、気づいてほしいという主張が出ているのかもしれません。
辻山 本を「見せてあげる」と急に売れ始めることもあります(笑)。常に本を気にするということだと思います。動きが悪いところにちょっと触ると、売れ始めることもありますから。
河野 書く人、つくる人、届ける人、読む人 ― 本の背後には必ず人がいて、実はそういう人たちの存在に私たちは支えられています。その交差点というか、さまざまな思いをつなげる場として、本屋がある。お店に行けば、顔を持った誰かがいるということも大事ですね。自動販売機ではない。
書店経営を取り巻く課題

河野 一方で、いまは書店を続けるのが厳しい状況にあります。WEB(インターネット書店)もあり、出版業界全体にかかわる問題なので、簡単に答えは見つけられません。いろいろな思いをお持ちでしょうが、何か提案や要望はありますか?
辻山 昔から言われている話ですが、本の売上は22%、つまり1,000円売れたら220円です。この歩率が5%上がるだけでも、全然違うと思います。半世紀以上も歩率が変わらないのはいかがなものか。構造的な問題は根強くありますね。
二村 大手の取次以外から仕入れると多少歩率はいいのですが、扱う本が限られていて返品もできませんから、本を買い切る覚悟が必要です。私たち個人経営の独立系書店も覚悟をもって仕入れるので、たくさん買い切る場合は歩率を上げていただきたい。また、大手の取次だと納品までに2週間かかることもあるので、お客さんはアマゾンなどで注文してしまう。構造そのものを変える時期に来ているのではないでしょうか。本気
でやれば、できるのではないかと思います。
河野 出版社や取次会社が、自らの痛みや出血を伴いながらも既存のシステムや組織を改革するのは容易ではありません。誰かがリーダーシップをとって課題を洗い出し、いま何が本質的に問われているのかを可視化し、対策を考えることが大事です。その意味で、経産省の書店振興プロジェクトはひとつの契機になったと思います。
著者、出版社、書店、図書館、読者という知のサイクルがあって、それが目詰まりを起こさないように、それぞれが知恵を持ち寄り、コンセンサスを形成していく必要があります。国や自治体、私たち受益者がそれぞれの立場でできることもあるはずです。
著者、出版社、書店、図書館、読者という知のサイクルがあって、それが目詰まりを起こさないように、それぞれが知恵を持ち寄り、コンセンサスを形成していく必要があります。国や自治体、私たち受益者がそれぞれの立場でできることもあるはずです。
二村 2023年に古物商の資格を取りました。本当に読み継がれてほしい本がどんどん絶版になって出版社から仕入れることができなくなっているので、古本で仕入れようと。本という文化を守ることにもつながると思っています。
辻山 私も古物商の資格を持っています。新刊か、古本かを気にしないお客さんもいますよ。
二村 配本自体が書店の規模でランク付けされていて、うちのような小さな店は、新刊を配本してもらえませんから、自分で読んで勉強して仕入れたほうがいい。いま思えば、それが自分を成長させてくれたのかもしれません。
河野 本を置いておけば売れるという時代ではありません。ただ、経産省のプロジェクトチーム設置は予想以上の大きな反響を呼びました。つまり、今なお書店の存続を願う人、「書店がなくなってもいいのか」と危機感を持つ人が多くいることがわかりました。
必要な本を必要な人に届ける
辻山 本屋に限らず、小売店の売り上げが落ちているのは事実ですが、必要としている人にどう届けるかについては、それぞれの業界で工夫している。例えば魚屋が捌き方や食べ方、調理法を教えるのは、小売を生業にしている以上、当たり前なのではないか。いまは、SNSで情報を発信したり、商品をネットで全国に届けることもできます。最盛期から比べたら規模は縮小したかもしれませんが、必要なものを届けるという点では、ほかの小売店と同じだと思います。
二村 いろいろな人のチェックが入ったうえで世の中に出ますから、本は信頼できる媒体だと思います。だからこそ、そのチカラを信じたい。最近は、出版になる前のゲラを読ませていただいて、自分が納得したうえで仕入れたり、イベントの計画を立てたりしています。根本にあるのは、やはり本への信頼を失いたくないという思いです。大変ですが、やり続けることに意味はあると思っています。
河野 辻山さんの近著『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』(朝日出版、2024年)の帯文が目を引きますね。長谷川書店の長谷川稔さんが書かれた「これだけ愚直というか、淘汰されつつある働きかたには、ますます価値があると思っています」というのは名言です。愚直に、この生き方を選んで、しぶとくやっている人たちがいる。そのしぶとさを生んでいるのは、やっぱり本のチカラだなと思います。
国家百年の計を考えた時に、社会の活力を失わないためには何が必要か、私たちの考えるチカラが問われています。
国家百年の計を考えた時に、社会の活力を失わないためには何が必要か、私たちの考えるチカラが問われています。
(2024年9月4日 公益社団法人日本フィランソロピー協会にて)
機関誌『フィランソロピー』巻頭鼎談/2024年10月号 おわり
クリックすると
拡大します。
拡大します。