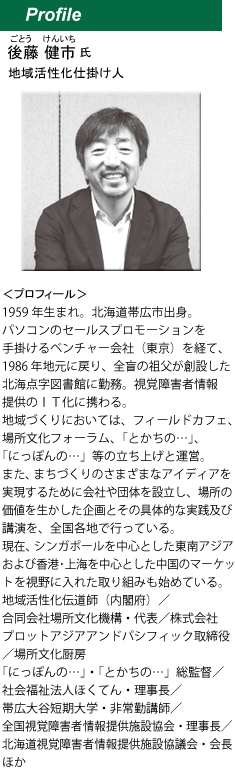

「東京もシンガポールも上海も俺らのまち」
“ホームアジア”で広がる縁側文化
いつもわいわいがやがや、よくわからないけどなんだか楽しそう。縁側はそんな人が集まる「たまり場」だ。地域活性化仕掛け人 後藤健市氏はそんな「たまり場」を戦略的に作り上げるプロフェッショナル。地域活性化の先駆者としてさまざまな企画を立ち上げ、さらに東京と地方を結ぶプランナーとして全国を飛び回ってきた後藤氏だが、今、彼の活躍の場はアジアに広がっている。アジアで「たまり場」づくりに取りかかる後藤氏に話を聞いた。
誰かを笑顔にしたいだから楽しいことをする
― 「縁側文化」で思い浮かんだのが、後藤さんの企画した十勝の場所文化ツアーです。最終日のミーティング会場が個人のお宅だったんです。確か菜種油を作っている方のお宅だったと。歓迎してくださってすごく感激しました。こういう家を外に開いている感覚が縁側文化の本質ではないかと思うのです。
後藤 為広さんの家ですね(笑)。自分の場所を開くという意味で縁側と共通しますね。自分の家でもないのに、お客様を勝手に連れて行ってしまったということですが、素敵な場所なのでつい自慢したくなるんです。
― 後藤さんは東京でお仕事をされた後、28年前に十勝・帯広市に帰って地域活性化を手がけられて、2001年にオープンした「北の屋台」(※1)にも関わられていましたね。
※1: 帯広にできた屋台村。飲食店営業の許可を得ているため、刺身などの生モノも提供できる。焼き鳥、イタリアン、寿司、韓国料理、ブラジル料理など20軒の多種多様な屋台が集まっている。全国各地で北の屋台をモデルとした屋台村が誕生している。
後藤 仲間と一緒に、地域が元気になる楽しいことをしようと活動を始めました。その中の一つの取組みが屋台村です。まちづくりの成功事例ということで評価していただいていますが、初めからすごい計画を立てたわけではないんです。みんな直感的に「これがいいよね」って自然に体が動いた感じで。一方で「そんなのうまくいかないよ」とも言われましたが、結果として成功したのは、やはりそれが必要とされていたということなんでしょう。
― 私も行きましたが、屋台の概念が変わりました。「あっちの店にも行きな」「こっちもおいしいよ」って。それぞれの個店だけでなく仲間同士が一緒に場をつくっていて、お互いの店を応援し合っている感じで楽しかったです。
後藤 「こんなのは屋台ではない」という人もいました。しかし、屋台かどうかの議論をしても意味がない。大事なのはコンセプトです。その場所で人と人が関わり、質の高い時間を過ごすことができればいい。要するに楽しければいいんですよ(笑)。
― 楽しいって大事ですね。帯広から始まった屋台村ブームはどんどん広がって、今年4月には鹿児島にもできて。
後藤 時代が必要としているものは社会に認められ、その結果持続するということです。はじめは直感でも、改めて見なおしてみるとそこにはやはり成功する理由があり、理論が眠っているんです。それを整理して抽出することで、他の地域への展開も可能になるし、私たち自身がそこから多くのことを学ぶことができます。
― なるほど。地域活性化仕掛け人後藤さんならではの発想です。後藤さんは視覚障害者支援もされていますよね。
後藤 支援活動ではなく、仕事です。見えない人、見えにくい人への情報提供をしている組織が集まって作っているNPO法人全国視覚障害者情報提供施設協会の理事長です。地元の帯広でも、祖父・後藤寅市がヘレンケラー女史の来日を機に昭和24年に創設した北海点字図書館の理事長もしています。
― 寅市さんは全盲でいらっしゃった。
後藤 祖父は子どものときの怪我が原因で失明しました。祖父が亡くなったのは私が小学校6年の時でしたが、それまでずっと一緒に暮らしていましたから、小さいときから祖父の手を引いてプールや銭湯、職場にも行ってました。ですから、見えないという障害を身近に感じることで、幼いころからいろいろな人がいる、いわゆる多様性ということを感覚的に捉えていたように思います。
― 幼いときのおじい様との経験は今の仕事にもつながっているようですね。
後藤 はい、つながっていると思います。祖父は「失明によって閉ざされた社会への扉が読書によって再び開かれた。だから自分と同じ障害のある人が、少しでも幸せになるよう良い本と出会ってほしい」との思いから点字図書館を作りました。私の活動の根底にあるのも「誰かを笑顔にしたい」ということなので祖父の思いと共通しますね。福祉の仕事のときは見えない人が対象ですが、地域づくりのときは見えている人も対象者です。要するに、私の仕事はまわりの人をハッピーにするには何をしたらいいのかを考えること。まあ単純に言うと、楽しいことはやる、楽しくないことはやらない、とごくごくシンプルな規範なんですけど(笑)。
自分の中の偏見に気づけば変わることができる
― 後藤さんは小さい頃から心の垣根がなかったんですね。
後藤 いえ、それがあったんです。私自身が自分の中に祖父の目が見えないということに対する偏見を持っていたんですね。小さい頃、祖父の手引をしていると、いろんな人が振り返って私たちを見ます。当時は祖父がどんな人かもわからず、亡くなったあとで祖父の偉業を知ったのですが、「大好きな祖父が目が見えないというだけで、周りの人はじろじろ見る。これは偏見だ、差別だ、そんな社会は良くない!」とずっと思っていました。でも、大人になってあるとき、ふと気づいたんです。周りの誰かではなく、私自身が見えない祖父のことを実は恥ずかしいと思っていたことに。私が見えないことをマイナスに感じていたから周囲の視線を偏見だと受け止めていた。周りの誰かではなく、全て私自身の心の問題だったんです。
― 他人の視線は自分の心の鏡だった。
後藤 祖父の座右の銘は「愛盲」です。自分は見えないという障害があったからいろいろな人に出会えたし、さまざまなことををやってこられたと。祖父は自分が見えないことを全く恥じておらず、逆に与えられた環境をプラスに捉えているんですね。私も祖父のこの言葉、考え方を自分自身の原点として、決して忘れてはいけないと思っています。
― 問題は自分にある。それに気づくことで見える世界は大きく変わりますね。
後藤 私のもう一つの仕事である地域活性化でも同じことが言えます。まちをだめにしているのは、行政や国ではありません。自分たち自身です。例えば、東京に対して他の道府県は東京一極集中は困ると文句を言います。北海道では札幌ばかりでは困ると言い、十勝エリアでは帯広ばかりで困るとなる。さらに周辺の町村に行くと本町ばかりで…、結局この文句に終わりがないんです。東京ばかり…ではなく、日本人である私たちにとって東京も「俺らのまち」だと思えばいい。「ちょっとまち遊びに行ってくるわ」って言いながら、帯広から東京に行けばいい(笑)。東京の魅力は日本の多様な価値が集約されていること
ほめ合うことが大事
― 東京という場を使った地域活性化の一つの具体的な取り組みが東京有楽町の国際ビル「KUNIGIWA」(※2)の中にある「とかちの…」「にっぽんの…」(※3)ですね。
※2: 丸の内仲通の有楽町駅側に建つ「国際ビル」地下1階に2007年誕生した1,200㎡の飲食ゾーン。「丸の内の地下に市場のような賑わいのある界隈をつくる」ことがテーマ。現在国際色豊かな
28店の飲食店が営業している。
※3: KUNIGIWAにある飲食店。「とかちの…」では十勝のじゃがいも、地元小麦のピザ、チーズが楽しめる。「にっぽんの…」は厳選された日本全国の美味しい食材やお酒を活かした料理が人気。
 後藤 「KUNIGIWA」は単なる飲食店の集合ではなく、都会のたまり場として、その場全体として魅力のある空間を提供することをコンセプトとして始めた場所です。「今日どこ行く?」の返事は「とかちの…に行こう」ではなく、「KUNIGIWAに行こう」となるような場になるのがいいと私は思っています。でも、今はまだそれぞれの店にお客様が来ている状態ですが。
後藤 「KUNIGIWA」は単なる飲食店の集合ではなく、都会のたまり場として、その場全体として魅力のある空間を提供することをコンセプトとして始めた場所です。「今日どこ行く?」の返事は「とかちの…に行こう」ではなく、「KUNIGIWAに行こう」となるような場になるのがいいと私は思っています。でも、今はまだそれぞれの店にお客様が来ている状態ですが。
― 以前、「とかちの…」に伺って素敵だと思ったのは、地元のものだけを使っていないことでした。塩は長崎のものがいいから使うとか。地域ナショナリズムではない。これは地域の縁側化でしょうか。
 後藤 まさに地域の縁側化といえますね。「しばり」と「こだわり」のメモリがある1本の物差しがあると考えてみてください。あるポイントを過ぎると、「こだわり」が「しばり」になってしま
う。何でもかんでもそこの地方のものでないといけないというのは、こだわりではなく、しばりであり、そこに来たお客様にとってハッピーとは限らない。地域の「こだわり」を軸に置きながら、そこに来てくださった方々が楽しめるように工夫することが大事です。いろんな地域が補完しあう関係がまちづくりでは大切なんです。
後藤 まさに地域の縁側化といえますね。「しばり」と「こだわり」のメモリがある1本の物差しがあると考えてみてください。あるポイントを過ぎると、「こだわり」が「しばり」になってしま
う。何でもかんでもそこの地方のものでないといけないというのは、こだわりではなく、しばりであり、そこに来たお客様にとってハッピーとは限らない。地域の「こだわり」を軸に置きながら、そこに来てくださった方々が楽しめるように工夫することが大事です。いろんな地域が補完しあう関係がまちづくりでは大切なんです。
― 自分を売る前に地域を売る、地域の前に日本を売る。やせ我慢も大切ですよね。
後藤 ほめ合うことが大事です。例えば、北海道の地域づくりも、札幌、函館、帯広、旭川、釧路…とそれぞれがバラバラに動いていました。だから札幌と函館どっちがいいか、みたいな議論になってしまいます(笑)。そうではなく、例えば帯広の人が「北海道には、神戸にも劣らない歴史的な建物がある函館があるぞ!」と自分の地域として自慢することが大切だと思います。日本中のどの地域のことも自分の地域として自慢する。もっと言えばアジアでもそうしたらいいと思います。中国とは政治的にもいろいろあるけど、「上海の外灘(ワイタン)の景色はアジアの宝だよね」とアジア人として自慢する。そうすれば中国の人も喜ぶし、お互いの心の垣根が低くなる。相手をほめることが大事なんです。
― 上海も「俺らのまち」なんですね(笑)。それぞれに個は個であってでも、お互いにほめ合って大きくつながる。しかし、近親憎悪というか、互いの距離が近いほうが難しいですよね。
後藤 そうかもしれません。それで今、視野を広げるために、地域づくりの取り組みをアジアに展開しているんです。
ホームアジアで広がる縁側のこころ
― えっアジアにですか!どちらの国に?
後藤 香港とシンガポールがメインです。香港は中国本土も視野に入れての取り組みであり、シンガポールは東南アジアからインドまでカバーすることを想定しています。今までは東京ローカルという言葉のもと、地域活性化の連携先として東京を使っていましたが、人口減や高齢社会などの状況もあり、日本国内のマーケットだけで地域経済の成長もしくは維持は無理、だから、これからはアジアも視野に入れようと思って。
― ローカルからグローバルですか?
後藤 いえ、アジアローカルです。私たちがアジアでつながる場所はいわゆるピカピカな場所ではないんです。シンガポールもベイサンズのような場所は、最先端であり、最高級が集まる世界につながるグローバルな場所。でもローカルな場所もあります。そういった場所を日本の地方(ローカル)につなげながら新たな関係を生み出していきたいと考えています。これまで東京を使って活動してきましたが、同じようにアジアに自分たちの場所を作ることができたら、アジアともつながれるでしょ?そうしたら「俺はアジア人だ」というホームアジアな関係ができるはずなんです。
― ホームアジア、素敵な言葉です!
後藤 アジア展開のインフラも整ってきたので、ようやく中小企業や地方がアジアと関われる時代になったんです。簡単でないですよ。しばらくは失敗も含めたトライアルが続くでしょう。でも、
10年後には今、熱く議論していることがごく当たり前のことになっていると思います。そうするためにも今は、そのことを意識して、かつ覚悟を持ってアジアの場づくりを仕掛ける必要があります。
― どのような場づくりをしたいと思っていますか?
後藤 やはり食が中心ですね。しかし、ただ食材を売るということではありません。食べることは全ての要素を含んでいます。生産者の食材に対するこだわりもありますし、物流業やレストランといったサービス業も大きく関わります。「食事」という言葉を見ると、食に事(コト)がつく。ただ栄養補給をしているのではなく、使う器のこだわり、調理方法、料理の出し方、さらに食べ方も含めたさまざまな作法といった文化面の要素もあります。楽しみ方も幅広くあるし、年齢も、子どもから年寄りまで広がりもあります。
― 確かに、食事には文化も産業もたくさん関係しています。日本政府も力を入れている観光にもつながりますね。
後藤 おもてなしの心の欠如については、アジア各国ではサービス業の現場だけではなく、政府も困っています。では誰がそれを教えられるのか。日本しかないですね。我々のおもてなしは、マニュアルで対応するホスピタリティーとは異なるもので、自分のこころを開いて相手を受け入れるという、縁側文化につながる人と人との関係性、相手への思いやりが根底にあります。その関係性の宝庫が田舎ですよね。そんな〝おもてなし〟のこころを学びたいアジアの人を、日本の田舎を受け皿にして、新しい教育プログラムを作ることを今後の観光の一つの切り口にできると考えています。
― まさに為広さんの家ですね(笑)。
後藤 これまで観光というと、ホテルや航空会社など一部の観光関係者だけをステイクホルダーだと捉えていました。でも、今は違います。地域全体がステイクホルダーにならないといけません。 自分は観光業でないから関係ないと思うのをやめたほうがいい。人が外から来ればそこにお金が流れます。地域に流れるお金の受け皿となるベースを作るのだから、当然そのもとになる人を迎えることをみんなで支えなければ。
自分は観光業でないから関係ないと思うのをやめたほうがいい。人が外から来ればそこにお金が流れます。地域に流れるお金の受け皿となるベースを作るのだから、当然そのもとになる人を迎えることをみんなで支えなければ。
 自分は観光業でないから関係ないと思うのをやめたほうがいい。人が外から来ればそこにお金が流れます。地域に流れるお金の受け皿となるベースを作るのだから、当然そのもとになる人を迎えることをみんなで支えなければ。
自分は観光業でないから関係ないと思うのをやめたほうがいい。人が外から来ればそこにお金が流れます。地域に流れるお金の受け皿となるベースを作るのだから、当然そのもとになる人を迎えることをみんなで支えなければ。
― 一人ひとりが意識を変えることで、地域が大きな縁側になるんですね。
後藤 地域の質が上がったとき、その地域は人がわざわざ来る場所になるんです。観光名所、例えば札幌の時計台は一度行ったらもう行かなくてもいいですよね。でも、対象が人の場合は一度会って気が合ったら、何度でも会いたくなります。その人の顔が見たい、また一緒に酒を飲みたい、そんな理由で人は何度でもその場所であり店に足を運びます。一番の資源は人なんです。それが地域の景観や文化、さらに食などと重なって総合的な魅力になる。それがホームアジア的な関係性を広げる鍵になるんです。
― 後藤さんのお話は常に人がキーワードですね。
後藤 アジアに行くときも、人に会いに行くという意識を持つことを大切にしています。日本のさまざまな地域がアジア各国にアプローチしていますが、目的が食材等の販路拡大だから、「うちの県の○○牛は△△牛より美味しい」と日本の他地域と足の引っ張り合いになってしまっている。そういう物売り展開をやめて、人と人との関係性を作りに行くという意識を持つことが大切です。それができれば、その人が持っている商品に違う意味と価値が生まれます。そして、相手の人がその商品を勝手に自分たちのワールドで広げてくれる。それが豊かな関係、持続可能な関係だと思います。
― アジアというマーケットでも人と人のつながりが原点ですね。
後藤 よく「13億人のマーケットがあるからすごい」とか言いますよね。でもそれはおかしい。だって、どうせそんなに作れないし、必要ないでしょ?自分の地域や会社の生産規模などを考えてちゃんと計算したら、1,000人でいいかもしれません。そう考えたらやるべきことがもっと明確になる。
― 夢が膨らみますね!
後藤 アジアとつながることで、改めて東京の価値が見えてきました。やはり日本のメインゲートは東京です。今度はアジアを意識しながら東京を使うことを考えていくことになりますが、それはとても重要だと思っています。先日決まった2020年東京オリンピックは、日本に将来への目標となる一つの灯を掲げてくれましたが、今、私にとってシンガポールが一つの灯台になっています。明るいな、あれに向かっていけばいいんだと。
― 後藤さんの原点は、おじい様の「愛盲」精神ですね。盲を愛する、要するに人を愛するということ。人の笑顔が好き。だから、人を笑顔にする場づくりと関係づくりをしているのですね。多様な縁側文化をあちこちで仕掛けてください。考えるだけでも笑顔になれそうです。今日は、ありがとうございました。
インタビュー
公益社団法人日本フィランソロピー協会
理事長 高橋陽子
公益社団法人日本フィランソロピー協会
理事長 高橋陽子
当協会機関誌 『フィランソロピー』 No.358/2013年10月号 に掲載