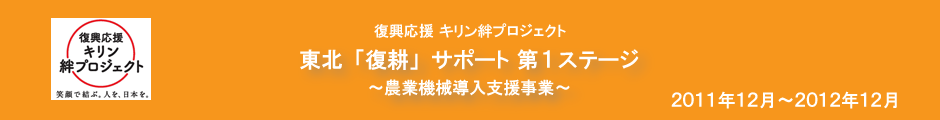
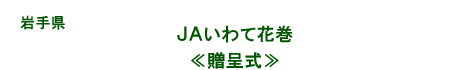
日時: 平成24年(2012年)12月12日(水)■10:30~11:45
会場: JAいわて花巻東部地区営農センター
会場: JAいわて花巻東部地区営農センター

≪開会あいさつ≫
古賀 朗
キリンビール株式会社 CSR推進部 |
≪贈呈者代表あいさつ≫
石田 雄治
キリンビールマーケティング株式会社 岩手支社長 |
 おはようございます。本日は「復興応援キリン絆プロジェクト東北復耕サポート」農業機械贈呈式にご出席いただき、ありがとうございます。
おはようございます。本日は「復興応援キリン絆プロジェクト東北復耕サポート」農業機械贈呈式にご出席いただき、ありがとうございます。キリングループでは皆さまの復興の応援をするため、できる限りニーズにあったものをご用意し、贈呈をさせていただくという活動をしております。もちろん、これが支援のすべてであるとは考えておりません。今後とも、少しでも皆さまのお役に立てるようにと考えております。
※キリンビール株式会社 CSR推進部・古賀朗氏より補足説明
キリンビールは農業復興の支援金として、2011年末に公益社団法人日本フィランソロピー協会に4億円を拠出いたしました。キリン絆プロジェクトでは、多方面のご協力の下、当協会において農業機械に支援事業、東北農業復興サポートを行い、支援金の助成を行なっています。助成に際しましては被災された皆さまからの申請に基づき事業選考審査を行い、公正な手続きにより決定の後、助成金の支出を行っております。
キリンビールは農業復興の支援金として、2011年末に公益社団法人日本フィランソロピー協会に4億円を拠出いたしました。キリン絆プロジェクトでは、多方面のご協力の下、当協会において農業機械に支援事業、東北農業復興サポートを行い、支援金の助成を行なっています。助成に際しましては被災された皆さまからの申請に基づき事業選考審査を行い、公正な手続きにより決定の後、助成金の支出を行っております。
桑名 隆滋
公益社団法人 日本フィランソロピー協会 事業開発チームリーダー |
 私どもの仕事は、企業様と被災者の方々との間を取り持つ「仲立ち」の仕事が主であります。まだまだ不十分なところもあるかと思います。また、時の経過と共に、皆さまにもさまざまな状況の変化があり、時に予想外の困難に陥っているケースもあるかと思います。私どもの想像力が及ばない、多種多様な局面に立ち会われていることでしょう。私どもは、できることをひたすら愚直にやっていきたいと考えております。
私どもの仕事は、企業様と被災者の方々との間を取り持つ「仲立ち」の仕事が主であります。まだまだ不十分なところもあるかと思います。また、時の経過と共に、皆さまにもさまざまな状況の変化があり、時に予想外の困難に陥っているケースもあるかと思います。私どもの想像力が及ばない、多種多様な局面に立ち会われていることでしょう。私どもは、できることをひたすら愚直にやっていきたいと考えております。
≪目録贈呈≫
贈呈内容説明/伊藤 一徳
贈呈内容説明/キリンビール株式会社 CSR推進部
贈呈内容説明/キリンビール株式会社 CSR推進部
トラクター9台
田植機5台
管理機8台
運搬機1台
刈払機1台
以上合計24台、総額16,850,600円です。
田植機5台
管理機8台
運搬機1台
刈払機1台
以上合計24台、総額16,850,600円です。
贈呈者/石田 雄治
贈呈者/キリンビールマーケティング株式会社 岩手支社長
贈呈者/キリンビールマーケティング株式会社 岩手支社長
贈呈者/桑名 隆滋
贈呈者/公益社団法人日本フィランソロピー協会 事業開発チームリーダー
贈呈者/公益社団法人日本フィランソロピー協会 事業開発チームリーダー


≪受贈者謝辞≫
雲南 幹夫 様
釜石市地域農業復興組合 役員 |
 本日はこのような貴重なご支援をいただき、誠にありがとうございました。私たちは釜石市の指導の下、農業復興組合を設立させ、4月から先月11月まで施策を打ってまいりました。3.11の大震災によって大切な畑や用地、そして数々の農業機械を失い、途方に暮れておりました。それでも皆作業に明け暮れながら、復興への想いを日に日に強くしております。そうした中で「農業機械の支援」という夢のような知らせが届き、今日それが現実となりました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
本日はこのような貴重なご支援をいただき、誠にありがとうございました。私たちは釜石市の指導の下、農業復興組合を設立させ、4月から先月11月まで施策を打ってまいりました。3.11の大震災によって大切な畑や用地、そして数々の農業機械を失い、途方に暮れておりました。それでも皆作業に明け暮れながら、復興への想いを日に日に強くしております。そうした中で「農業機械の支援」という夢のような知らせが届き、今日それが現実となりました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。私たちは現在、土地区画整理事業を進める中、復興に必要とされる組織を申請・運営していく予定です。今後の私たちに必要なのは、この機会をきっかけに農業をより魅力的なものにし、それによって従農者の高齢化、後継者の不足といった課題を解消していくことであると考えております。今回のご支援を有益に活用し、今後の復興作業に関わる中で、大きな役割を果たせるよう、力を注いでまいります。
鈴木 堅一 様
釜石市鵜住居(うのすまい)地区 |
 本日はこのような贈呈式にお呼びいただき、ありがとうございました。私事になりますが、実は4人の家族を亡くしております。私のほかにも大勢、家族を亡くした者がおります。鵜住居地区はご覧いただいた通り、一部の田んぼが復旧している以外、ほとんどが営農できる状態ではありません。このような状況で、誰もが「農業を続けるか否か」の選択を迫られておりました。しかし、本日このような農業機械の支援をいただき、営農再開へ向けての大きな励みになりました。今日のご支援を胸に、今後も励んでいきたいと思っております。
本日はこのような贈呈式にお呼びいただき、ありがとうございました。私事になりますが、実は4人の家族を亡くしております。私のほかにも大勢、家族を亡くした者がおります。鵜住居地区はご覧いただいた通り、一部の田んぼが復旧している以外、ほとんどが営農できる状態ではありません。このような状況で、誰もが「農業を続けるか否か」の選択を迫られておりました。しかし、本日このような農業機械の支援をいただき、営農再開へ向けての大きな励みになりました。今日のご支援を胸に、今後も励んでいきたいと思っております。
阿部 德造 様
大槌町地区 |
 本日はひと言お礼の言葉を申し上げたいと思います。この度は農業機械のご支援をいただき、誠にありがとうございました。感謝を申し上げます。地域全体で営農へ向け有効活用をしていきたいと思っています。
本日はひと言お礼の言葉を申し上げたいと思います。この度は農業機械のご支援をいただき、誠にありがとうございました。感謝を申し上げます。地域全体で営農へ向け有効活用をしていきたいと思っています。
≪JAグループ協力団体ごあいさつ≫
高橋 専太郎 様
花巻農業協同組合 代表理事組合長 |
 この度のご支援、誠にありがとうございました。今ここにおられる生産者の方々は全員、私どもの組合員です。ほとんどが身内を失い、家を流され、大変な思いをした方ばかりでございます。そうした中、全国より大変なご支援を頂戴し、また全員が復興へ向け日々頑張っておりますが、ご覧の通り、営農にはまったく手が付けられておりません。
この度のご支援、誠にありがとうございました。今ここにおられる生産者の方々は全員、私どもの組合員です。ほとんどが身内を失い、家を流され、大変な思いをした方ばかりでございます。そうした中、全国より大変なご支援を頂戴し、また全員が復興へ向け日々頑張っておりますが、ご覧の通り、営農にはまったく手が付けられておりません。厳しい最中ではございますが、「キリン絆復興プロジェクト」ということでこの度、皆のモチベーションが高まるような素晴らしい支援をいただきました。全組合員を代表し、心から感謝と御礼を申し上げる次第でございます。ありがとうございました。
3.11以来、今申し上げた厳しさに加え、福島の原発事故による放射能の風評被害がございます。生産者のみならず、岩手県民全員が辛い想いをしている現状があります。こうした皆さまの想いをきちんと受け止めながら、我々は今後、被災地をきちんと農業ができる環境にしていかなければなりません。農協としてそう強く感じつつ、皆さまの努力にきちんと報いなければと、思いを新たにしているところです。
この農業機械を有効活用することで、営農の再開、活動に弾みがつくことになると思います。
小田島 利昭 様
全国農業協同組合連合会 岩手県本部 副本部長 |
 私ども全農とキリンビール様は、復興を通じ、社会貢献するという部分で協力関係にございます。
私ども全農とキリンビール様は、復興を通じ、社会貢献するという部分で協力関係にございます。先月に縁ありまして、キリンビール・磯崎社長の講演を聞く機会がございました。そこで磯崎社長は今後キリンビールが進んでゆく道として、「CSV」のお話をされておりました。いわく「CSV」とは、ただの事業ではなく、地域の課題を解決していくための存在であるとのこと。まさに私たち全農も同様の立場にあるわけでございます。我々もぜひCSVとして、さらなる協力をしていければと考えております。
今回は支援された農業機械と、生産者の皆さまとのニーズをマッチングさせていただいたわけですが、支援を受ける方が本日全員ご出席されていると聞き、非常に驚いております。
農業機械は重要な生産資材でございます。今回は生産者の皆さまからの「こんな農業機械が欲しい」というニーズに対し、中古の農業機械で応えさせていただきました。本プロジェクトは、エコと絆を結びつけた壮大なプロジェクトであったと思います。
これまでも岩手県内で、同様のマッチング作業をしておりましたが、なかなか実際は欲しいものと供給できるものとの間に、ギャップがあるものだと感じておりました。しかし本件に関しては県内全体で上手くマッチングでき、190台の農業機械のご支援に対し、さまざまな審査を通して生産者の元へ渡ったのが114台と聞いております。全農としても一つの成果を残せたのではないでしょうか。
今後も厳しい農業情勢が続きますが、一日も早く営農を再開し、来年の収穫時にはみんなでキリンビールを飲みながら、いい秋を迎えられるように今後とも頑張っていきましょう。
≪懇談≫
≪閉会あいさつ≫
古賀 朗
キリンビール株式会社 CSR推進部 |
私どもの農業機械支援は、来週に贈呈式を1つ残し、すべて終了ということになります。
東北3県の皆さまに対し、当初は4億円の規模で考えておりましたが、最終的には5億2,000万円、合計386台の機械をお届けすることができました。これにはJA様はもちろん、全農様を通じ全国からいろんな農業機械を集めていただき、生産者の皆さまからのニーズとマッチングをしていただいた結果でございます。3県全体で中古の比率は44%程度となっておりまして、実にさまざまなところから農業機械が届いております。ぜひ皆さま方に農業機械を活用いただき、一日も早く営農再開をしていただきたいと思っております。
我々としても今回の支援で終了というふうにはまったく考えておりません。皆さまが生産した生産物を新ブランドとしてPRすること、あるいは今までになかった販路を開拓し、より多くの場所へ向けて販売をしていくことなど、私どもにできるお手伝いが、ほかにも必ずあるはずだと思っております。
私どものテーマは生産から食卓までの支援です。ビールもまた食卓で味わっていただくものですが、そのビールの横に皆さま方が生産したものがあるという姿を描いております。
先日は気仙沼で茶豆が復活したことを受け、「気仙沼茶豆」をキリンビールの系列である飲食店「キリンシティ」で販売させていただきました。実は収穫時期の関係で、提供する枝豆の品種を2週間ごとに入れ替えておりますが、そうした数々の枝豆の中、気仙沼茶豆の売り上げがNo.1になったそうです。
また今月は七ヶ浜で大豆が復活したということで、豆腐店とマスコミにお声掛けをし、PRをさせていただきました。まだまだ厳しい状況にあるかとは思いますけれども、岩手県でも、来年には新たな生産物が出荷されると思います。皆さまのところで、こうしたお手伝いができる部分があれば、ぜひお声掛けください。
東北3県の皆さまに対し、当初は4億円の規模で考えておりましたが、最終的には5億2,000万円、合計386台の機械をお届けすることができました。これにはJA様はもちろん、全農様を通じ全国からいろんな農業機械を集めていただき、生産者の皆さまからのニーズとマッチングをしていただいた結果でございます。3県全体で中古の比率は44%程度となっておりまして、実にさまざまなところから農業機械が届いております。ぜひ皆さま方に農業機械を活用いただき、一日も早く営農再開をしていただきたいと思っております。
我々としても今回の支援で終了というふうにはまったく考えておりません。皆さまが生産した生産物を新ブランドとしてPRすること、あるいは今までになかった販路を開拓し、より多くの場所へ向けて販売をしていくことなど、私どもにできるお手伝いが、ほかにも必ずあるはずだと思っております。
私どものテーマは生産から食卓までの支援です。ビールもまた食卓で味わっていただくものですが、そのビールの横に皆さま方が生産したものがあるという姿を描いております。
先日は気仙沼で茶豆が復活したことを受け、「気仙沼茶豆」をキリンビールの系列である飲食店「キリンシティ」で販売させていただきました。実は収穫時期の関係で、提供する枝豆の品種を2週間ごとに入れ替えておりますが、そうした数々の枝豆の中、気仙沼茶豆の売り上げがNo.1になったそうです。
また今月は七ヶ浜で大豆が復活したということで、豆腐店とマスコミにお声掛けをし、PRをさせていただきました。まだまだ厳しい状況にあるかとは思いますけれども、岩手県でも、来年には新たな生産物が出荷されると思います。皆さまのところで、こうしたお手伝いができる部分があれば、ぜひお声掛けください。
≪記念撮影≫

≪生産者インタビュー≫
雲南 幹夫 様
釜石市地域農業復興組合 役員 |
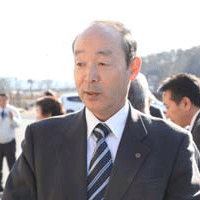 私たちの農地があるのは唐丹(とうに)町というところです。山のふもとから海の方まで約100世帯ほどありまして、津波でおよそ20世帯ぐらいの方が被災されています。現在は特に水田をお持ちの方中心に、復興を計画を進めています。
私たちの農地があるのは唐丹(とうに)町というところです。山のふもとから海の方まで約100世帯ほどありまして、津波でおよそ20世帯ぐらいの方が被災されています。現在は特に水田をお持ちの方中心に、復興を計画を進めています。畑はほとんどが小規模なもので、ほぼすべての皆さんが水稲を作っていますね。稲作は、農業機械さえあれば、実はあまり手が余りかかりません。田植えや刈り入れのときにだけお手伝いしてもらえれば大丈夫なぐらい。私自身、稲作に必要な農業機械がほとんど揃っていましたから、大抵の作業を一人でやっていました。
現在、畑に関しては畑を掘って土を入れ替える、ということをやっていて、現在はGOサインが出れば来春から営農できるところまで来ています。今年の10月ぐらいにおおよその表土入れ替えが終わりました。私の周辺だけで7町から8町歩ぐらいの面積になりますでしょうか。
震災前、このあたりは農地が細かく点在していましたが、復興にあたり区画整理を行ないました。「換地」というんですが、例えばAさんとBさんの土地を一緒にして、2haぐらいのまとまった広さにし、農業機械が入って作業しやすいようにする。効率化を図るために農地を集積し、協同でやりましょう、ということを現在進めています。
実を言うと最初、区画整理に際して「もめるかな」と考えていました。しかし皆さん非常に協力的でして、おかげでスムーズに進んでいます。今後は工事が入り、個々の問題を解決しながら進めていく段階に入りました。唐丹の方は皆さん真面目で、一生懸命作業する方ばかりですよ。年齢層は40代から80代前半ぐらいまで、と非常に幅広く、兼業される方がほとんどですね。漁業をされている方が1割で、あとは私のようなサラリーマンです。みんなで集まって情報交換しながら作業しています。
鈴木 堅一 様
釜石市鵜住居地区 |
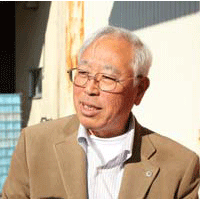 私が住んでいたのは鵜住居(うのすまい)の中心地です。かあちゃんが津波で流されてしまい、現在は1人で農作業をやっています。津波が来る前はちゃんと、ここにいたんだけれど…。かあちゃん含め家族4人、津波で一気に持って行かれてしまいました。今は「何かやらないと」と思って動いています。ただボーっとしていると、かえって辛いですからね。
私が住んでいたのは鵜住居(うのすまい)の中心地です。かあちゃんが津波で流されてしまい、現在は1人で農作業をやっています。津波が来る前はちゃんと、ここにいたんだけれど…。かあちゃん含め家族4人、津波で一気に持って行かれてしまいました。今は「何かやらないと」と思って動いています。ただボーっとしていると、かえって辛いですからね。震災前は400坪ぐらいの広さの畑を持っていました。作っていたのは枝豆とか、普段食べるような栽培が簡単なものだけですが。鵜住居はわりとこんな風に「自分が食べる分だけ作る」という人が多いですね。内陸の人ですと、田んぼも何町歩と持っているけれど、この辺りではせいぜい5、6反がいいところでしょうか。
1年耕さないと、土が固まってしまうんですよ。塩害は、海水も年々薄まっていくので放って置いても大丈夫なんですが、土をそのまま置いておくのはよくないんです。ガレキはほぼすべて撤去しました。ただのガレキじゃなく、釘やガラスなんかが入っているもんですから、作業が大変で…。営農の準備として、表土を新しく土と入れ替えているんですが、ガレキと一緒に畑の表土を30cmぐらい持っていく必要があり、それまで育てていた“いい土”を失ってしまったのが残念でしたね。
今一番心配しているのは「農地がどのような形で返却されるのか」。それだけです。現在、津波で流失したエリアには制限がかかっていて、こちらで手を付けられない状態なんです。農地にしても、宅地にしても、これからのことは分からない。今住んでいる仮設住宅が、もといた場所から5kmほど離れた場所にあるもので、復旧作業をするために仮設から通うのも大変でなんです。とにかく早く何かを作ってやらないと。でもきっと、再開するのに5年はかかるでしょうね。そういう状況なので、今回支援していただいた農機具届いたら、知り合いのところで畑を手伝いながら、農作業を楽しもうと思っています。「ここを使え」と言われている場所があるもので。
以前ならかあちゃんと2人でケンカしながら農作業していたんですけどね。私が「枝豆撒け」と言えば、あっちは「いや、別のを撒け」って言い合いながら。2人で農作業するには広い畑だったので、最終的にはお互いに撒きたいものを撒いて、配りたいところに配ってね。でもいまじゃケンカ相手もいなくなってしまった。とにかく、楽しみながらやらないと。何かやらないと頭がおかしくなりそうだから。
でもJAの方に今回のことで声を掛けてもらって本当に良かったですよ。これが無かったら今、何もしていなかったと思いますから。少しずつ、やっていかないと。楽しんでやらなきゃ。後戻りはできないから、前を向いていかないとね。
≪現地視察≫
アテンド/菊池清重 様・及川秀徳 様
JAいわて花巻 |
 閉会後は、現在復旧中の「鵜住居地区」「唐丹地区」の圃場(ほじょう)視察を行いました。大槌町では、農地復旧のために表土の入れ替えを進めています。現在の圃場は、ガレキの混じった土をすべて取り去り、新しい土を待つばかり。早ければ来年春より営農を再開できるそうです。どの方も手ごたえを口にしていました。
閉会後は、現在復旧中の「鵜住居地区」「唐丹地区」の圃場(ほじょう)視察を行いました。大槌町では、農地復旧のために表土の入れ替えを進めています。現在の圃場は、ガレキの混じった土をすべて取り去り、新しい土を待つばかり。早ければ来年春より営農を再開できるそうです。どの方も手ごたえを口にしていました。≪鵜住居地区≫
 ここは今、ちょうど土を掘った状態ですね。深さ的には60~70cm位。初めは遠野から土を持ってきていたんですが、それも足りなくなってしまったので、最終的にはあちこちから土を持ってきていました。運び入れる土は主に、畑から持ってきているようですね。遠野は「大笹」という場所の土なんですが、かなり深い部分まで土の状態が良いんですよ。あまり砂利なども入っていませんし。しかしそれだけではまかなえず、最終的には宮城県からも土をもらっていたようです。
ここは今、ちょうど土を掘った状態ですね。深さ的には60~70cm位。初めは遠野から土を持ってきていたんですが、それも足りなくなってしまったので、最終的にはあちこちから土を持ってきていました。運び入れる土は主に、畑から持ってきているようですね。遠野は「大笹」という場所の土なんですが、かなり深い部分まで土の状態が良いんですよ。あまり砂利なども入っていませんし。しかしそれだけではまかなえず、最終的には宮城県からも土をもらっていたようです。大槌町では特に塩害対策はせず、どこも土の入れ替えによって農地を復旧させています。ここに土が届くのは、おそらく来春あたりでしょう。ロータリーで一度代掻きして、土をまぶして。この辺りだと田植えはだいたい5月15日に行います。実は水路にも大きなダメージを受けていまして、インフラがまだ復旧していません。こちらは来年営農できるかどうかの瀬戸際ぐらいですね。農地の復旧と同時進行で、インフラの復旧も進めています。水源となる川がすぐ近くにありますので、そこから水を引くための整備を行います。
これまで作っていたのは、コシヒカリとあきたこまち。近頃ひとめぼれが増えてきましたが、やはりあきたこまちが主流ですね。こっちの方は、遠野と比べるとかなりあたたかく、雪もさほど残りません。距離はあまり離れていませんが、トンネルを抜けると別世界になりますからね。遠野は本当に雪深くて、冬の作業が大変です。
≪唐丹(とうに)町地区≫
 この辺りも全部田んぼですね。唐丹町は再来年からの作付けになる予定です。この一帯全部が、ここから見える、あの海から直接波を被ったんですよ。27世帯あった中、残ったのは1軒だけでした。
この辺りも全部田んぼですね。唐丹町は再来年からの作付けになる予定です。この一帯全部が、ここから見える、あの海から直接波を被ったんですよ。27世帯あった中、残ったのは1軒だけでした。現在は「換地委員会」が、農地の集積を行なっています。「あなたの畑はこうなりますよ」という図を起こし、それに関する了解を取りつつ取り決めをして。換地にあたっては、例えば「年を取ってもう農作業ができない」という方から提供いただいた農地などを集めつつ、営農を続ける方全員で一緒にやりましょう、という流れになっています。
私も1回だけ会議に出席しましたが、換地自体への反対意見はなかったですね。皆さん、非常に前向きで復興に望んでいらっしゃいます。一方、同時進行で農地自体の工事も進め、土を入れるばかりの状態まで持って来ました。大体1年ぐらいかかったでしょうか。現在は、せっかく支援いただいた機械をしまっておく場所がないので、保管庫を作るところです。皆さん仮設にお住まいですし、そこへトラクターを持って行くわけには行きませんからね。
JA管内の被災地で、復興組合が一番早くできたのがここなんです。この機会を上手に利用する方と、「いやーどうしようかな」とためらう方で、後々差がつくのではないかと個人的には思っています。換地を行うと、どうしても農地の所有面積が狭くなった人と、広くなった人とが出てきますが、そこは広くなった分を狭くなった人から購入する、という形をとることで、解決しています。
この一帯は、ヤマセが厳しいですが雪は少ないんです。地盤沈下の影響も多少はありましたが、満潮時でもギリギリ入ってこない程度で収まっています。釜石市では満潮になると水浸しで通行止めになるところもあると聞きますが、こちらはまだいい方でしょう。
もともとJAでは「大槌で冬野菜を作ろう」という計画を進めていました。震災があったため一時中断していましたが、今年から仕切り直し、試験栽培を再開したところです。来年は通算で3年目になるので、いよいよ実践試験に入ろうと思っているんです。第1弾は「冬獲りキャベツ」 。現在は大槌で作っていて、今年は澤山地区と、種沢地区の奥の方で作ります。第2弾に予定しているのは「寒締めホウレンソウ」。あとは、老齢者でも重くないニラとかアスパラといった軽量野菜の栽培も予定しています。
三陸自動車道の大槌ICができると、今日、贈呈式を行なった場所が降り口になるんです。それをきっかけにして、今度営農センターと産直施設ができることになりました。せっかく産直ができるのに、冬に出す物がないって言うのは寂しいですからね。ゆくゆくは大槌の特産品をたくさん出せるようにしていきたいですね。