◆特別インタビューNo.337/2011年2月号
世界のどこかで苦しんでいる人に
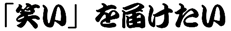
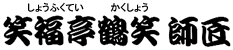
 <プロフィール>
<プロフィール>1960年兵庫県生まれ。1984年六代目笑福亭松鶴に入門。1990年ニューヨーク公演を皮切りに、バンコク・上海・ロンドンなど世界各国で国際派落語家として活躍。2000年から家族でシンガポールに移住。同年、南アフリカ公演でスワヒリ語を交えて現地の民話を落語化し、朝日放送でドキュメンタリー番組となる。さらに同年、在トルコ日本大使館およびNGOの依頼により、トルコ大地震公演。仮設住宅を訪ね、トルコ語でパペット落語を公演。2003年芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。文化庁の「文化交流使」第一号に指名される。翌年渡英。ロンドンを中心に文化交流活動を開始。2006年特定非営利活動法人「国境なき芸能団」代表となる。
「国境なき医師団」は知っていても、「国境なき芸能団」を知る人は多くはないだろう。2006年に立ち上がったこの芸能団は、メディアから忘れられ、NGOの援助も届きにくい厳しい状況にある人たちに、「笑い」で元気・勇気・気力を取り戻してもらうべく活動を続けている。昨年(2010年)12月には、まだ危険地帯のイラクを訪問し話題となった。傷の手当は医師に任すが、心のケアは笑いが担う。そんな心意気を持って世界を飛び回る代表の笑福亭鶴笑師匠に話を伺った。
世界に届くパペット落語誕生秘話
―鶴笑師匠は24歳のとき笑福亭松鶴師匠に弟子入りされて。でもその2年半後には松鶴師匠が亡くなられたのですよね。
鶴笑/はい。しかしその2年半は僕の人生で一番濃くて大事な時間だったと今も思っています。師匠は僕にとってはもう神様みたいな存在で、毎朝拝んでいます。落語を辞めないで続けてこられたのは、この修業のお陰です。その後にどんなことがあっても、あの苦労を無駄にしたくないと思って落語を続けることができています。
―しかし、そんな師匠が亡くなって、ご苦労されたでしょ?
鶴笑/はい。仕事がなくてお金が底をついたときは、公園で草を食べていたときもありましたねぇ。ハコベラは食えるなぁとか(笑)。
―ええっ!そこまでの困窮状態ですか。他のアルバイトをしようとは思わなかったのですか?
鶴笑/芸で食おうと決めていましたから。でも、草食っている貧乏芸人がいると話題になって。それをテレビで見た人がアパートの前にパンを置いてくれたり(笑)。それで仕事がくるようになりましたが、当時は漫才ブームで、落語が衰退していて、演芸場でもダウンタウンとはが出るとキャーって盛り上がるんですが、落語ではシーンですよ。まず落語が始まると、お客さんは席を立って休憩に行ってしまうんですから。それで、「しゃべっても笑わないのなら、もうしゃべらない。人形にしゃべらせてやれ」って人形を持って落語をしたら、キャーって若い人にも大うけして。そこから膝に人形を付けて演じるパペット落語が始まったんです。
―人形を使った落語。周りからは邪道と言われませんでしたか?
鶴笑/今では認めてもらっていますが、当時は「そんな飛び道具を使う落語は落語じゃない!」と言われましたね。でも、お客さんは笑う。どっちを選ぶかですようね。僕はお客さんを選んだ。
―そのパペット落語が、世界で公演活動をするきっかけになったんですから人生っておもしろいですよね。
鶴笑/この落語はお年寄りから幼稚園児まで誰でもがわかる落語です。使う言葉が簡単ですから、これは海外でもいけるんじゃないかと思って。これまでに30か国以上で公演をしてきましたが、どの国にでもその国の言葉でするんですよ。
―ええっ!そうなんですか。でも相当な準備がいりますよね?
鶴笑/いえ、逆に日本で準備をしたらだめですね。本に書いてある言葉じゃだめなんですよ。僕は訪問地の訛りで語りますから、言葉は現地で勉強します。その土地の言葉を使うと「なんでその言葉を知っているの~」ってことだけで仲良くなって、ワーってうけますよ。
―すごい!現地の人にとってそんな楽しいことはないですよね。
笑いに「国境なし」笑いで心のケアを目指す
―2000年から8年間、海外で暮らされていますよね。ご家族も一緒に行かれたのですか?
鶴笑/シンガポールとロンドンに4年ずついました。「明日から行くで!」と奥さんと息子に言って、それぞれがスーツケース持って出かけるんです(笑)。あてがなくても行って開拓する。芸人はどこでも食えるもんですから。家族がいるとストリートでも稼がないといけないって、がんばれます。
―ロンドンには文化庁の文化交流使として行かれたとか。
鶴笑/文化交流使といっても何の保証もないんです。1年間の滞在費はくれましたが。そもそもロンドンなんて「日本の文化交流使がどないなもんじゃ、お前のほうが勉強して帰れ」という感じです(笑)。それでストリートで稼いだり、なんとか自分で這い上がって4年がんばりました。それでわかったことは、結局、人間は同じだということです。イギリス人の芸人にしても、はじめは「すごいやすかな」と思ったけど、「なーんだこんなことで悩むんだ」ってわかったんです。お客さんも同じです。「それで笑うんかー」って(笑)。8年外国に住んでわかりました。世界はみんな同じやなと。
―まさに「国境なき」という団体名が、心底ストンと落ちた感じですね。
鶴笑/その通りです。ロンドンから帰って「国境なき芸能団」の活動を本格化しようと、協力をお願いしてここに(大阪市淀川区)に事務所を構えました。
―師匠は「国境なき芸能団」を立ち上げる前から、ボランティアでホスピスなどに慰問されていると聞きましたが、もともとボランティアに関心があったのですか?
 鶴笑/ボランティアに目覚めたのは阪神・淡路大震災のときです。しばらくは避難所のお手伝いや、子どもと遊んだりしていましたが、少ししたら、「悲しんでばかりもいられない。笑いたい、鶴笑さん落語やってくれないか」って言われて。落語を始めると、みんな集まって来て一緒になって笑うんです。避難所もいろんな人間関係がありますよね。でもそういったものを超えて楽しんでもらえたのです。「元気出てきたわ」っておばあちゃんにも言われましたね。それまでは、僕自身もお笑いなんてどこか「不謹慎なもの」というイメージがありましたけど、笑いは人を元気にする、人の役に立つんだということを強く感じました。笑いには力があることがわかった。
鶴笑/ボランティアに目覚めたのは阪神・淡路大震災のときです。しばらくは避難所のお手伝いや、子どもと遊んだりしていましたが、少ししたら、「悲しんでばかりもいられない。笑いたい、鶴笑さん落語やってくれないか」って言われて。落語を始めると、みんな集まって来て一緒になって笑うんです。避難所もいろんな人間関係がありますよね。でもそういったものを超えて楽しんでもらえたのです。「元気出てきたわ」っておばあちゃんにも言われましたね。それまでは、僕自身もお笑いなんてどこか「不謹慎なもの」というイメージがありましたけど、笑いは人を元気にする、人の役に立つんだということを強く感じました。笑いには力があることがわかった。
―そんな経験がその後の活動につながったのですね。具体的に「国境なき芸能団」を作ろうと思ったきっかけは何だったのでしょう?
鶴笑/トルコ大地震の被災地を訪れたとき、「国境なき医師団」の方に出会ったことです。その方に「我々は薬で病気や傷を治すけど、心の病はそれでは治らない。心のケアができるのは笑いではないですか?あなたにできることではないですか?」って言われたんです。医者は体の傷を治し、芸人は心をケアする。この2つが一体となったらいいんじゃないか!と思ったわけです。
イラク訪問・広がる支援の輪
―「国境なき芸能団」として、これまでにドミニカ、ブラジル、カンボジアに笑いを届けてこられましたが、昨年(2010年)12月にはイラクを訪問されましたね。
鶴笑/クルド地区の難民キャンプに行きました。そこにはバグダットを追われたスンニ派の人たちが暮らしています。スンニ派はフセイン寄りだったからNGOも救援に入ってこなかったんですね。そもそもイラクは危険だし、イラクを助けるのはアメリカに対してもややこしいから国際的な援助の手も回っていなかったそうです。現地に人は、「世界から忘れられるのが一番怖い」と言っていましたね。
―しかし危険地域です。よく行かれましたね。
 鶴笑/実は最初は断ったのです。何かあって国に迷惑をかけることにならないかなと。でも今回の話を持ってきてくれたジャーナリストの西谷文和さんから「クルド人地区は落ち着いていて、まさに町を復興しようとしている場所。今こそ笑いが必要なんだ」と言われて。西谷さんからビデオを見せてもらったのですが、子どもたちが泣いているものばかりですよ。「この子の笑顔が見たい。笑いを取り戻すぞ!」という思いが湧いてきて、それが背中を押しました。
鶴笑/実は最初は断ったのです。何かあって国に迷惑をかけることにならないかなと。でも今回の話を持ってきてくれたジャーナリストの西谷文和さんから「クルド人地区は落ち着いていて、まさに町を復興しようとしている場所。今こそ笑いが必要なんだ」と言われて。西谷さんからビデオを見せてもらったのですが、子どもたちが泣いているものばかりですよ。「この子の笑顔が見たい。笑いを取り戻すぞ!」という思いが湧いてきて、それが背中を押しました。
―まさに落語家魂ですね。
鶴笑/職業病ですよ(笑)。でも行ってよかったです。子どもたちは、もう今しかないっていうくらい笑いました。「私も生きてるぞ!」っていうそんな力がみなぎっていましたよ。中には片目をなくした子もいましたが、その子も目をなくしてからはじめて笑ったと言っていました。しかし病院を訪問したとき、大きなショックを受けて笑えなくなっていた子がいました。その子はどうしても笑ってくれませんでした。一体この子に何があったんだろう。辛かったんだろうな。でも、もう一度笑わせたいですよ。人間らしさを取り戻してあげたい。
―子どもは、理屈では理解できないからこそ、心深く、体全体で受けとめてしまったのですね。今回の訪問の反響は日本でも大きかったそうですね。
鶴笑/そうなんです。先日、和歌山の中学と高校から電話があって「鶴笑さんを、ぜひもう一度イラクに連れていきたい。学校でボランティアや募金活動をしたいので、イラクの現状やボランティアの大切さを話してほしい」と。それってこういう活動の原点ですよね。2月の中旬にその学校で講演会をすることになりました。
―子どもたちに、ぜひ現地の子どもたちのお話をしてください。こうした経験を通して、鶴笑師匠自身も変わってこられたのではないでしょうか?
鶴笑/僕も昔は、世界の大きな舞台で活躍して有名になりたいと思っていました。でも今は、もっと現場主義といいますか、小さな町や病院で直接笑いを届けたいと思っています。災害でも戦争でも、はじめはマスコミに取り上げられるけれど、少し経つと誰も見向きもしなくなってしまうでしょ。でも、そんなところにこそ笑いを求めている人がいるんですよね。そんな世界のどこかで笑いを求める人のところに、笑いを届けに行きたいと思います。
―まさに、落語家 笑福亭鶴笑の天命ですね。素敵なお話をありがとうございました。
聞き手
公益社団法人日本フィランソロピー協会
理事長 高橋陽子
公益社団法人日本フィランソロピー協会
理事長 高橋陽子