◆巻頭インタビューNo.352/2012年10-11月号
日本の働き方そのものを変えていく必要があるのです
佐藤 博樹 (さとう・ひろき) 氏
東京大学社会科学研究所教授
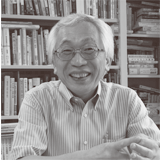 <プロフィール>
<プロフィール>1953年生まれ。一橋大学大学院社会学研究科を経て、雇用職業総合研究所(現・労働政策研究・研修機構) 研究員になる。1983年、法政大学大原社会問題研究所助教授。1991年、法政大学経営学部教授。1996年より東京大学社会科学研究所教授。
女性の能力開発、両立支援からスタートしたワーク・ライフ・バランスという考え方は、今日、男性はもとより幅広い年齢層を含めた社員の間でも欠かせないものになっている。
勉強や趣味、自己啓発、育児、介護などの理由で、勤務時間にある程度の制約を持つ社員の「ワーク」と「ライフ」のバランスを取ることは、職場での意欲と仕事の成果に直結する。近年ではワーク・ライフ・マネジメントが重要視され、私たちの働き方はダイナミックに変わっていこうとしている。個人と企業をより有機的に結びつける新しい働き方について、東京大学社会科学研究所教授の佐藤博樹氏にお話を伺った。
勉強や趣味、自己啓発、育児、介護などの理由で、勤務時間にある程度の制約を持つ社員の「ワーク」と「ライフ」のバランスを取ることは、職場での意欲と仕事の成果に直結する。近年ではワーク・ライフ・マネジメントが重要視され、私たちの働き方はダイナミックに変わっていこうとしている。個人と企業をより有機的に結びつける新しい働き方について、東京大学社会科学研究所教授の佐藤博樹氏にお話を伺った。
多様な生き方を受け入れるのが
ワーク・ライフ・マネジメント
ワーク・ライフ・マネジメント
―ワーク・ライフ・バランスという考え方は、だいぶ社会に定着していますが、一方で、単に女性の子育て支援のような形に矮小化されている面もあります。男女を問わず、働き方全体の変化を踏まえ、企業からの視点も含めて、もっと本質的に考えないといけないと思うのですが。そういう意味でもワーク・ライフ・マネジメントという言葉に興味があります。
佐藤/まず社員にとって、「意欲的に仕事ができ、かつ仕事以外でやりたいこと、やらなければいけないことに取り組めている」という状態が「ワーク・ライフ・バランスが取れている」と言えます。企業から見ると、一人ひとりの社員が置かれた状態ですね。ただ「バランス」という言葉がなんとなくワークとライフが半々というイメージになってしまうのがいけなくて、人によって釣り合いの取り方はさまざまなんです。極端にいうと、新卒で企業に入って、新しいことを覚えるのが楽しくて、1日仕事をしているだけで幸せだと
いう人もいるでしょう。ワーク・ワークの時期があるのは決して悪いことではない。ただ、そういう仕事の仕方しか受け入れられない会社や職場は困ると言うことです。
―多様な生き方を柔軟に受け入れるということですね。
佐藤/そうです。ワーク・ライフ・バランスの状態は一人ひとり違うし、ライフステージによっても変わります。それを誰がマネージするのかというと、まず1つは自分自身。自分のライフステージに合わせて、ワーク・ライフ・バランスを考えてマネジメントする。そして2つめが会社や管理職です。管理職には部下がワーク・ライフ・バランスを実現できるように支援するマネジメントが求められる。これをワーク・ライフ・バランス支援というマネジメントと呼んでいいのではないかと思います。
仕事への意欲を引き出す鍵は時代とともに変わる
―ワーク・ライフ・マネジメントは企業にとって、どのような利点があるのでしょうか?
佐藤/社員に意欲的に仕事に取り組んでもらうことと関係してきます。企業の人材活用の基本は3つあって、1つは経営戦略や目標が職場の社員にブレイクダウンされて、社員一人ひとりが自分のやるべきことを理解することです。正しく理解しないで一生懸命に働いても、変な方向にいってしまいますから。また、やるべきことがわかっても能力がなければできないので、2つめは能力開発です。会社や上司は能力開発の機会を提供し、社員本人も能力開発に努力をする。3つめが、保有している能力を発揮する仕事への取り組み
です。能力があれば期待するだけの仕事ができるわけではないのです。
―宝の持ち腐れになってしまう。
佐藤/ええ。つまり、どんな会社でも、これら3つの要素が人材活用の基本だといえば、経営者の誰もが納得します。そして、これら3つは全部が大切だけれど、近年では3番目の要素が特に重要になってきています。なぜかというと、仕事の性格が変わってきたからです。仕事のやり方をいちいち細かく指示したり、マニュアル通りにやればよいという仕事はだんだん減ってきています。特にコア社員に期待されているのは「なにをやるべきか」までは伝えられるけれど、やり方は自分で考えてね、という部分でしょう。そうしないと良い成果が出ないような仕事が増えてきたんです。それだけでなく「何をすべきか」を考えることも期待されています。
―「やり方を考える」というのは、非常に創造性が求められる分野ですから、確かに仕事への意欲があるか、ないかが重要なのは間違いありませんね。
佐藤/自分の持っている能力を100%発揮しようと思うような意欲により、仕事の出来ばえ、成果、創造性を左右するような仕事が増えています。それを踏まえたときに、どうしたら社員が意欲的に取り組めるか。仕事以外にやりたいこと、やらなければならないことがないワーク・ワーク社員なら、仕事が充実していればいいんですね。長年、それでやってきた部課長から見ると「やりたい仕事を任されて、頑張れば評価される」と思っています。しかし部下からすれば働きにくい。なぜかというと、確かに仕事は面白いし、ちゃんと評価してくれる。一方で、自分はもっと勉強がしたいとか、家族と過ごす時間がもっと欲しいなどのニーズがある。
―彼らにとって「ワーク」と「ライフ」は両立させたい大切な要素なんですね。
 佐藤/ワークとライフのバランスが取れていない状態を「ワーク・ライフ・コンフリクト」と言います。この状態に陥ると、社員は仕事に意欲的に取り組めなくなり、会社側としては人材活用の失敗ということになります。今、なぜワーク・ライフ・バランス支援を考えないといけないかというと、社員が変わったからなんです。ワーク・ワーク社員もいるけれど、一方でワーク・ライフ社員が増えてきた。そういう社員にも意欲的に働いてもらうためにワーク・ライフ・マネジメントが不可欠になったのです。それは法律でやらないといけないことではなくて、うちは経営が苦しいからやらないという話でもなく、人材活用の基本なんですね。つまり企業経営のためにやらないといけない取り組みなのです。
佐藤/ワークとライフのバランスが取れていない状態を「ワーク・ライフ・コンフリクト」と言います。この状態に陥ると、社員は仕事に意欲的に取り組めなくなり、会社側としては人材活用の失敗ということになります。今、なぜワーク・ライフ・バランス支援を考えないといけないかというと、社員が変わったからなんです。ワーク・ワーク社員もいるけれど、一方でワーク・ライフ社員が増えてきた。そういう社員にも意欲的に働いてもらうためにワーク・ライフ・マネジメントが不可欠になったのです。それは法律でやらないといけないことではなくて、うちは経営が苦しいからやらないという話でもなく、人材活用の基本なんですね。つまり企業経営のためにやらないといけない取り組みなのです。
―守りではなく、攻めの発想ですね。
佐藤/そう。ワーク・ライフ・バランス支援が企業の人材活用では当たり前のことになったんです。昔の日本を見ると、たとえば男女雇用均等法ができる少し前、女性に意識調査をすると「仕事は結婚出産まで」と答える人が全体の6、7割いました。そういう時代に「うちの会社に来れば男女別なく働けて、管理職になれます」ということは女性に魅力的でないことにもなります。つまり、社員が意欲的に働ける条件は時代とともに変わってきているんです。
育児休暇は長すぎない方がいい
―ワーク・ライフ・バランスが取れていれば意欲的かというと、案外、今の若い人たちが二極化していませんか? 自分で考えて意欲的に働ける人と、「やり方を教わっていません」と言って、なかなか動けない人がいるような気がします。
佐藤/自分で納得できる仕事につきたいという気持ちはすごく大事で、しかし、その仕事が自分に向いているのか、いないのかはやってみないとわからない。すると何が大事かというと、入社3年目くらいまでの初期キャリアです。この会社に勤めて、この仕事が自分に向いていると思えるような仕事をマネジメントできるかどうか。これは初任配属先の管理職の問題なんです。仕事の与え方ひとつを見ても、人を潰すのは簡単ですよ。でも仕事に自信を持たせるのは結構難しくて、たとえば育成のためにはある程度頑張ればできるくらいの仕事を与えないといけない。やはり管理職自身、部下を育てることを考える余裕がなくなってきたという問題がすごく大きい。
―すぐ即戦力と短期的成果を求めますね。
佐藤/これは女性の働き方にも関わってくる問題です。女性が結婚し、子どもが生まれても働き続けられるように両立支援制度があるわけですが、いくら制度が整っていても、実際に仕事と子育ての両立は大変ですよね。それでも仕事を続けようと思うには、自分の仕事にそれだけの価値を見いだしているかどうかが重要です。つまり、ここでも初期キャリアなんです。結婚する以前に、この仕事が面白いから続けようと思えるかどうかで決まってくる。
―制度の整っている大企業に勤めている女性で産休、育休、時短をめいっぱい取って辞めるという人もいますね。
佐藤/仕事が面白い、続けたいと思えば、普通は、育児休業を取得しても早く職場に戻りたいと思いますね。また、そう思わせる仕事のさせ方や職場でないとだめですよ。逆に育児休業が子が3歳まで取れるというような会社は、その人は現場にいてもいなくてもいい、と言っているようなものでもあります。
―早く戻りたいと思う意欲は大切です。でも戻れないという女性をつくらないことも大事なワーク・ライフ・マネジメントですね。
 佐藤/僕が一番いいと思うのは、子どもが1歳までは育児休業を取り、短時間勤務の期間は短く、なるべく早くフルタイムに戻り仕事と子育ての両立が可能な職場です。過度な残業がなく、残業する場合も事前に計画を立てて、必要に応じて残業をする時もある。そんな働き方のイメージです。これを実現させるには3つの要素が必要で、1つめは女性が意欲を持ち続けられるような仕事であるかどうかです。2つめは制度ではなく、働き方そのものです。育児休業があっても、実際の子育ては長く続くので、仕事との両立ができるかどうか。3つめは夫のあり方です。ところが現実はこの3つが欠けているから、職場に戻らない女性がいて、また戻っても子育てとの両
立が大変で「2人目の子どもは無理ね」となってしまう。
佐藤/僕が一番いいと思うのは、子どもが1歳までは育児休業を取り、短時間勤務の期間は短く、なるべく早くフルタイムに戻り仕事と子育ての両立が可能な職場です。過度な残業がなく、残業する場合も事前に計画を立てて、必要に応じて残業をする時もある。そんな働き方のイメージです。これを実現させるには3つの要素が必要で、1つめは女性が意欲を持ち続けられるような仕事であるかどうかです。2つめは制度ではなく、働き方そのものです。育児休業があっても、実際の子育ては長く続くので、仕事との両立ができるかどうか。3つめは夫のあり方です。ところが現実はこの3つが欠けているから、職場に戻らない女性がいて、また戻っても子育てとの両
立が大変で「2人目の子どもは無理ね」となってしまう。
仕事と介護の両立が日本の働き方を変える
―まだまだ基本的な働き方で、歯車がずれているように思えます。
佐藤/育休や時短などの制度は建物の2階に過ぎなくて、大事なのは1階部分の働き方です。これまでの日本の職場はワーク・ワーク社員を前提にして、仕事があれば終わるまでやる。管理職は部下に、5時半頃、突然「残業して、この仕事をやって」と言ってもやってもらえた。しかしワーク・ライフ社員は「今日は学校へ勉強に行く日」であったり「子どものお迎えがある日」かもしれないから突然の残業は無理ですね。「昨日、言っておいていただければ、調整できました」という話です。ワーク・ライフ社員でも決して残業ゼロではなく、本当にやらないといけないことはやる、ということです。
―高度成長期の働き方のイメージを持っている社員がまだ現場にいますから、なかなか意識が切り替わらないのですね。
佐藤/現在は未婚化も進んでいるので、まだまだ時間制約のある働き方をする人たちは少数派です。育児中で残業のしにくい人に「みんなでカバーするから、早く帰りなよ」と優しく声をかけ、周囲は「いつでも残業ができる」という働き方を変えません。その結果、時間制約のある人はいつまでも責任ある仕事を任せてもらえず、仕事への意欲をなくしてしまう。しかし今後、時間制約のある人が増えてきたら、みんなでカバーすることもできなくなりますね。
―解決策はありますか?
佐藤/ひとつチャンスがあるとしたら介護の問題です。統計的に見ると、50歳から65歳の15年間は介護と仕事の両立の時期なんです。子育ては奥さんが主に担ってくれた人でも、介護はやってくれませんから、夫が自分の親を看なければいけない。
―今の50歳以上だと、ほぼワーク・ワーク社員ですね。
佐藤/いままでワーク・ライフ・バランスというと、「ま、仕方がない。そういう部下が増えてきたから考えよう」という感じだった。それが介護の課題に直面して、初めて自分のこととして考えざるを得なくなる。まさにチャンスですね。実際、僕が介護の問題でセミナーやると男性がたくさん来る。「介護と仕事の両立考えると、働き方を変えないといけない」と伝えると、すごく関心があります。男性がライフの方にエネルギーと時間を割き、一方で仕事もちゃんとやる。そうした方が実は仕事の質が高くなると考えた方がいいですし、社会全体としてワークとライフのバランスをとる働き方を推進しなければいけないですね。
―課題と可能性多し、ですね。本日はありがとうございました。
インタビュー
公益社団法人日本フィランソロピー協会
理事長 高橋陽子
公益社団法人日本フィランソロピー協会
理事長 高橋陽子