◆特別インタビューNo.365/2014年12月-2015年1月号
「不就学」を防ぎ、すべての子どもに豊かな人生を送ってほしい
小林 克嘉(こばやし・かつよし)氏
文部科学省 大臣官房国際課 国際協力企画室 室長補佐
 <プロフィール>
<プロフィール>1976 年生まれ。東京大学文学部スラヴ語スラヴ文学専修課程卒 業。2001 年文部科学省に入省。文部科学省では、専門学校、青少 年教育、toto(サッカーくじ)、世界遺産等の業務に携わったほか、 内閣府、農林水産省や千葉市教育委員会にも出向。2012 年より内 閣府定住外国人施策推進室において、日系ブラジル人等への施策の 取りまとめを担当し、2014 年4 月より現職。
現在、日本にはおよそ200万人
の在留外国人が暮らしている。中長
期で日本に滞在する人々のなかには
家族連れで来日し、学齢期の子ども
を養育している場合もある。国籍に
関係なく、子どもは教育を受ける権
利があるが、実際には日本語が障壁
となり、中学・高校に通えない子ど
もも少なくない。教育現場でも、彼
らにどのような学びの場を与えるの
か試行錯誤が続いている。
外国にルーツのある子どもたち
の教育支援の現状、そして国が行っ
ている施策について、文部科学省大
臣官房国際課の小林克嘉さんに聞い
た。
「不就学」が外国籍の
子どもに広がっている
― 在留外国人の子どもたちへの教育
問題は、以前から注目されていたの
でしょうか?
小林/1990年前後までは、外国
人といえば韓国・朝鮮人の方々でし
た。歴史的な背景もあり、教育に際
して大きな問題となる言葉の問題
は、ニューカマーといわれるブラジ
ル人等とは比べると低かったかもし
れません。
― 1990年に入管法(出入国管
理及び難民認定法)が改正され、外
国籍の日系二世、三世にも在留資格
が与えられました。それからは日系
ブラジル人などの入国が一気に増え
ましたが、彼らが本国から家族を呼
び寄せて、そこから外国にルーツの
ある子どもたちの教育問題が出てき
たということでしょうか。
小林/当初、2000年前後から増
加してきたといわれるブラジル人学
校で教育が行われていたのです。
ところが2008年のリーマン・ ショック後の不況で親の仕事がなく なり、授業料が払えず、学校に通え ない子どもが出てきました。そし て、このような子どもたちが「不就 学」という状態になることも多く、 社会的な問題になったのです。
ところが2008年のリーマン・ ショック後の不況で親の仕事がなく なり、授業料が払えず、学校に通え ない子どもが出てきました。そし て、このような子どもたちが「不就 学」という状態になることも多く、 社会的な問題になったのです。
― 学齢期に達していない子どもたち
は「未就学」という言葉を使います
が、それとは違うのですね。
小林/「不就学」とは、学齢期で
あっても就学をしていない状態の
ことです。日本人は義務教育が課
されているので、仮に不登校であっ
ても学校に籍はあるのです。
しかし外国人には必ずしも、その ような義務がありません。そのた め、就学の機会を逸することのない よう、お住まいの自治体の教育委員 会から、小学校入学の段階でお知ら せはしていますが、外国籍の子ども の教育には、さまざまな考え方があ ります。
たとえば、将来帰国する予定があ るので、両親が子どもを本国の学 校に行かせたいという方がいれば、 それは尊重すべきことでもあるの です。
しかし外国人には必ずしも、その ような義務がありません。そのた め、就学の機会を逸することのない よう、お住まいの自治体の教育委員 会から、小学校入学の段階でお知ら せはしていますが、外国籍の子ども の教育には、さまざまな考え方があ ります。
たとえば、将来帰国する予定があ るので、両親が子どもを本国の学 校に行かせたいという方がいれば、 それは尊重すべきことでもあるの です。
― 親の失業がきっかけで学費が不
要な日本の小・中学校に入ろうとし
ても、言葉の問題がありそうです
ね。
小林/学校に行っても、日本語ができなければ、当然、勉強についてい
けません。そうしたことも原因で、
「不就学」状態になり、その結果、
中学生くらいの年齢の子どもが昼
間からぶらぶらしていたり、まして
や働いていたりということになる
と非常に大きな問題です。
日本は国連の人権規約を批准し ているので、すべての子どもが教育 の機会を与えられるように、権利を 保障しなければなりません。そこで 文部科学省では2009年度から 「虹の架け橋教室」という事業を始 めています。外国人が多く住む北関 東や東海地方を中心に教室を運営 し、日本語教育や学習習慣を指導 し、公立校やブラジル人学校への就 学を促しています。
日本は国連の人権規約を批准し ているので、すべての子どもが教育 の機会を与えられるように、権利を 保障しなければなりません。そこで 文部科学省では2009年度から 「虹の架け橋教室」という事業を始 めています。外国人が多く住む北関 東や東海地方を中心に教室を運営 し、日本語教育や学習習慣を指導 し、公立校やブラジル人学校への就 学を促しています。
― 教室の運営はどこが行っている
のでしょうか?
小林/現在はNPO法人やブラジ
ル人学校など、全国20団体程度が活
動しています(下表参照)。
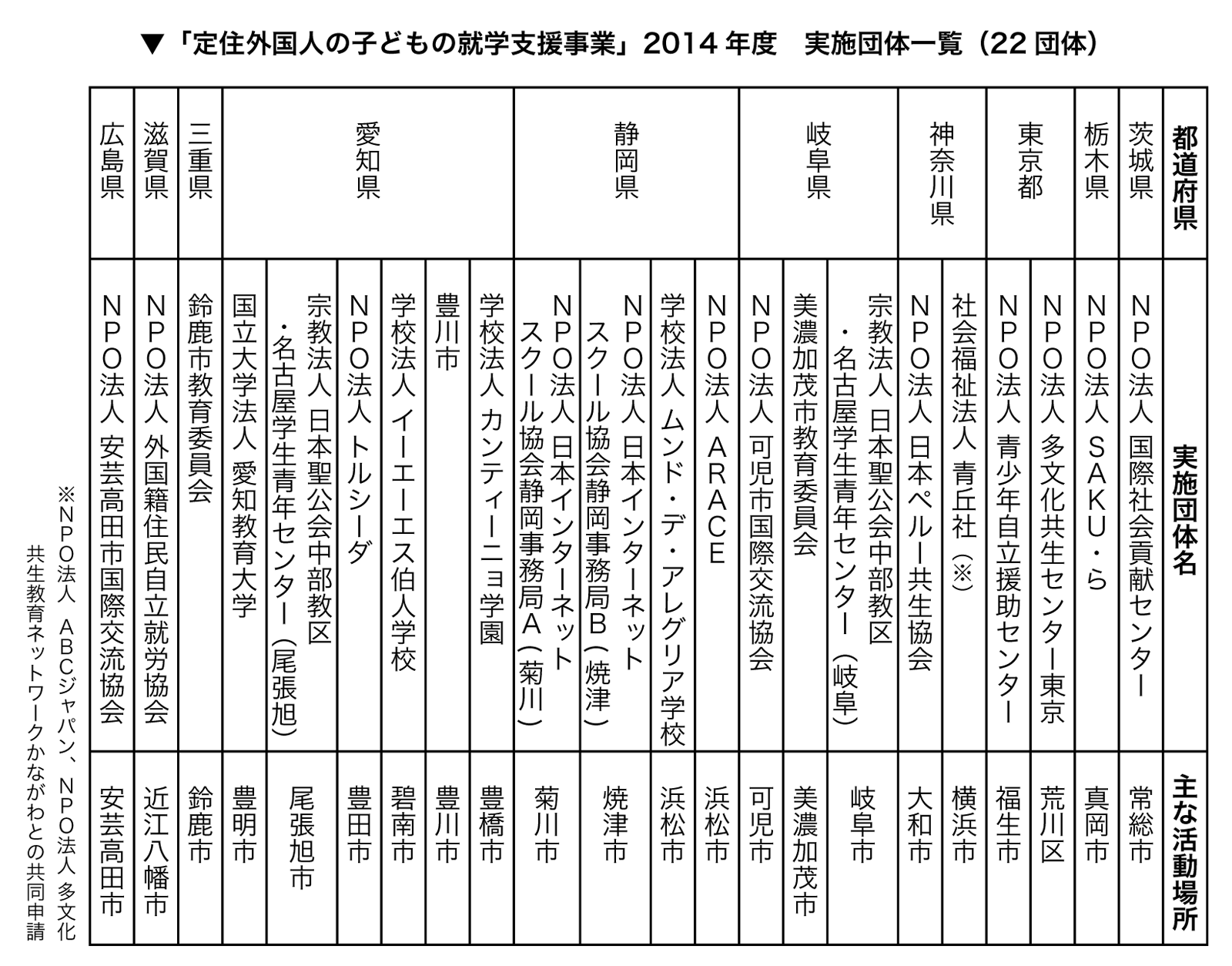
たとえば浜松市では日系ペルー 人やブラジル人のための学校「ムン ド・デ・アレグリア」が有名ですね。同校は各種学校としての認可を取 り、自治体の建物を校舎として利用 しています。本国政府からの認証 もあり、学校のウェブサイトには、 日本と南米社会の架け橋となり、将 来は母国の大統領になり得る人材 を輩出することを目標としておら れます。また、虹の架け橋事業でも 協力いただいています。
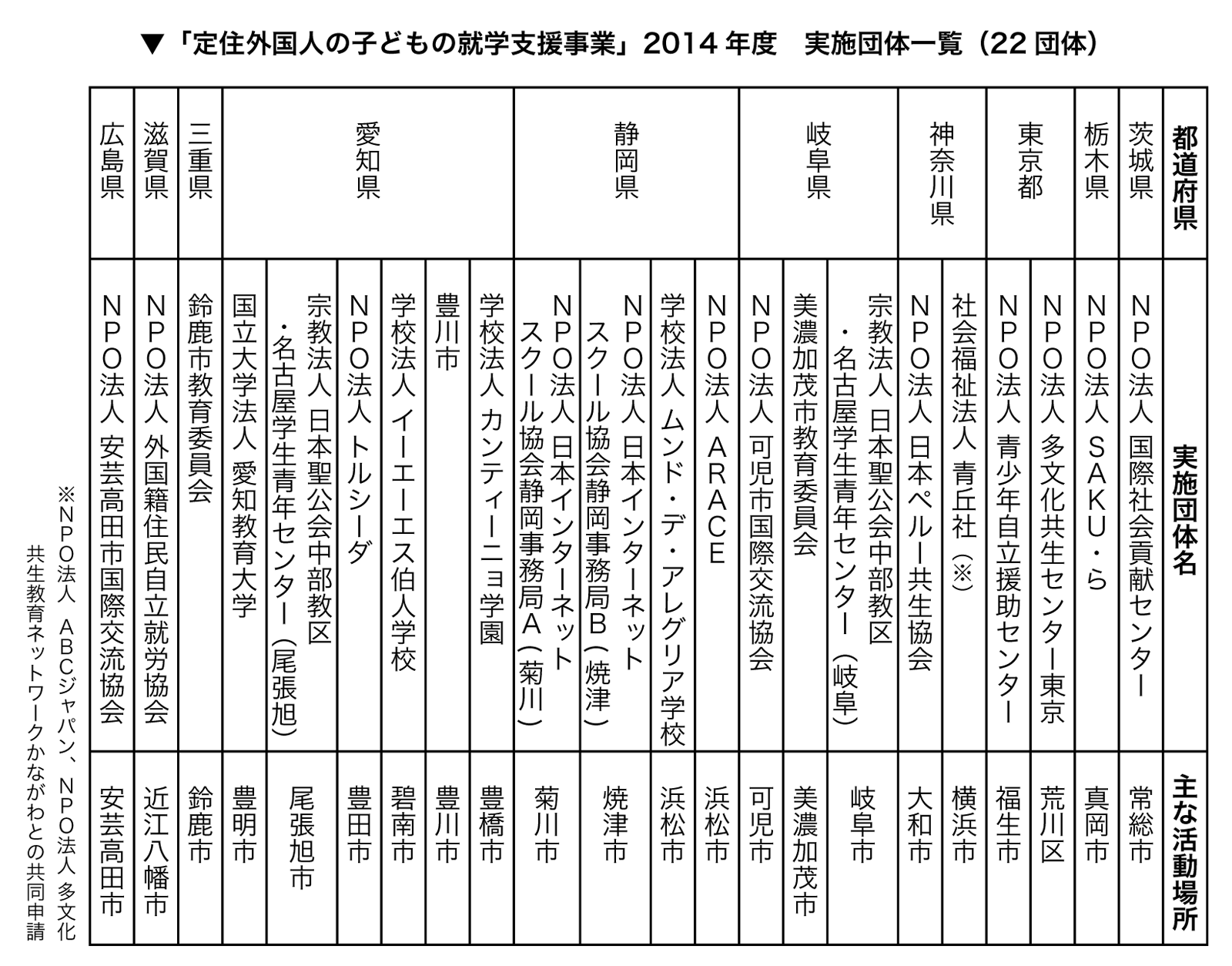
たとえば浜松市では日系ペルー 人やブラジル人のための学校「ムン ド・デ・アレグリア」が有名ですね。同校は各種学校としての認可を取 り、自治体の建物を校舎として利用 しています。本国政府からの認証 もあり、学校のウェブサイトには、 日本と南米社会の架け橋となり、将 来は母国の大統領になり得る人材 を輩出することを目標としておら れます。また、虹の架け橋事業でも 協力いただいています。
― 「不就学」の問題は日系人が中心
でしょうか?
小林/当初は日系ブラジル人、ペ
ルー人のお子さんの就学支援に中
心でしたが、最近では中国人やフィ
リピン人の子どもたちも増加して
います。フィリピン人は母子家庭の
方が多いといわれており、ブラジ
ル人やペルー人のように一部の地
域に集住せず、日本各地に散らばっ
て住んでいて、行政の目が届きにく
い一方、貧困問題への対策も必要な
状態です。
ダブルリミテッドが
知的発達を阻害する
― 日本の公立学校に進学できれば、
子どもたちの教育問題は解決でき
ますか?
小林/いえ、やはり言葉の問題は大
きく、たとえば公立中学を卒業した
日系ブラジル人のお子さんの場合、
高校進学者の割合は約4分の3と
いう調査もあり、日本人とは明らか
に異なります。その7割のなかには
通信制、定時制も含まれていて、子
どもたちが望んで進学するという
より、学力的な問題で進路が決まっ
ているのかもしれません。
その結果、大学などの高等教育の 道も閉ざされてしまいます。近年、 医大に進学したり、弁護士になった りという子どもたちの例も聞きま すが、まだまだ少数派です。
その結果、大学などの高等教育の 道も閉ざされてしまいます。近年、 医大に進学したり、弁護士になった りという子どもたちの例も聞きま すが、まだまだ少数派です。
― 子どものうちから日本に住めば
言葉はなんとかなると思いがちで
すが、現実には簡単にいかないもの
なのですね。
小林/言葉の問題はいろいろな段
階があって、日常会話はすぐにでき
るようになっても、学習言語ができ
ているかどうかは別なのです。中学
生なら、中学の勉強ができる言葉
の能力がないといけない。しかし、
ある程度の年齢になってから日本
に来ると、このレベルに到達するこ
とが大変です。
― 近年、母国語も日本語の習得も中
途半端で、年齢に応じた発達段階に
到達できない「ダブルリミテッド」
の問題も指摘されています。
小林/ダブルリミテッドは当初、帰
国子女の問題だとされていたので
すが、いわば、その外国人バージョ
ンで、事態はより深刻です。
言葉は「考える」という行為に 繋がります。言葉ができなければ、 考えることもできなくなり、国語の 授業がわからないだけでなく、算数 も理科もできない。結局、すべての 勉強に影響するのです。現場の教員 からは知的障がいではないかと見 られてしまう子どももあると聞き ます。
言葉は「考える」という行為に 繋がります。言葉ができなければ、 考えることもできなくなり、国語の 授業がわからないだけでなく、算数 も理科もできない。結局、すべての 勉強に影響するのです。現場の教員 からは知的障がいではないかと見 られてしまう子どももあると聞き ます。
― 公立校では外国人の子どもたち
のために、なにか特別な教育を行っ
ているのでしょうか?
小林/突然、日本の学校制度のなか
に入るのは難しいので、最初の1、
2カ月は準備教室で指導したり、
外国にルーツのある子どもが多い
クラスをつくり、指導力のある先
生が担当するなどの方法を取って
います。また、「加配教員」といっ
て、教員を通常より多く赴任させて
教育のサポートを行う方法もあり、
現場からは評価の声もいただいて
います。
外国籍の人のために
企業ができること
― 外国にルーツのある子どもたち
が十分な学習経験を経ないまま高
校を卒業してしまうと、進路も限ら
れそうですね。
小林/大人になると、今度は就職の
問題が出てきます。正社員ではな
く、派遣のような仕事、あるいは
日本人がやりたがらない3K職場、単純労働に就きがちで、人生の選択
肢が非常に狭くなるのですね。
そもそも、彼らの親世代は日本語 を使わなくてもよい職場で働いて いた方も多く、ごく簡単な日本語 しか話せない。親ができなければ、 子どもも話せず、言葉の問題が継承 されてしまうのです。
あるいは子どもは学校で語学力 を向上させ、日本語が満足に話せな い親を軽視し、家族の繋がりが途切 れてしまうこともあるようです。
そもそも、彼らの親世代は日本語 を使わなくてもよい職場で働いて いた方も多く、ごく簡単な日本語 しか話せない。親ができなければ、 子どもも話せず、言葉の問題が継承 されてしまうのです。
あるいは子どもは学校で語学力 を向上させ、日本語が満足に話せな い親を軽視し、家族の繋がりが途切 れてしまうこともあるようです。
― 親世代が日本語を学習する機会
はないのでしょうか?
小林/ 「日系人就労準備研修事業」
を厚生労働省が行っていて、求職中
の日系人の方々を対象に、日本語
を無料で指導しています。職業選
択の幅が広がることもあり、コミュ
ニケーションが必要な仕事ができ
るように学習しているのですが、高
レベルの日本語、特に読み書きは大
変です。やはり漢字などの文字が非
常に高いハードルになっているよ
うです。
― 親子関係の問題も踏まえて、生活
全般からメンタル面までサポートが
必要な状況ですね。親世代を雇って
いるのは日本企業ですが、企業側で
サポートできることはあるのでしょ
うか。
小林/外国籍の人を雇っている企業
は、日本語教育の部分で面倒をみて
いただけたらありがたいですね。
トヨタ自動車やスズキといった大
企業は、以前からさまざまな取り組
みをされていますし、外国人を多く
雇用している群馬県の食品工場で
は、日系ブラジル人のチーフがい
て、日本語、生活習慣などを会社の
活動のなかで細かく目配りしていま
した。また、滋賀県には社員寮の中
にブラジル人学校を設立している企
業もあって、こういう良い事例が紹
介されて、各地に広まるといいと思
います。
― 中小企業であっても、そのような
サポートができるのですね。やはり
人をコマとして使うのでなく、企業
側も彼らを大切な人材として扱って
ほしいですね。
増加し続ける
アジアからの子どもたち
― 今後も外国にルーツのある子ども
たちの教育については対策が必要で
しょうか?
小林/日系ブラジル人などの方々
は、リーマン・ショックの不景気で
帰国され、人数はガタッと減りまし
た。現状では新規入国者はほとんど
いませんが、
18
万人程度が日本に定
住し、人口は横ばいか、新たに子ど
もが生まれて少し増加する程度で
す。
ただ中国、フィリピン、ベトナム などアジア各地からは、日系人をは じめ多くの外国人が、引き続き来日 しています。そして 10 歳前後の学齢 の子どもたちの入国も認めているの で、同様にダブルリミテッドのよう な状況は起こりうると考えられま す。
ただ中国、フィリピン、ベトナム などアジア各地からは、日系人をは じめ多くの外国人が、引き続き来日 しています。そして 10 歳前後の学齢 の子どもたちの入国も認めているの で、同様にダブルリミテッドのよう な状況は起こりうると考えられま す。
― 子どもたちが十分な教育を受けら
れず、将来、人生の選択の幅が狭く
なっては本人にとってもつらいです
し、日本にとっても損失ですね。
小林/ 日本としては単純労働を行う
外国人を受け入れないとことが原則
で、日系人の方も当初は、出稼ぎで
来られる方が多かったので、子ども
の教育については、大きな問題とし
て捉えにくかったということがあり
ます。しかし、現実には、一部の子
どもたちが「不就学」に陥っている
現状があり、その子どもたちが、非
行等の反社会的行動に走るなどのこ
とがあれば、地域社会にも悪影響が
出てしまいます。今後は自治体、そ
して国としても対策をしていかなけ
ればいけません。
― 子どもは日々成長しますから、ま
さに待ったなしの状況です。
小林/ やはり大前提として、子ども
は学ぶ権利がありますから、そこを
しっかり確保するという考えをもと
に、今後も対策を考えていくことが
大切だと考えています。
― 日本経済を支える外国人就労者の
子どもたちの問題は、われわれ日本
人にとっても他人事であってはなら
ないですね。日本に暮らすあらゆる
国籍の子どもの学ぶ権利に、もっと
敏感でいたいと思います。
本日はありがとうございました。
本日はありがとうございました。
インタビュー
公益社団法人日本フィランソロピー協会
理事長 高橋陽子

【2014年10月17日 文部科学省にて】
公益社団法人日本フィランソロピー協会
理事長 高橋陽子
【2014年10月17日 文部科学省にて】