◆特別寄稿 No.365/2014年12月-2015年1月号
ダブルリミテッド問題の現状とその支援
柴崎 敏男(しばさき・としお)氏
特定非営利活動法人国際社会貢献センター(ABIC)
 <プロフィール>
<プロフィール>1970 年三井物産株式会社入社、鉄鋼部門、10 年間のドイツ勤務経て96 年より広報部で芸術文化活動、障がい者支援などの社会貢献活動に携わる。 2005 年より在日ブラジル人支援、特に児童生徒支援活動を担当し、2012 年6 月に同社退職後も、特定非営利活動法人国際社会貢献センター(ABIC) にて三井物産の業務委託として在日ブラジル人支援活動を継続するともに特 定非営利活動法人難民支援協会の理事などを務める。特別講師として大学で 企業の社会貢献の講義も行う。
観光立国を標榜している日本。
2013年に日本を訪れた外国人
〈観光客〉は1036万人に達し
た。一方、日本には約209万人の
外国人が住み、約72万人が〈労働
者〉として働いている 。
私たちの生活・経済はこの人たちに依っているところがかなりある。大手企業に直接雇用されているケー
スは多くないが、その工場が使う部
品の、またその一部をつくる工場で
働いている人もいるし、皆さんがコ
ンビニで毎日目にする弁当も彼らが
つくってくれている。
在日外国人に関しては、雇用環
境、生活環境、教育などの問題があ
る。今回は教育に関して、特に子ど
もの言語習得に焦点を当てて、その
実態をお伝えし、早急な対策が必要
であることを知っていただきたいと
思う。
なぜなら、彼らの権利を守り、良
き隣人が増えることは、結果として
我が国にとっても、利益をもたらす
ことになるからである。
移民の子どもたちの学力
OECD(経済協力開発機構)
が41の国と地域を対象に実施した、
2003年のPISA(生徒の学習
到達度調査)の結果に基づく分析に
よると、多くの国では移民の子ども
の学力がネイティブの子どもの学
力と比べて明らかに低いと報告さ
れている。当センターは2005年
から三井物産が取り組む在日ブラ
ジル人児童生徒支援活動を業務委
託として引き受けており、私も毎年
日本各地を回っているが、子どもた
ちの実態が想像以上に大変であり、
早急な改善の必要性を感じている。
なぜ学力が振るわないのだろう
か。
1989年の第44回国連総会に
おいて採択され、日本も94年に批准
した「児童の権利に関する条約(子
どもの権利条約)」は、4つの柱
(生きる権利、守られる権利 、育
つ権利、参加する権利)で成り立っ
ており、当然、子どもたちの「教
育を受ける権利」も含まれている。
しかし、学力の差を見せつけられる
と、外国にルーツのある子どもたち
の権利が守られているとは言い難
い。
人間がものを考え、他人に自分
の気持ちを伝えるには、語彙とその
ルール、つまり言語が必要だ。言
語が習得できているということは、
単に、友だちと話ができる、買い物
ができるというレベル(生活言語)
ではない。学習についていけるだけ
の力(学習言語)が必要なのであ
る。
つまり、当然のことだが、言語
習得が遅れるということは、学力不
足に繫がり、コミュニケーションが
とれないと、つい暴力に訴えるとい
うことにもなり得る。
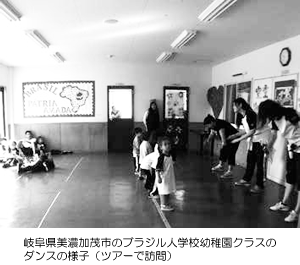 私たちはいったいどのように言
語を習得するのだろうか。言語習得
に関しては多くの説があるが、人は
生まれながらにして言葉を獲得す
る能力を備えているようだ。とはい
え、ある年代、具体的には10歳から15歳位まで十分な刺激を受け、正し
い言葉に接することがないと習得
が難しいといわれている。その時期
は「臨界期」と呼ばれている(「感
受性期」という学者もいる)。
私たちはいったいどのように言
語を習得するのだろうか。言語習得
に関しては多くの説があるが、人は
生まれながらにして言葉を獲得す
る能力を備えているようだ。とはい
え、ある年代、具体的には10歳から15歳位まで十分な刺激を受け、正し
い言葉に接することがないと習得
が難しいといわれている。その時期
は「臨界期」と呼ばれている(「感
受性期」という学者もいる)。
一方、言語習得の能力は生得的
といっても、環境が重要であること
は明白である。日本人の子どもで
も、外国にいて日本語に触れる機会
がなければ、その国の言葉は覚える
ことができても、日本語は習得でき
ない。親が話しかけ、社会的な環境
がその子の持っている言語の能力
を適正に伸ばして、日本語が話せる
ようになっていく。つまり、生育環
境が整わなければ、多くの人が理想
だと思っているバイリンガルどこ
ろか、一つの言語も習得できない。
翻って、日本にいる外国人労働
者をみると、早朝から深夜まで働い
ている保護者には、子どもに丁寧に
話しかける時間も余力もないため、
子どもたちは母語(継承語)ですら
正しく身につける機会がない。家庭
で教科学習に必要な、正確な日本語
を教えることができる外国人の保
護者は、どれだけいるだろうか。
さらにもう一つの問題は、保護
者によっては、自身が十分な教育を
受けていないために、教育の重要性
が理解できていない場合や、理解で
きていても、子どもたちに適正な教
育を施すことができない事例が多
いことである。
つまり、このような家庭で育つ
子どもたちは、重要な時期に適正に
言語を習得する機会を失っている
恐れがあるということだ。さらに、
資格も経験もない人間が子どもを
預かるような託児所に入れられて
いる児童の生育にも、おおいに問題
がある。駅などの荷物預かり所のよ
うに一時期だけ置いておくのとは
わけが違う。世話を必要としている
生身の人間であることが忘れ去ら
れている。
日本の学校に通い始めれば問題
は解決すると思っている保護者は
多いが、子どもたちの実態をみる
と、小学校一年入学時点でみられる
日本の児童との語彙・学力の差は、
成長するにつれ、縮まるどころか
広がる傾向にあり、小学校高学年、
中学校で落ちこぼれになってしま
うケースが多く見られる。
1・5世代問題
「1・5世代問題」とは、親と
一緒に移民(移動)した小学高学
年から中学生くらいの子どもたち
が陥る問題のことである。彼らは、
移動した先の現地語、例えば日本語
を一生懸命に学ぼうとするが、一方
では継承語(ブラジルの場合はポル
トガル語)に触れる機会が少なくな
り、語彙も減少する。
彼らは、表面的には日本語がと
てもよく話せるし、母語も使うこと
ができるので、傍目からはバイリン
ガルのように見える。しかし、日本
語の語彙も表現力・理解力も不十分
なので、当然授業について行けな
い。学力のレベルは、同年代の日本
の子どもたちと比較すると数学年
下レベルといったところだろうか。
頭は悪くないのに周りからは「成績
が悪い、頭が悪い」といわれがち
で、自信を喪失してしまう。一方、
母語での学習を継続している訳で
はないので、母語の学力レベルも落
ちて行く。
このように、両方の言語とも十
分な力が備わっていない状況が「ダ
ブルリミテッド」である。
実は、1990年代に日本に入っ
てきた子どもたちのなかには、この
ダブルリミテッドの状態になった
1・5世代の人たちがいて、その人
たちが、今、子どもを育てている。
その家庭での言語はどうだろう
か。継承語でさえ正しく使えない
し、まして日本語力はほとんどな
く、学校から帰ってきた子どもたち
の宿題をみることもできない。その
ような環境で育った子どもたちの
学習能力は、残念ながら伸びない。
前述のように、1・5世代の問
題は単に本人だけの問題ではない。
その家庭に育った子どもは、さらに教育的には多くの問題を抱えるこ
とになる。このような家族が新しく
ダブルリミテッドの子どもたちを
生み出してしまう連鎖を断ち切る
には、何が必要なのだろうか。
まずは、子どもが、少なくとも
ひとつの言語で思考ができるよう
に、いわゆる臨界期に達するまで
に、遊びや生活を通じて多様な刺激
を適正に与え、さまざまな生活経験
をさせながら、しっかりと言語レベ
ルを上げることが必要だ。
しかし、生活のために働かざる
を得ず時間的に余裕がなく、
自身が教育を受けていない
保護者に向かって、その重
要さを説明し教育するよう
にいっても、それは非現実
的である。家庭、保護者に
は頼れない問題なのであっ
て、この負の連鎖を断ち切
るには、公的な支援または
地域の住民やNPOなどに
よる支援が必要だ。このま
までは、OECDの報告の
通りの〈学力の低い子ども
たち〉が増え、社会問題が増大する
だけで、解決が急務である。
公的な対策を
 現在の政府は移民政策をとらな
いと明確に言っているが、少子高齢
化を迎える日本にとって、外国人の
力を借りなければ、震災後の復興だ
けでなくオリンピックでさえまと
もにできないことは、火を見るより
明らかで、外国人が増える傾向は続
くと思われる。
現在の政府は移民政策をとらな
いと明確に言っているが、少子高齢
化を迎える日本にとって、外国人の
力を借りなければ、震災後の復興だ
けでなくオリンピックでさえまと
もにできないことは、火を見るより
明らかで、外国人が増える傾向は続
くと思われる。
労働力不足を補うための
1990年の入管法(出入国管理及
び難民認定法)の改正で、日系人は
3世まで定住ビザがもらえることに
なった。しかし、受け入れ環境が未
整備のまま進められたために、多く
の子どもが教育的にまたは家庭的
(離婚、シングルマザー等)に犠牲
になっている。労働者として受け入
れる外国の人々も、家族を持った生
きた人間であるということをしっか
り認識して外国人を受け入れるこ
とが、政府が取るべきSR(Social Responsibility:社会的責任)だ
と思う。
そのためには、まず、国としての
移民政策を遅滞なく策定し、それに
基づき自治体への資金的、人的支援
を早急に行う必要がある。それを受
け、現在の種々の支援に加え、特に
重要と思われる就学前の児童の支援
(愛知県などで始めた「プレスクー
ル」)をはじめ、各地で成功例のあ
る学校での放課後支援活動や、外国
人の保護者を雇用している企業で
は、企業内研修による保護者の日本
語研修などを提供することで、子ど
もたちはかなり救われるだろう。
政府・自治体・教育関係者・
NPO・企業等などの協力によって
はじめて、日本に暮らす外国にルー
ツのある子どもたちに、日本と母国
の架け橋になる可能性が開け、日本
にとっても重要な役割を果たしてく
れるようになると期待している。