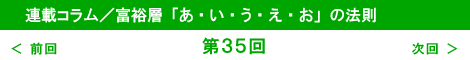
2012年に京都大学の山中伸弥教授がiPS細胞に関する研究でノーベル賞を受賞されました。最近は「リケジョ」という言葉も出てきて、科学に興味関心を持つ女性が注目されていますが、少し前までは「理系離れ」が叫ばれていました。もちろんこのことだけが原因ではないと思いますが、日本の学力が世界と比較して下がってきているというデータもニュースや新聞で取り上げられています。このような状況を受けて、文部科学省では昨年週6日制について検討に入ったらしいですね。
もちろん、学習時間が学力と密接な関係にあることは確かでしょう。しかしながら、最近の日本の状況を見ていると、単純に学習時間を増やすことだけではもの足りないような気がしています。驚くことに日本のほとんどの大学では、学生が書いたレポートや論文の内容とWeb上のテキストを比較検証するシステムが導入されているそうです。一昔前では考えられなかったような状況ですが、逆に言えば、それほどコピーライトが盗用しやすい、されやすい、ということを示しています。スイスのボーディングスクールなどが実践している「考える」時間を増やすほうがどうやらよさそうかなと思ってしまうのは私だけではないはずです。
そのヒントになるかもしれない例を2つ見つけましたのでご紹介を。
ひとつは「crefus(クレファス)」というロボット制作を通じて科学を学ぶ教室です。ここでは、幼稚園年長から小学2年を対象とした「ジュニアエリート」というコースを設けています。キーワードは子どもの自由な「想像力」、そしてそれを具体化するための「創造力」と「科学の知識」。知識を詰め込むことよりも、子どもたちが実際に自分の手で試行錯誤を繰り返しながら「ものをつくる」過程を重視しています。あるレストランで母親が温度が丁度よいと言ったとき、お子さんが「温度が一定に保たれているのは、エアコンに温感センサーがついているからだ」と得意げに話をしたなんてエピソードもあるそうです。
もうひとつはドイツの「サイエンスラボ」。ここでは水晶体に懐中電灯の光を当てると虹ができるというような簡単な実験を行っています。実験自体は理科の授業で行われるようなものですが、重要なのはサイエンスラボが伝えようとしているテーマです。「自然科学は子どもたちにとって冒険です」という言葉は、「crefus」の考え方に通じるところがあるような気がします。
何度も失敗を繰り返しながら自由な発想で自分なりに答えを出してみるという一見非効率的なことがより重要ですよね。「あ・い・う・え・お」レベルの話なんですから周囲の私たちは、否定から入らないことが大切だと思います。私が顧客からお聞きする教育もこんな感じなんですよ。
公益社団法人 日本フィランソロピー協会
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル244区
TEL:03-5252-7580 FAX:03-5252-7585
Copyright (c) L'Association Philanthropique du Japon. Tous droits réservés.
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル244区
TEL:03-5252-7580 FAX:03-5252-7585
Copyright (c) L'Association Philanthropique du Japon. Tous droits réservés.
