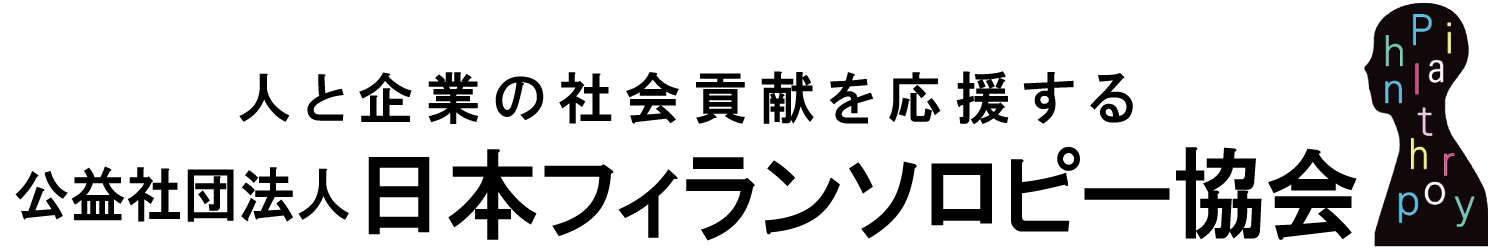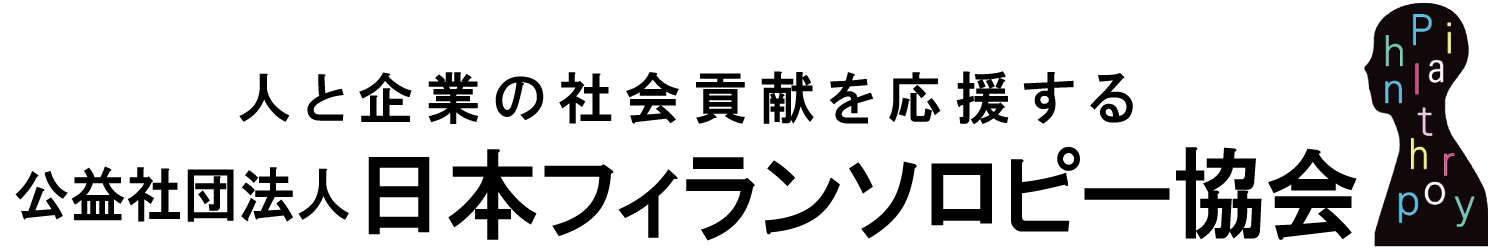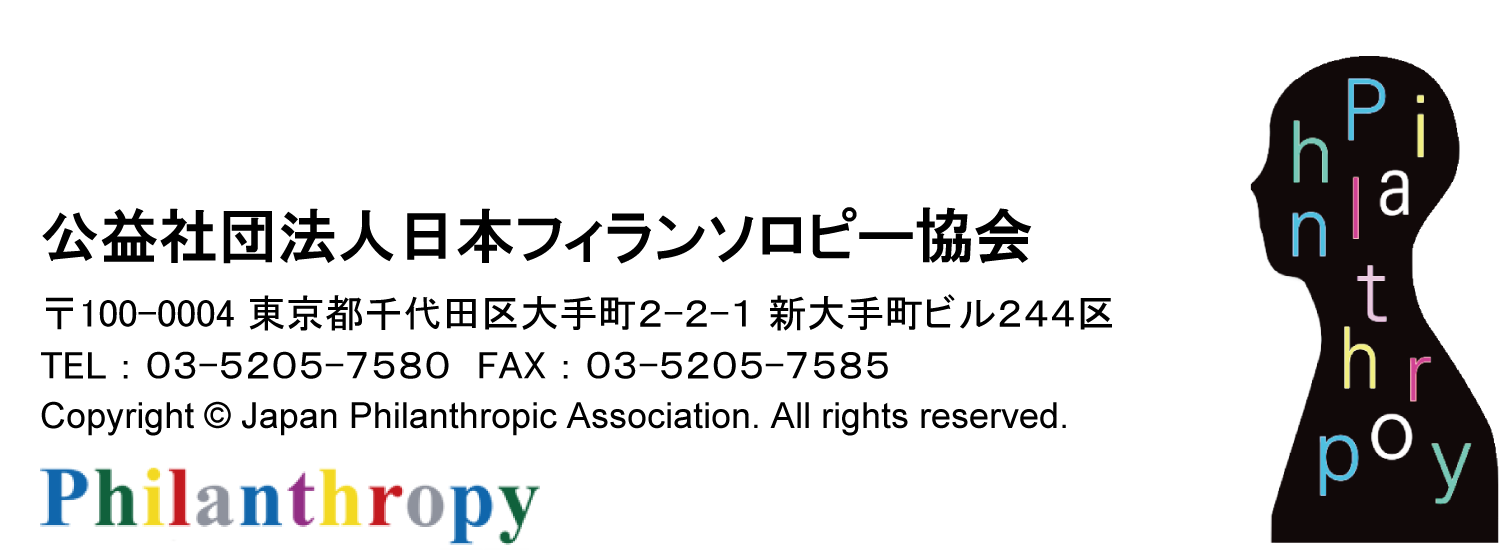コロナ禍3年目の今年の夏は、厳しい暑さと自然災害にも見舞われ、気持ちを抑えながらも、それぞれの判断で夏休みを楽しんでおられるのではないだろうか。
当協会の機関誌『
フィランソロピー』で映画や文化のコラムを書いていただいている石井純さんを訪ねて、小豆島に行ってきた。石井さんは、元パナソニック株式会社常務で、会社人生の最後はメセナ担当だった。そして、今は、小豆島に移り住み、祖父母がかつて住んでいた家を私設ミュージアムにしている。
ジョルジュ・ギャラリー というのだが、ジョルジュ・ルース(Georges Rousse/フランスのアーティスト)氏とは、阪神・淡路大震災後の復興支援で出会い、このミュージアム開設につながっている。
さらに、その裏手にある元醤油会館を『
醤の郷(ひしおのさと)現代美術館』として使用。小豆島につながりのある作品はじめ、100点余りの作品が展示されている。オークションで手に入れたものもあるが、石井さんのつながりが生んだ作品も多く、何ともリラックスしてかつ心温まる美術館である。

石井さんの祖父母の家に金箔を施した
インスタレーションアート
(ある位置から見るとこのように丸く見える)

元醤油会館を利用した
『醤の郷現代美術館』前景
そして、なんと、もう一つ美術館が増えていた。近くのレンガ倉庫をリノベ―トして、「MOCA HISHIO ANNEX」がオープンしていた。チューブで編んだり、段ボールで組み立てたりして創作したポップな作品群にこちらの気分もポップに盛り上がる。題して「ズガクリ」(ズガ・コーサク+クリ・エイト)館。折しも、3年に一度の
瀬戸内国際芸術祭2022 が開催中で、これらの美術館も参加している。
翌日、島の各所にある作品を見て回ったが、意外と数少ない観光客がいるだけで、島の人にとっては関係ない風である。直島(なおしま)や豊島(てしま)は多分、もう少し賑わっていると思うが、小豆島は、従来、瀬戸内の島々の中では食品産業も多く豊かな土地柄だったせいか、切迫感がないうちに衰退がじわじわ来ている感がある。
実際、面白かったのは島の人との出会いである。泊まった民宿のお爺さんは、港から電話をかけてルートを教えてもらい向かっていると、宿の前の道路に立って、ずっと両手を振って迎えてくれていた。その後の多少長いおしゃべりもウエルカムトークと納得。「パスタ+たこ焼き」というあり得ない組み合わせの定食を出す店のお兄ちゃんは、やっぱり大阪出身の移住者。排他的だけど優しい人が多い、とは移住6年目の弁。猛暑の中、バスを待つ間、ちょっと涼むつもりで入ったカントリーウエスタン気取りの餃子屋のおっちゃんは、妻にも子どもたちにも逃げられた、という話が頷ける、頑固さと寂しさをごちゃまぜに出してくる面倒なご仁であった。ただ、ウエスタンブーツ&ハットのいでたちながら、小豆島愛だけは全身から伝わってきた。
石井さんは、3年に一回ではない、毎年開催する小豆島の人たちと作る「もうひとつの芸術祭」を計画しているそうだ。自然と風土と人の暮らし。それが織りなす作品こそアートの根源か、と思いつつ・・。
機関誌『フィランソロピー』の次号(2022年10月号)のテーマは「社会インフラとしての文化芸術」。乞うご期待。