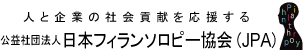2020.02.20
第18回/2つの映画から学ぶ「誰も取り残されない社会」とは?
ことし最初に観た映画は『男はつらいよ お帰り 寅さん』。昨秋、NHKで寅さんの少年時代を描いた『少年寅次郎』を観たのだが、寅さんは、赤ん坊の時、母親に捨てられている。実の父親の家にもらわれるが、その父親が寅ちゃんになぜか冷たい。温かく育んでくれたのが、父親の奥さん。物語は、その育ての母が亡くなった後、寅ちゃんが家を出て、フーテンの寅さんになっていくところで終わった。寅さんの幸せになることへの臆病さ、人のぬくもりを求め、でも、それに甘えられず、すっと消えていく。心底優しい心根。彼の生まれと育ち、そして、彼の死後、影響を受けた人たちの寅さんの温もりを求め、なぞるように生きている様。それが、50年経った今も根強い人気の所以だろう。それにしても、山田監督の人物の描き方に、今更ながら脱帽である。
次に観たのが、ドキュメンタリー映画の『プリズン・サークル』。島根あさひ社会復帰促進センターという刑務所に入所している受刑者の話。ここには、初犯などの男子受刑者2,000人が収容されている。ここは、全国で唯一「TC(治療共同体・回復共同体」)と言って、当事者たちが中心となり、お互いに語り合ったり、ロールプレイをしながら自己開示をする。相互に影響を与えながら、自分自身の犯罪に向き合い、受け止め、新たな価値観や生き方を身に着けるリハビリテーションのためのプログラムである。人間的成長を促すための場とアプローチを提供している。本人が希望し、かつセンター側でも可能だと判断した受刑者30名から40名が半年から2年程度、寝食や作業を共にしながら、週12時間程度のプログラムを受ける。
この映画では、主に4人の受刑者を追っている。彼らが向き合うのは、犯した罪だけではなく、幼児期に経験した貧困、いじめ、虐待、差別などの記憶や痛み、哀しみ、恥辱や怒りといった感情にも向き合い、それを表現する言葉を獲得するというプロセスを追う。自分の被害者にはなかなか向き合えないのだが、人のケースを話し合っている時には、被害者の傷を思うことができるという受講者がいた。そして、自分の犯罪について語りながら涙をぬぐう当事者に、「それは何の涙?」と突き付ける仲間。そして、少しずつ、自分と向き合えるようになる。それを臨床心理士など専門家がファシリテーターとして伴走する。
こうした取り組みがなされていることにも驚いたが、現在の受刑者約4万人のうち、TCを受けているのは40名程度だということにもっと驚いた。ますます、犯行に至る過程での体験の深刻化や複雑化が進む中、こうしたプログラムは、彼らのやり直しや再犯防止にも、非常に有効なはずだ。出所後も、時々、TC受講者が集まるサークルが設けられている。やくざなどに引っ張られそうになっている仲間に、叱咤激励が飛ぶ。
犯罪予防、そして、出所後の再生のためには、寅さんのような、寄り添って応援してくれる人がたくさん必要だ。そして、刑務所内での更生のためにも、非常にきめ細かいサポートが必要であることがわかった。TCプロジェクトも、参加者を増やすためには、対象者の特性や、心的状況・人間環境・体験のレベルなどに合わせた多様なプログラム開発も必要だろう。
支える人たちの育成や人件費が必要だ。これは、「税金で」とは言ってられない。民間の知恵とお金が不可欠である。個人寄付の行き先は、後を絶たない。誰も取り残さないためには、皆で支えることを考え、できることから行動に移すことが必要だと切に思う。
2019.12.29
第17回/一人ひとりの幸福に向けて(年末雑感)
最近、気に入っている番組がある。BS日テレの「小さな村の物語 イタリア」だ。名も知られていないイタリアの各地の小さな村に住む人たちの暮らしを追っている。一旦、村から都会に出て、戻ってきた人、生まれてからずっとこの村で暮らしている人、他の街から縁あってやってきて、この村を故郷にした人。それぞれに故郷に愛情と誇りを持ち、仕事をし、人生を送っている。ゆったりと流れる音楽と三上博史の静かで淡々と、そして愛情深く語り掛けるナレーションに、しばし、心穏やかな時間を過ごしている。この番組の魅力の一つは、村人たちの発する言葉だ。彼らは詩人であり、哲学者だ。先日の、年老いた料理人の女性の言葉。「何かに立ち向かう時は、のんびりしていた方がいい」
心臓弁膜症を持病に持つ8歳の少女は、「みんなができて自分にできない事は、慣れたので平気。今は、他の人にできないけれど自分にできることがあると思っている」と言って、趣味の手芸用品を作り、友人などにあげている。今では隣町から注文を受けるほどになっている。親の介護があり、進学をあきらめてずっと村で暮らす40代の主婦は、家族のために自分にできることがあることが嬉しいと、家族が集まる昼食づくりを楽しそうにしている。
アダム・スミスは、人間の幸せは、心が平静になっていることと言った。そんな言葉を思い出させてくれる、村人たちの珠玉の笑顔と言葉。
ここ数年、これまでの福祉やまちづくりの、思い先行の活動から、成果を見据えた合理的で戦略的な事業運営が大事だと言われている。そして、各NPOの活動の評価にも関心が高まり、より成果が期待できる、さまざまな新たな活動を、心ある優秀な人材が興し、また、そこにも若者が集まってきている。非常に頼もしいと思う。ソーシャルビジネスにも関心が向き始め、これまでとは違う新たな可能性が見えてきた。しかし、進んでいく中で、事業の利益と社会性の両立が困難で、ズレが出てくることがある。ズレを直し、しかも成果を出すには、卓越したアイディアと実行力、ネットワーク力を駆使するために不断の努力が必要になると思うが、その時に、手段が目的化しないように、心しなければと思う。誰のために、何のためにやっているのだろうか?を考えて立ち止まることが必要だ。現場の一人ひとりの声にヒントがある。
2020年最初の機関誌は、「今、改めてアダム・スミスに学ぶ」(仮題)というテーマ。2月1日に発行する。そして、2月21日は、第17回企業フィランソロピー大賞 の贈呈式だ。先日、機関誌に掲載するために、大賞の北良株式会社の笠井社長に話を聞いた。東日本大震災時の、釜石の奇跡について、こう語っていた。「小・中学生の生存率が99.8%と言われていますが、小学生は3名亡くなっています。救えなかったことがつらい。今度は、あらゆることをして助けたい」と、人材育成と機器の開発を進めている。数で捉えるのではなく、一人ひとりの名前のある人間の存在に目を向ける経営者の心意気と覚悟に圧倒された。
当協会の役割は、社会貢献のコーディネーターであるが、これからはより一層、現場の一人ひとりの思いや声を届けることに改めて心していきたい。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
2019.12.02
第16回/人生100年時代のかっこいい女性二人
観光客であふれる晩秋の鎌倉に、谷口奈保子さん(NPO法人ぱれっと 創設者)宅を訪ねた。この日は、ケニアで25年間、ストリートチルドレンを支え、彼らのために奔走する モヨ・チルドレン・センター の松下照美さんが谷口さん宅に滞在しておられるというので、ウキウキ、でもちょっと緊張しながら会いに行った。
 松下照美さん(左)と谷口奈保子さん(右)
松下照美さん(左)と谷口奈保子さん(右)
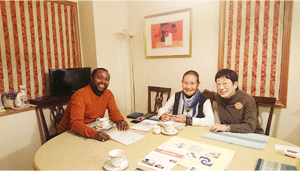 モヨ・チルドレン・センター理事で
モヨ・チルドレン・センター理事で
弁護士のボビーさんと
松下照美さんは、ご主人が亡くなられた後、1994年に、48歳で、たまたま訪ねたウガンダで出会った13歳の男の子が原点で、活動を始めたそうだ。その男の子は、「妹が亡くなった、土に埋められてしまう」と言って泣きながら土を掻いていた。抱きしめるしかなかったという。その後、1996年にケニアに移住し、英語は話せなかったという松下さん、54歳で語学学校に入り、英語を学びながらNGO設立の準備をした。そして、1999年、NGO設立の認可を得て、今日に至る・・・と思ったら、なんと、2000年に脳梗塞を発症した。日本に帰国し、手術。そして、3か月後には再びケニアに戻っている。超短髪は、手術の時に切ったのがきっかけで、そのままのヘアスタイル。ケニアでは洗髪は、体を洗う以上に水を使うし、この方が楽だからだそうだ。借家で「子どもたちの家」を発足。やってくる子どものほとんどが薬物中毒だそうだ。最初は、ご自身の年金の範囲で活動をしようと思っていたのだが、出身地の四国で支える会が発足し、その後、「ニュー・ホーム」という2軒目を設立。2018年には、政府の「草の根無償資金」とクラウドファンディングで、ストリートの子どもたちのリハビリを有機農法を通じて行う「ドラッグリハビリセンター」を完成、というように、活動も広がってきている。そして、今、74歳。「日本に出稼ぎに行ってくるねと言っているのよ」と笑う松下さんは、年1、2回は帰国し、支援者への報告を兼ねて、講演などで全国を回っているそうだ。
谷口奈保子さんは、松下さんより3歳上の喜寿。NPOぱれっとは、すでに後進に譲り、今は、ぱれっとインターナショナル・ジャパン(PIJ)で、スリランカ、マレーシア、モンゴルの障がい者のための作業所設立、就労支援、支援者の育成に尽力しておられる。お子さんを小児がんで亡くしたことをきっかけに病院ボランティアを経て、再度、社会福祉を学ぼうと、母校に入学、そして、41歳で「ぱれっとを支える会」を立ち上げた。日本ではじめて、障がい者の作業所でクッキーづくりを行った人だ。そして、障がい者の仕事を作るために、売れる商品としてクッキーを位置付けた社会起業家としてのパイオニアでもある。
お二人とも、彷徨う子どもたちのため、障がい者の自立のためという強い思いから始め、そして偏見や無理解との闘いも苦労も厭わない、まっすぐに突き進むというシンプルさを持つ。まさに、真実はシンプルであることを実証している。
もう一つの共通点は、70代に入って、今なお、未来に向かっていることだ。それは、自分の夢や生きがいとはかなり違うように思う。寿命を超えて、見ようとする子どもたちの、障がい者たちの未来だ。かっこいい先輩女性二人に触発され高揚した、鎌倉の週末だった。

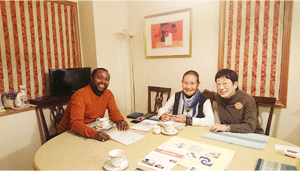
弁護士のボビーさんと
2019.09.30
第15回/郡山市における農福連携


2.8ヘクタールの畑で60種類もの野菜を育てている埼玉県三芳町の明石農園のお話。代表の明石誠一さんは、28歳の時に東京から移り住み、新規就農した人だ。有機農法からスタートし、10年前からは農薬や除草剤、さらに肥料さえも使わない「自然栽培」に取り組んでいる。ここでは、野菜同士が互いを育てる肥やしになり、雑草は3年を経て有機物に富んだ堆肥になるのだそうだ。種も、ほとんど市販の種を使わず、畑で育てた野菜から種採り(自家採種)しているので、不揃いな野菜が出来るが、「不揃いであることが自然の本来の姿だ」と明石さん。「それは人間も同じだ。どんなに重篤な障がいを抱えた人も、その人の存在価値はある。」「競争社会から共生社会へ」を農を通じて実践している。明石農園には、多くの就農希望者がやってきて、ワイワイ、ガヤガヤ、失敗しながら野菜作りに悪戦苦闘している。20年前に、奈良県で自然農法をする方を訪れたことを思い出した。修行僧のようなところがあり、俗世間から離れた、孤高の人の風情を持っておられた。今は違う、子育てしながらのお母さんも、若者も、早期退職の人も、障がいのある人も、料理教室やコンサートを開いて、楽しみながら、新規就農に挑戦している。そうした顔の見える野菜を購入する消費者も増えてきた。
【農福連携】農業者と、社会福祉法人やNPO法人などの福祉団体が連携して、障がい者や高齢者らの農業分野での就労を支援する取り組みの総称。当協会の 農福連携推進モデル構築事業(福島県郡山市委託事業)
2019.09.02
第14回/久里浜少年院訪問記


2019.08.15
第13回/終戦記念日に「つながり」を思う
強い日差しと真っ青な空が定番だった8月15日の終戦記念日。台風襲来で、被害の少ないことを祈るばかりだが・・・。終戦記念日の記憶の映像が代わるようで、それ自体が、何だか不安になる。真夏の青空の下での平和への希求を、私たちの絶対的な価値として持ち続けることを再確認する日だ。
ところで、ことしのお盆は、仕事はしつつも早めに帰宅し、迎え火を焚き、仏壇には、それなりに(?)盆飾りらしきものを設え、またまたそれなりのご馳走を供えたりしている。いつもより、ゆったりと仏壇の前に座り、お位牌を裏返してみたりしていると、蜷川幸雄のマクベスの舞台を思い出す。仏壇を舞台に見立てたシェークスピア劇。巨匠蜷川の、何とも自由な発想に驚嘆したものだが、実際には、企画に行き詰った時に、実家に帰って仏壇に手を合わせていて思いついたのだそうだ。確かに、仏壇の中には、代々の先祖の人たちの人生が詰まっているように思う。
私の曾祖母は、私が9歳の時に88歳で亡くなったが、私の知っているひいおばあちゃんは、おぼつかない足取りで家の中を手を引いてもらって歩いているか、横になっていた。そんな姿しか思い出せない。しかし、そのお位牌の裏を見ると、ひいおばあちゃんの夫が30歳で亡くなり、息子は21歳で亡くなっていることが分かる。3人の子どもを抱えて20代で未亡人になり、やっと育てた息子をこの若さで亡くし、さぞ苦労し、辛い思いをしたのだろうと今頃になって思う。「もっとやさしくしてあげればよかった」と、何と60年近くもたって反省する愚かさよ。先祖たちは皆、それぞれに幸せや不運を味わった人生を生き切ったのだろう。そう考えると、仏壇は、見えない人たちのドラマがいっぱい詰まった劇場である。そして、それらがずっとつながって自分があることを改めて思い知る。それは、血縁という意味だけではなく、生命はずっとつながって、そしてまた、次につなげていくという見えないものを感じるというようなことだろうか。そう思うと、今、この時代に生きている人たちもつながっている。「つながり」が人を支えているのかもしれない。
ホームレスとは、単に住む家がないハウスレスではなく、つながりがなくなっていることを指すのだそうだ。数年前、横浜の公園で、夜中にホームレスの男性が中学生に襲われた事件があった。被害者である男性は、「あの子たちは家はあるけれど帰るところがないのだと思う。心配してくれる人がいないのだなー。あの子たちの気持ち、わかるなー」と言ったそうだ。そんな子が増えている。彼らのつながりのほころびを縫い、つながりを丁寧に紡ぎ続けることが、今、私たちに求められているように思い至る。おっと、疎かになっている自分の周りとのつながりも忘れずに・・・。たまに仏壇に丁寧に向き合っていると、殊勝な気持ちになる終戦記念日だ。チーン。
2019.07.29
第12回/参議院選挙と映画「新聞記者」から民主主義を考える
令和最初の参議院選挙が終わった。多くの課題が山積する中、乱立する主張のわかりにくさに、「選択肢なき消去法」と言われるような逡巡を持つ有権者が多く、その結果、全体の投票率は48.8%、さらに、18歳と19歳の投票率は31.33%という低さ。私が育った高度経済成長期は、国際政治でいえば、冷戦の時代。国内政治も、その下で、資本主義か共産主義か、あるいは間の社会主義かのイデオロギー対決であり、ある意味で分かりやすい選択であった。今は、イデオロギー論争ではなく、政策論争・・・のはずだが、イメージ論争になってしまった。テレビ報道も、当日だけ、まるでショーのような過熱ぶりだが、一日たてば、単なるイベントが終わったように事件モノと芸能ネタでもちきりである。国民の民度以上の政治はできないというのであるから、自らを反省するしかない。
当協会は、「日本に健全な民主主義を育成する」ということをミッションに活動している。民主主義は、永田町や霞が関から与えられるものではなく、国民一人ひとりが現実を直に見たり、体験することで他者の不足と痛みを感じ、考え、議論し、選択し、行動することだと思う。実際、フィランソロピーは直接民主主義と言われている。自らの発意で税金ではなく寄付を、代議制の代わりにボランティア等、自分が持てるものを提供する。自分の日常の中でどうすべきかということを模索しながら選ぶことに民主主義の真実があるのではないだろうか。
映画「新聞記者」を観た。
記者の姿を通し、強大な権力と対峙しつつ真実を伝えようとするジャーナリストの志と使命を浮き彫りにしている。もっとも、フィクションの中に、実際の事件の中心人物など実在の人物も登場させて、現政権への批判を思い起こさせる手法には少々興ざめしたが。いちばん心に響いた場面はラストシーン。真実を暴露した記者と、内閣情報調査室(内調)職員が道路を挟んで見つめ合っている。それぞれの、仕事への確固とした矜持と共に、平安な暮らしを保証してあげたいという家族への心情。その狭間で苦悩し、そして選んだ父としての誇り、父に呼応する子の生きざま。二人の俳優の演技も素晴らしかった。実際に、観て感じていただきたい。人権、公正、平和への希求は守るべき価値。しかし、それを貫くことは、心身ともの危険や身近な人の苦難を起こすこともある。その狭間で人間は迷い、逡巡し、そして選択し続けている。民主主義を健全に育成するということは、迷いや葛藤の連続ではないだろうか。だからこそ、生身の人間の苦しみに触れることで、そこから逃げずに考え続けるという「体験と思考の繰り返し」が大事なのだと思う。他者の痛みを感じ取り、持てるものを分け合う力を引き出すことに、諦めずに葛藤しながら(笑)挑戦し続けたいと思う。そうすることで、教育の本質も、「誰も置き去りにしない」というSDGsの本質も見えてくるのではないだろうか。
2019.06.18
第11回/石巻日日こども新聞
東日本大震災から1年後の2012年3月11日に創刊した 石巻日日こども新聞。季刊発行し、6月11日に30号を出した。発行部数は3万部。日本だけでなく、海外でも読まれている。発行元は、公益社団法人こどもみらい研究所。代表の太田倫子さんは、震災後、参加したイベントで、笑わない子どもたちがいることが気にかかった。悲惨な苦しみや悲しみを受けた子どもたちには、それを吐き出すことが必要だと考え、表現手段の一つとして新聞発行を思いついた。太田さんの故郷である石巻市には、石巻日日新聞があった。同紙は、震災後の1週間、電気が来ない中、模造紙に手書きで書いた壁新聞を避難所などに配ったことで知られる(第7回ブログ で紹介)。太田さんは、同社の近江弘一社長に相談し、印刷などの協力を取り付けた。取材や執筆は子どもたちが担当する。小学校5年生から高校3年生までの子どもたちが毎週土曜日に集まり、企画を考え、聞き取りや執筆のワークショップなどをして腕を磨いている。
 ダンボールで作ったロータリーエンジンとキーホルダー
同研究所の目的は「子どもたちの『つくる』『つたえる』『つながる』を応援すること」。子どもたちの持つ好奇心や感動する心、それを引き出し応援する太田さんの揺るぎない覚悟と一途な願い。石巻の今を伝える紙面からそれらが滲む。もう一つの子どもたちの活動に、商品開発とその販売がある。6月11日号には新商品の発売について載っている。キーホルダー「ロータリー」だ。作者の小俣渓志郎くん(小6)は大の車好き。特に、マツダのローターリーエンジンがお気に入りだとか。あまりに好きすぎて、ある日、ダンボールで模型を作ってしまったそうだ。
それから、色を付けて、Tシャツにでも紙にでも、とにかく描きまくっていたそうだ。それを知った今野梱包株式会社の今野英樹社長から「キーホルダーを作りませんか?」と声がかかって、この度完成したという。売り上げは、小俣君の希望で「京都大学ips細胞研究基金」に寄付するという。子どもの感性と表現力はすごい。それを引き出すのが教育の本質。
しかし、悲惨な体験を吐き出すことが出来ないまま苦しんでいる子どもたちがいる。
ダンボールで作ったロータリーエンジンとキーホルダー
同研究所の目的は「子どもたちの『つくる』『つたえる』『つながる』を応援すること」。子どもたちの持つ好奇心や感動する心、それを引き出し応援する太田さんの揺るぎない覚悟と一途な願い。石巻の今を伝える紙面からそれらが滲む。もう一つの子どもたちの活動に、商品開発とその販売がある。6月11日号には新商品の発売について載っている。キーホルダー「ロータリー」だ。作者の小俣渓志郎くん(小6)は大の車好き。特に、マツダのローターリーエンジンがお気に入りだとか。あまりに好きすぎて、ある日、ダンボールで模型を作ってしまったそうだ。
それから、色を付けて、Tシャツにでも紙にでも、とにかく描きまくっていたそうだ。それを知った今野梱包株式会社の今野英樹社長から「キーホルダーを作りませんか?」と声がかかって、この度完成したという。売り上げは、小俣君の希望で「京都大学ips細胞研究基金」に寄付するという。子どもの感性と表現力はすごい。それを引き出すのが教育の本質。
しかし、悲惨な体験を吐き出すことが出来ないまま苦しんでいる子どもたちがいる。 キーホルダーの袋に入っている説明書きそんな子どもたちを応援しようと思い、「誕生日寄付」事業を始めた(第9回ブログ で紹介)。年に1回、いのちを与えられた誕生日に感謝と共に寄付しよう、という運動だ。彼らに寄り添い、見守る大人の存在が子どもたちの支えになると、ある精神科医に教えてもらった。7月6日には、発足記念の チャリティパーティ を開催し、困難の中にいる子どもたちの現状や課題を寄付先の団体の方にお話しいただく。太田さんも石巻から駆け付けてくれるという。子どもたちの困難に寄り添い、子どもたちの希望と夢を応援する仲間が増えることが楽しみだ。
キーホルダーの袋に入っている説明書きそんな子どもたちを応援しようと思い、「誕生日寄付」事業を始めた(第9回ブログ で紹介)。年に1回、いのちを与えられた誕生日に感謝と共に寄付しよう、という運動だ。彼らに寄り添い、見守る大人の存在が子どもたちの支えになると、ある精神科医に教えてもらった。7月6日には、発足記念の チャリティパーティ を開催し、困難の中にいる子どもたちの現状や課題を寄付先の団体の方にお話しいただく。太田さんも石巻から駆け付けてくれるという。子どもたちの困難に寄り添い、子どもたちの希望と夢を応援する仲間が増えることが楽しみだ。


2019.05.07
第10回/令和時代を迎えて
5月1日、平成から令和に元号が移った。
発案者の中西進氏によると、「うるわしい平和を築こう」という意志を表すものだという。上皇さまが退位にあたり、「平成の時代が平和であったことを感慨深く安堵している」と述べられたことは、誠にずっしりと重い。戦争体験を持たないものとしては、その重みを実感する由もないが、想像をめぐらすことで、平和をより進化させていくことが、今を生きるものとしての責務ではないかと改めて自らに問うている。
 ちょうど、ゴールデンウイークに重なり、ことしは新天皇即位に合わせて10連休。新潟の十日町市に行ってきた。十日町は、全国の棚田ファンの間では、聖地として知られているとか。
信頼資本財団の熊野英介理事長に声をかけていただき参加した。助成先を訪ね、その地の地元の人たちの町おこしや地域活性化への取り組みを聞き、対話をする「シンライノテーブル」の一環として、今回は、十日町市松代で古民家再生をし、現在、農家民宿として「棚田再生」にも取り組んでいるトロノキハウスに宿泊させていただいた。トロノキハウスは、古民家再生をライフワークとする建築デザイナーのカールベンクス氏の作。オーナーの阿久澤剛樹さん、運営管理者兼調理人で、本職は気象サービス社長の池田徹さんの最高コンビのおもてなしで、地元の地域プロデユーサーたちとの対話で盛り上がった。それにしても、持参いただいた地元料理の数々は絶品。ちょうど山菜の時期でもあり、おいしい山菜料理と新潟の各種酒の数々にはうっとりだった。さて、棚田は写真でもご覧のとおり、100年以上続いている。ただ、最盛期の20分の1になっているという。どこも同じだが、高齢化が進み、ことし限りというところも多いと聞く。
ちょうど、ゴールデンウイークに重なり、ことしは新天皇即位に合わせて10連休。新潟の十日町市に行ってきた。十日町は、全国の棚田ファンの間では、聖地として知られているとか。
信頼資本財団の熊野英介理事長に声をかけていただき参加した。助成先を訪ね、その地の地元の人たちの町おこしや地域活性化への取り組みを聞き、対話をする「シンライノテーブル」の一環として、今回は、十日町市松代で古民家再生をし、現在、農家民宿として「棚田再生」にも取り組んでいるトロノキハウスに宿泊させていただいた。トロノキハウスは、古民家再生をライフワークとする建築デザイナーのカールベンクス氏の作。オーナーの阿久澤剛樹さん、運営管理者兼調理人で、本職は気象サービス社長の池田徹さんの最高コンビのおもてなしで、地元の地域プロデユーサーたちとの対話で盛り上がった。それにしても、持参いただいた地元料理の数々は絶品。ちょうど山菜の時期でもあり、おいしい山菜料理と新潟の各種酒の数々にはうっとりだった。さて、棚田は写真でもご覧のとおり、100年以上続いている。ただ、最盛期の20分の1になっているという。どこも同じだが、高齢化が進み、ことし限りというところも多いと聞く。
 「観光地から関係地へ」「人口密度ではなく人交密度の高い地域へ」のモデル地域にしたい、棚田再生をそのきっかけにしたいという阿久澤さん。彼の本職はホテルアセットマネジメント。複数の外資系ホテルの運営会社の社長でもある。そのノウハウを活かして、里山アセットマネジメントを提唱。トロノキハウスを拠点とした棚田再生を核にして、2拠点居住を実践しながら、愉快に挑戦を始めている。豊かさの概念を改めて考え直し捉え直すような、土地・人・課題との出会いであり、当協会の使命と役割にとって、様々な気づきもいただいた。先憂後楽ではなく、先向共楽の時代にしたいと思う「令和」の幕開けであった。
「観光地から関係地へ」「人口密度ではなく人交密度の高い地域へ」のモデル地域にしたい、棚田再生をそのきっかけにしたいという阿久澤さん。彼の本職はホテルアセットマネジメント。複数の外資系ホテルの運営会社の社長でもある。そのノウハウを活かして、里山アセットマネジメントを提唱。トロノキハウスを拠点とした棚田再生を核にして、2拠点居住を実践しながら、愉快に挑戦を始めている。豊かさの概念を改めて考え直し捉え直すような、土地・人・課題との出会いであり、当協会の使命と役割にとって、様々な気づきもいただいた。先憂後楽ではなく、先向共楽の時代にしたいと思う「令和」の幕開けであった。


2019.04.12
第9回/誕生日寄付開始
5月1日、平成から令和に元号が移った。
本年1月25日に「誕生日寄付」サイトをオープンし、約2か月半が経った。これまで誕生日登録者が130名、寄付をしてくださった方が50名。これから本格的に拡げたいと思っている。
「誕生日寄付」プロジェクトのヒントは、元Jリーグのチェアマン川淵三郎さんにいただいた。社会貢献としての寄付をした人を顕彰する 第20回まちかどのフィランソロピスト賞 の特別賞を受賞していただいた川淵さんは、25年以上も、誕生日に寄付をしておられる。寄付先は、さわやか福祉財団。寄付を始めるに当たり、川淵さんは、同財団の当時の理事長(現会長)堀田力さんを訪問し、堀田さんに気になっていたことを聞いた。「寄付は、ボランティアより価値が低いのだろうか?自分は、身体は動かせないので寄付で貢献したいのだけれど」。堀田さん「寄付もボランティアもどちらも尊い。自分ができることで役立つことが大切」。では、と川淵さんは続けた。「いくらぐらいするのがいいでしょうか?」堀田さん「そうですね。ちょっと痛い金額がいいですね。」
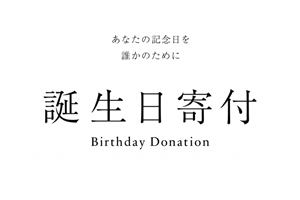 この言葉に川淵さんは痺れた。それからずっと、ちょっと痛い金額を寄付し続けているそうだ。
さて、本「誕生日寄付」に寄付してくださった方の寄付もなかなか痺れるものがある。96歳の方が、ことしは96,000円寄付してくださった。ことし還暦だという私の友人は60,000円。34歳の青年は3,400円。それぞれ、ちょっと痛い金額を毎年続けてくださるという。
この仕組みを利用すると1,000円から30万円までの寄付ができる。それ以上の金額は、振り込みでお願いしている。
メッセージもなかなか興味深い。大人になってからの誕生日はそれほど嬉しくもないものになっていた。「誕生日寄付」に参加することで、これからの自分の誕生日が少しでも意味のあるものになることが嬉しいという声が多い。今年度の寄付先は、今、苦しい状況にあり、つらい思いをしている若者を地道に支援する6団体。地味だが粘り強い活動をしている団体を選ばせていただいた。
7月6日(土)には「誕生日寄付」発足記念チャリティパーティを開催する。ぜひ、お越しいただきたい。近日中にHPにもアップする予定だ。
まずは、誕生日登録をいただきたい。登録いただければ、誕生日にメールが届くことになっている。いのちに感謝して、次世代を担う若者を支え、未来に投資する仲間を増やしたいと思っている。
この言葉に川淵さんは痺れた。それからずっと、ちょっと痛い金額を寄付し続けているそうだ。
さて、本「誕生日寄付」に寄付してくださった方の寄付もなかなか痺れるものがある。96歳の方が、ことしは96,000円寄付してくださった。ことし還暦だという私の友人は60,000円。34歳の青年は3,400円。それぞれ、ちょっと痛い金額を毎年続けてくださるという。
この仕組みを利用すると1,000円から30万円までの寄付ができる。それ以上の金額は、振り込みでお願いしている。
メッセージもなかなか興味深い。大人になってからの誕生日はそれほど嬉しくもないものになっていた。「誕生日寄付」に参加することで、これからの自分の誕生日が少しでも意味のあるものになることが嬉しいという声が多い。今年度の寄付先は、今、苦しい状況にあり、つらい思いをしている若者を地道に支援する6団体。地味だが粘り強い活動をしている団体を選ばせていただいた。
7月6日(土)には「誕生日寄付」発足記念チャリティパーティを開催する。ぜひ、お越しいただきたい。近日中にHPにもアップする予定だ。
まずは、誕生日登録をいただきたい。登録いただければ、誕生日にメールが届くことになっている。いのちに感謝して、次世代を担う若者を支え、未来に投資する仲間を増やしたいと思っている。
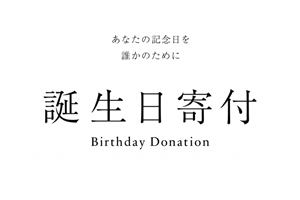
※川淵三郎さんと「ちょっと痛い金額」のお話は、機関誌『フィランソロピー』2018年12月号 に掲載しています。(全文をご覧いただけます。)
「理事長・髙橋陽子のブログ/2019年度」おわり