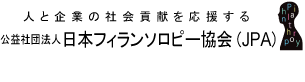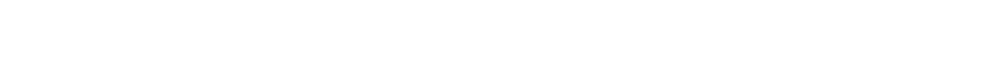
2025年8月号
Date of Issue:2025.8.1
Date of Issue:2025.8.1
◆ 巻頭座談会/2025年8月号
障がい者と共に旅を楽しむために
一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会顧問
久保 厚子 さん(写真右)
一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会会長
佐々木 桃子 さん(写真左)
<ファシリテーター>株式会社セントラルツアーズ営業部法人営業課課長
三浦 啓代 さん(写真中)
障がい者や高齢者、外国人の生の声を聞き、バリアフリー施策に反映させる。岐阜県高山市の取り組みは、観光と福祉を連携させた先進事例として耳目を集めた。この取り組みに共感し、当協会では同市でバリアフリーモニターツアーを企画・実践した。その後、「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方から、観光の領域ではユニバーサルツーリズムと呼ばれるようになった。
旅を取り巻く環境はどう変わったのか。当事者や家族の苦労や不安は解消されたのか。知的障がい者の権利擁護、各種施策の整備や充実を求めて活動する久保厚子さん、佐々木桃子さん、旅をコーディネートする三浦啓代さんに、実体験に基づく旅の苦労と楽しみについて語ってもらった。
障がい児との旅行で苦労したこと
三浦 佐々木さんも久保さんも、重度の知的障がいがあるお子さんがいらっしゃいますが、旅における体験やご苦労をお話いただけますか。

久保 息子は着替え、食事、トイレ、入浴などすべてに支援が必要な最重度障がい者ですから、外出の際は私一人では無理なので、夫のサポートが必要です。やはり宿泊はハードルが高いです。施設内の段差といった物理的なことだけではなくて、夜寝ないとか、声を出すこともあるので、ほかの宿泊者のご迷惑になるのではないかと、車の中で食事をしたり寝たこともありました。安心して泊まれるところがあれば、と思うことはありますね。
佐々木 うちの息子も小さい頃は夜興奮して寝なかったので、泊りがけで旅行に行ったときは、夫が車でホテルの周りを回って寝かしつけたりしていました。初めて行くところは慣れないので、同じところに行くことが多いです。ほかのお客様に気を遣うので、食事は部屋出ししてくれるところにするとか、夫が一人で息子を入浴させるのも大変なので、見守りしてもらえる友人家族と一緒に行くことが多いですね。
いま38歳で、平日グループホーム、週末にわが家に帰ってくるという生活パターンですが、夏休みや年末年始、ゴールデンウィークも家に帰ってきます。そうすると、必ず「ホテル」って言うんですよ。旅行に行きたいという意思表示なんです。長野県の原村にお気に入りのペンションがあって、息子がそこのご主人のことが好きなので、夏はよく行きます。
深刻なトイレ問題
佐々木 久保さんがおっしゃるように、一人で息子を連れて行くのは本当に大変です。小学生のときに、障がい児のための合宿に参加させたのですが、迎えに行ったとき、私がトイレに行きたくなったんです。小学校高学年でしたから、女性用のトイレに連れて入るのははばかられたので、トイレの入り口で「ここで待っててね」と言い聞かせたのですが、出たらいなかった。改札口のところに立っているのを見つけた時はほっとしました。親がトイレに行くときには、誰か見守ってくれる人が必要なんです。
三浦 トイレの問題は大きいですね。今回の万博会場では、多種多様なトイレ設備が注目を集めていますが、バリアフリートイレ、オールジェンダートイレなども設置されています。

佐々木 2021年の東京オリパラのときに、トイレについて意見したことがあります。障がい者だけではなくて、高齢者や病気の方も含めて、一人で用を足せない人もいます。男女で一緒に入れるトイレを要望しましたが、なかなか理解してもらえませんでした。発達障がいのご家族をお持ちの委員が、必要だと言ってくれました。
新国立競技場には、車椅子用、オストメイト対応、多目的シート対応、オストメイト・多目的シート付車椅子用、男女共用トイレなど、さまざまなトイレが整備されました。補助犬用トイレもありますし、聴覚障がい者に緊急事態を知らせるフラッシュランプも設置しています。また、外部の音をなるべく遮って気持ちを落ち着かせることができる「カームダウン・クールダウンスペース」もあります。自閉スペクトラム症の人などはパニックが生じることがありますが、そんなときは特に声をかけず、15~20分ほど静かに過ごせる場所があれば落ち着くことができるんです。こうしたスペースが認められたことは画期的でした。
久保 万博会場のトイレは車椅子利用者を意識してつくっていたと思います。障がい者イコール車椅子、という認識があるようですが、知的障がい者や発達障がい者も考慮に入れてほしいと、大阪府の育成会でも声を上げました。
知らないから想像できない 当事者が声を上げる必要性
佐々木 カームダウン・クールダウンスペースについては、東京オリパラのとき、「誰でも休憩できるスペースにすればどうか」という意見が出ました。それも必要かもしれませんが、知的や発達障がいの人は刺激があると困るので、「誰でも使える部屋」だと使えないんです。今回の万博では数カ所設けられたようです。当事者が声を上げないとわからないと思います。

三浦 知らないと想像ができないですからね。支援学校の修学旅行の手配を担当した際、夜尿への備えとして防水シーツを用意しました。宿泊施設に事前に確認すると、「対応はご自身でご準備を。万が一の際はクリーニング代をご負担ください」と大人の方の夜尿は考えたことがないといったニュアンスでした。赤ちゃんの排泄周りのことは想定されている一方で、障がいのある方への配慮はまだ浸透していない施設も多いと感じます。
久保 息子はある程度は歩けますが、自分で排せつを知らせることができないので、おむつをしています。旅行や遊びに行ったときに、おむつを替えたいのですが、赤ちゃん用のベッドはあっても大人用はない。大人用がほしいですね。
佐々木 先日、赤坂迎賓館で内閣府主催の共生社会を目指すイベント「ともともフェスタ2025」が開催されたのですが、前庭で地面がガタガタしていて、車椅子利用者には不便でした。屋外にトイレも設置されていましたが、ベッドはないし、寝台型の車椅子だと回せない。ストレッチャーで外出するということは想定されていないんですよ。知的障がいも軽度から重度まで、大変さも違うので、同じ知的障がいの親でもわからないことはあります。
三浦 当事者からお話を聞いたり、体験しないとわからないですね。
佐々木 プールも、家族用の更衣室がないところには連れていけません。でもある時プールに行ったら、私たち家族より前に家族用更衣室を使われていたのが、高齢のご夫婦でした。ご主人が病気の後遺症がおありでリハビリのためにプールにいらしていた。一人では着替えが難しいので奥様が手伝っておられました。
心のバリアフリー 地域で理解を深める
三浦 不便という視点で見ると、共通することがありますね。これまで、誰かに助けてもらったという体験はありますか?
久保 息子の下に娘が2人いるのですが、息子が京都の病院に通っていた時に、下の娘を母に預けて、上の娘は連れて行きました。息子は7歳まで歩けませんでしたから、当時バギーに乗せていたんです。駅の階段に差し掛かったときに、娘と荷物を置いて、先にバギーに乗せた息子を上げようと思っていたら、若い男性二人が、「自分たちが担ぎますよ」と息子を上げてくれたんです。私は娘と荷物と一緒に上ることができました。すごく助かりましたね。見るに見かねて、かもしれませんが、最近は若い方が割と手伝ってくださるんですよ。
三浦 助け合いを進めるためにも、地域ぐるみで理解を深める取り組みも必要ですね。
佐々木 そういう意味では、町内会や自治会と施設の人たちが意見交換、情報交換するような場が少ないですね。講演会はわりとありますが、日常のつながりがない。同じ町内のご近所さん同士として、違う組織が出会う場は必要だと思います。
育成会は全国に100カ所以上ありますが、啓発のためのキャラバン隊活動として、知的障がい者の特性を理解してもらう疑似体験などもやっています。差別解消法で民間事業者も合理的配慮の提供が義務化されましたから、例えば通所の際に利用する公共交通機関にも声掛けしています。
でも、どちらかと言うと障がい者の団体側からの働きかけですから、町内会、PTA、公共施設や公共交通機関の側がやってくださると、一般の方の参加のハードルも下がるのではないかと思います。
ユニバーサルツーリズムの情報が利用者に届かない現実
三浦 ユニバーサルツーリズムの一環として、例えば入浴介助サービスを積極的に展開している温泉地があります。また万博では、LET`S EXPOという団体が、車椅子を押したり、視覚障がい者の手引きをするサービスを行なっているのですが、ご存知ですか?
久保 どこにどのようなサービスがあるかは、あまり伝わってこないですね。入浴介助サービスは、温泉の旅館協同組合のようなところでやっているのですか?
三浦 各地のバリアフリーセンターを中心に取り組みが広がり、地域が一体となって意欲的に進められています。実施されている方の思いや利用者の喜びの声を聞く中で、より多くの方に知っていただけたらと感じました。
久保 当事者やその家族にはあまり伝わってこないですね。もっとPRしてくれるといいのですが。
佐々木 お風呂のことで旅行をあきらめる障がい者はけっこういます。行ったときに嫌な体験をしてしまうとトラウマになります。逆に良い対応をしていただいたところは安心なのですが、同じところばかりに行くことになってしまう。情報をいただけるとありがたいですね。うちの会報誌などにも掲載できますから。
久保 息子の好きなところに連れて行ってやりたいと思うけれども、ハード面やサービスのことを考えるとなかなか思うところに行かれません。
佐々木 先日、ユニバーサルツーリズムで帯広に行ったときに、あるご家族が朝食で個室のような場所に案内されていました。ちょっと騒いでも大丈夫なようにホテル側が手配してくれたんです。分けることが差別につながると思いがちですが、ああいう気遣いはうれしいですね。
久保 パーテーションがひとつあるだけでも違います。分けたほうがいいですか、このままでいいですか、と聞いてくださるといいと思います。遠慮したり考えすぎてしまうより、聞いてくだされば、お願いしたいことはお願いできますから。
ボランティアに望むこと
三浦 LET`S EXPOで、ボランティアを募集したら2週間ぐらいで700人ほど集まったそうです。万博というキーワードもあるかもしれませんが、ボランティアをしたい人は一定数いると思います。だからこそ万博後も各地で広がればいいですね。
佐々木 知的障がいの場合、目が離せない、一人で置いておけない、ということがあります。そんなときにちょっと見ていてください、とお願いできるボランティアがいるとすごく助かりますね。見守るだけならそんなに難しいことはありません。
以前PTAをやっていたときに、「夏の学校」というイベントをやったことがあります。小中高で60人ほど参加するのですが、ボランティア初参加という人には軽度の人をお願いするといった調整をします。4年間やりましたが、事故は一度もありませんでした。
以前PTAをやっていたときに、「夏の学校」というイベントをやったことがあります。小中高で60人ほど参加するのですが、ボランティア初参加という人には軽度の人をお願いするといった調整をします。4年間やりましたが、事故は一度もありませんでした。
三浦 どうしたら楽しんでいただけるか、工夫が必要ですね。
佐々木 事前学習は大切だと思います。初めてのところは特に、親も含めて何が起こるかわかりません。事前に写真を見たり、この行程が終わったらどうするか、宿泊先でどうするか、などを調べて予測しておけば落ち着いて旅行ができます。施設や学校で行く場合はそういう準備ができますが、個人はなかなか難しいので、そういうところをサポートしてもらえると助かりますね。万博の場合、混雑しているでしょうから、予測困難なことも多いと思います。迷子が一番大変かもしれません。
久保 音が気になる人は逃げたいから、急に走り出したりするかもしれません。素早いから、振り向いたらいない(笑)。
三浦 カームダウン・クールダウンのスペースの場所は把握しておいたほうがいいですね。
大事なのは共に「楽しむ」こと
三浦 よく行かれる場所はどのようなところですか?
佐々木 中学生ぐらいまでは千葉県の勝浦によく行っていましたが、あるときから行かなくなりました。プールは好きなのですが、外海の波が怖くなったのかも知れません。成長につれて変化していると思います。あとは原村のペンションは、オーナーがとてもいい方で息子も大好きなので、息子からリクエストされます。知らないところはなかなか難しいし、混んだ電車だと大きな声を出したりするので、車で行けるところが多くなります。宿の食事は部屋に運んでくれるところだと気を遣わないのでいいですね。
久保 息子は仏像が好きなので、お寺には行きますね。こちらが退屈するくらい、ずっと見ています。千手観音のような細かい仏像よりも、大きくてドーンとした奈良の大仏とか涅槃像のような仏像が好きなようです。あとは動物園とか、歌舞伎も好きです。歌舞伎は本物を見せたいのですが、声を出したりするので、難しいですね。
三浦 バリアフリー演劇はありますから、バリアフリー歌舞伎もあったらいいですね。歌舞伎好きなボランティアの方も歓迎ですね。
佐々木 一緒に声を出せたら楽しいでしょうね。新しくできる秩父宮ラグビー場には、発達障がいや感覚過敏等の症状のある子どもと家族が安心して観戦できるセンサリールームができます。遮音されていて周囲の視線を避けた部屋で、防音ガラス越しに競技が見られます。歌舞伎観賞にもそういうスペースがあるといいですよね。
久保 障がい者70人ぐらいに対して、学生ボランティアを集めて毎年研修会をやっていたことがあります。そのときに学生たちが、「身構えていたけれども、友だちと一緒にいるのと同じだった」という感想を述べてくれました。
三浦 地域のつながり自体が希薄になっていますから、ユニバーサルツーリズムをきっかけにつながりが構築されるといいですね。
佐々木 自分も一緒に楽しめばいい。いろいろな企画をしましたが、しんどいけれども頑張れたのは、自分たちも楽しいからです。
三浦 旅にも可能性はありますね。
佐々木 ありますよ。楽しければ、次も行こうと思いますから。
(2025年7月1日 滋賀県厚生会館にて)
機関誌『フィランソロピー』巻頭座談会/2025年8月号 おわり