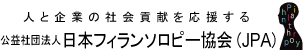Date of Issue:2018.2.1
<プロフィール>

福岡県久留米市生まれ。1960 年、東京大学医学部卒業。労働省入省、アジア、アフリカ、中南米の開発途上国の人材育成に約15年携わる。その後、3年間ニューヨークで国連日本政府代表部公使として外交活動に参画。官僚として30年のキャリアを積んだ後、The Body Shop(Japan) の初代代表取締役社長を10年務める。2002年に認定NPO 法人女子教育奨励会(JKSK=女性の活力を社会の活力に)を立ち上げ、現在に至るまで理事長として活躍。現在会長・理事長。http://jksk.jp/
◆ 巻頭インタビュー/No.384
~社会課題に対峙するための意識改革~
女性の活力を社会に活かす
女性の活力を社会に活かす
認定NPO 法人JKSK 女性の活力を社会の活力に
会長・理事長
会長・理事長
木全 ミツ 氏
木全ミツ氏は、東大医学部に入学、労働省(現厚生労働省)、国連、社会変革を推進する企業に関わり、現在、日本再生に女性の活力を活かそうと活動されている。男性優位の日本社会で、与えられたチャンスを最大限に活かして実績を築いてきた。その生き方はまさに「木全イズム」。その真髄をうかがった。
どんな時代・環境でも、自立して生きよう
― 子どものころに、満州から引き揚げて来られたのですね。
木全ミツ氏(以下敬称略) 9歳でした。父が軍医で満州の新京にいましたが、敗戦の数日前に父と別れ、母は5人の子どもを連れて朝鮮半島を渡り、舞鶴を経て九州の久留米に帰り着きました。
― お母様は苦労されましたね。
木全 明治生まれですが、福岡高等女学校に通っていたときに、振袖にラブレターを入れた若い軍医との大恋愛で結婚、それが父です。帰国後は、父とは音信不通の中、生活保護を受けながら、食べ盛りの子どもを前に、母は何もできませんでした。「日本の陸軍大将の妻になるのが夢だった母」のはしごをはずされた無力な姿に、「私は、あんな哀れな女にはなりたくない」、どんな時代、どんな環境に置かれても、自分の二本の脚で生きていける人間になりたいと思いました。
― まあ、9歳で自立を決意ですか!
木全 しかし、母のためになんとかお金を稼ぎたいと思いました。時々、家を訪問してくれていた父の部下のおじさまに相談すると、パンの訪問販売を教えてくださいました。その手助けも受けて、学校が休みの日曜日に、9円で仕入れて12
円で売ることに一生懸命。数か月間も売り歩いたでしょうか、3,000円を母に渡すことができました。
― 小学生なのにすごい行動力です。
木全 この体験から得た教訓は、「私の辞書には不可能という文字はない」。これが座右の銘となり、どんなこともNOと思わずやってみれば、ほぼできるという実体験を積み重ねることができ、私の人生を支えてきました。
― その後、音信不通だったお父様が帰られたとか。
木全 子どもたちが書き続けた手紙の1通が届き、家族は死んだと知らされていた父は、5年間のシベリアでの抑留生活後に、最後の引き上げ船で帰ってきました。その父が言ったのは、「日本に将来があるとすればテクノロジーだ。進学するならサイエンスの道を選べ」。そして「これからの日本には、男も女もない」という素敵な言葉でした。
― それで東京大学の医学部で公衆衛生を専攻されたのですね?
木全 日本の医学が進歩したと耳にする度に思ったことは、「医者にかかれる人は100人に2・3人。私は、医者にかかることができない90%以上の人たちに関わる仕事をしたい」ということでした。父に相談すると、「それは公衆衛生だ。地味
だしお金にならないが、一生の仕事とするならいい選択だ」と。
― 社会のために仕事をしたい。引揚や戦後の貧しさの体験が、木全さんを自立した正義感の強い少女に育てたのですね。
男性社会で、演じながら見える実績を残そう
― 志の高い少女が東大で公衆衛生を学び、仕事として官僚を選ばれたのは、どのような経緯からですか?
木全 卒業を控えて、将来についてみんなで話し合っていると、日本の公衆衛生のレベルアップを図っていくには、ひとりの力では何もできない。大学、研究機関、産業界、官僚などが連携をとりながら、響き合っていく必要があるのではないか、「あなたが官僚に…」と勧められ、正直、戸惑いを禁じ得ませんでした。
1959年当時、私は「ソビエト医学研究会」に属するラディカルな左翼派の学生で、仲間の間では「官僚は、国民のために何もなっていない、社会の癌だ」とまで言われていた時期。「あの、隠然とした力を持つ官僚を避けて人生を渡るのか、ひとりの力など大したことはないかもしれないが、どうして、中に入って改革しようと思わないのか」と自問自答。そして「よーし、改革をしていこう」と決めたのです。
1959年当時、私は「ソビエト医学研究会」に属するラディカルな左翼派の学生で、仲間の間では「官僚は、国民のために何もなっていない、社会の癌だ」とまで言われていた時期。「あの、隠然とした力を持つ官僚を避けて人生を渡るのか、ひとりの力など大したことはないかもしれないが、どうして、中に入って改革しようと思わないのか」と自問自答。そして「よーし、改革をしていこう」と決めたのです。
― なぜ労働省に?
木全 日本の社会では、労働者の人権(団体交渉、最低賃金、労働時間等)が守られていない、女工哀史をみるように女性の人権も踏みにじられ、また、児童労働が横行していました。その日本をアジア地域の同盟国、民主国家にしようする戦略をもっていたアメリカの影響を受けて、戦後に生まれた省庁である労働省を選択しました。5つの局があり(※1)、1950年から女性の大卒のキャリア官僚が採用され、彼女たちは、男女同権、男女雇用均等、男女共同参画、男女平等を主として担当した婦人少年局に配属されました。その後10年を経て、日本はOECD(経済協力開発機構)のメンバー国、つまり、先進国の仲間入りをしていく時代になり、私は、女性官僚が1人もいない職業訓練局に配属されました。
― ガチガチの男性社会に突入です。
木全 当時、働きたいと思えば、日本社会で生きていく以外に選択肢はありませんでした。批判しても始まらない。まず、男性社会を知ろう、自分の役割を演じていこう。女優になろうと思いました。
― そこで海外協力という、前例のない仕事に巡りあわれた?
木全 入省した当時、日本は高度経済成長期に突入しており、OECDの先進国として、世界の開発途上国に対して先進国らしい行動が求められ、その一例として、ODA(政府開発援助)がスタート。労働省では、人材の育成、つまり職業訓練の分
野で協力を開始することになりました。諸外国を相手に仕事をすることが前提にない労働省では、英語のできる大学卒業直後の者にと、私が担当することになりました。
― 英語はいつ学んだのですか?
木全 大学1年生のころ、日本もいつの日か先進国になり、あの欧米先進国と対峙する日が来る。その時、自分の言葉で堂々と話せないそんな哀れな日本人にはなりたくないとESS (English Speaking Society) に入会しました。おかげで開発途上国に対する人材育成分野の技術協力は、経験者も教えを乞える先輩もなく、前例もない中で、開発途上国の立場にたち、実にのびのびと仕事をさせてもらいました。
― 途上国の方々との関係は?
木全 初めて日本の地を踏んで、キョトンとしている参加研修生たち。最初は冷たいものでした。でも、真正面から一人ひとりと対峙し、職業訓練行政官セミナー等に参加してくる各国の高官と「あなたのお国の20年・30年後の社会を、どのようにしていこうとされているのですか、その時に必要な技能人材は…」と問いかけ、大いに語り合いました。熱心に話す参加者たちの目の奥にキラッと輝く情熱の光に、私の心の火が燃え上がるのを禁じ得ませんでした。
― 省内はいかがでした?
木全 当初、労働省の中では、「顔の色の違う人と変な言葉を使って、あれが労働行政かよ、仕事かよ」と継子扱いされましたが、最初は東南アジアからアセアン諸国、更にアジア全域、そして、アフリカ、ラテンアメリカを対象に研修生を受け入れました。最終段階では130余か国から年に500人を受け入れ、100人の専門家たちを家族とともにこれらの国に派遣し、更には、世界各地で海外職業訓練センターの設置・運営協力プロジェクトを50か所展開しました。
― お子さんもいて、出張が大変でしたね?
木全 「経済成長率に比例してODAの予算を増加させるように」というOECDのルールも反映し、ODAの仕事は「継子行政から」「うらやましい仕事に」変わっていきました。団長を、職業訓練局の幹部の方々にとどまらず、労働省の他の部局の幹部の方々にもお願いする時代に入っていきます。お願いする時は、出張計画、目的、交渉内容など周到なファイルを作成し、綿密なレクチャーを行い、有能な部下を同行させました。多くの幹部の方々に貴重な体験をしていただくことにより、貢献をしていただきました。
― 演じながら実績を作る、まさに木全イズムの真髄ですね。
木全 役所の上級職は、1年半~2年ごとに転勤と昇進があります。日本は、国際会議でもODAでも、1度限りの出張、すなわち「How do you do の外交※」になりがちで、各国との間に信頼関係が全く醸成されていませんでした。私は、労働省で人事権を持っている官房長に、「開発途上国の仕事で、一番大切なことは、人的な信頼友好関係を作ること。日本が最も弱い点であると思います。偉くなることに関心はありませんので、私の人事はお忘れください」と直訴。そういうことも影響したのでしょう、在職30年中、15・6年を、ODAをはじめ国際協力の仕事に没頭させていただきました。
【How do you do の外交】当時の国際会議では、参加各国の人々は会議の前に意見交換し、落としどころも打ち合わせ、会議が始まると親しくファーストネームで呼び合って会議を進行させた中、日本からの出席者はそのときだけの参加で、手をあげ
ると「Japan」と呼ばれたという。
国連で、とことん人間同士のお付き合いをしよう
― 国際協力の次は、国連外交での活躍、そのはじまりは?
木全 1975年にメキシコで、国連主催の「第1回世界女性会議」が開催。それを契機に、世界各国の女性たちが、競って国際会議や外交の場に姿を現すようになりましたが、いつまでも暗い色のスーツ姿の男ばかりの日本は、野蛮国だと言われていました。そこで、目立つ外交の場、世界160か国が集まる国連外交の場に女性を…という発想から国連日本政府代表部の大使の次のポジションに女性を配属しようと、初代の女性公使に国際政治学者の緒形貞子さんが選ばれました。その4代目に労働省の海外協力課長の木全に…と、外務省から労働省に打診がありました。
その件で呼び出された時に、労働次官は、「ご主人の意見を聞いてくださいますか」と。男女同権を叫んでいる先輩たちだったら、どうして赴任する私に聞かないのですかと反論したでしょうけれど、その場はぐっと抑えて夫に伝えることにしました。帰宅した夫に事情を説明すると、ものの3秒で「素晴らしい、お受けしたら」と。同居中の義母、学生の息子からも背中を押されて、3年間の単身赴任を決意しました。
その件で呼び出された時に、労働次官は、「ご主人の意見を聞いてくださいますか」と。男女同権を叫んでいる先輩たちだったら、どうして赴任する私に聞かないのですかと反論したでしょうけれど、その場はぐっと抑えて夫に伝えることにしました。帰宅した夫に事情を説明すると、ものの3秒で「素晴らしい、お受けしたら」と。同居中の義母、学生の息子からも背中を押されて、3年間の単身赴任を決意しました。
― そして1986年に着任ですね。
木全 開発途上国に対する国際技術協力の仕事は、日本政府としても、自分自身としても素晴らしい仕事であったので、誇りと自信をもってニューヨーク(以下NY)入りしたのですが、その翌日から、日本と国交のある国連加盟国すべての国々を訪問し挨拶した中で、世界の各国、特にアジア諸国の外交官から受けた対応は予想外のものでした。「えっ、日本がアジアのリーダー国ですって?われわれアジア諸国は、誰もそんなことは思っていない。日本が一人うそぶいているだけですよ」。経済成長に酔いしれ、このホテルも明日は日本のものになっているんでしょうね…と。
― ジャパン・バッシングの頃ですね。
木全 「国際社会における日本人とは?」と真剣に考えました。この機会に、国連加盟国約150か国の外交官と、外交を語り合い、意見交換をし、とことん人間同士のお付き合いをし、見極めてみよう…と心に誓いました。
― 外交の仕事は、どのような?
 木全 国連外交は、別名「選挙外交」だといわれます。国連総会のもとに、「安全保障理事会」「経済社会理事会」、その下にさまざまな委員会があり、そこに所属しないと世界の情報も入手できないし、議論にも参加できません。即ち、国際社会に積極的に貢献できません。従って、日本はもとより各国は、委員会のメンバーになるために立候補をし、選挙戦で競い合います。
木全 国連外交は、別名「選挙外交」だといわれます。国連総会のもとに、「安全保障理事会」「経済社会理事会」、その下にさまざまな委員会があり、そこに所属しないと世界の情報も入手できないし、議論にも参加できません。即ち、国際社会に積極的に貢献できません。従って、日本はもとより各国は、委員会のメンバーになるために立候補をし、選挙戦で競い合います。
― 選挙権はどの国もあるのですか?
木全 米国も中国もアジアやアフリカの小国も同じ1票です。しかし、赴任前に、日本にとって重要なのは25か国の先進国OECDグループ。その次が40数か国のアジア。あとのアフリカやラテンアメリカは、ODAを上手に活用して。東欧諸国とは
距離を置くように…という外務省のオリエンテーションがありました。
― 外務省流というか男性社会ですね。木全さんが貫いてきたやり方とは、全く違います。
木全 私は、まず、アフリカ50か国を私の選挙区に。ラテンアメリカも東欧諸国もきちっと押さえ、その上に立って、アジア、OECD諸国を…と戦術を練っていきました。どんな国とも、交渉、意見交換する場合には、その国について、徹底的に研究、勉強し、呼びつけるのではなく、相手が求める場所に足を運びました。
私は、「私の外交」を展開しようと思いました。官僚として毎晩夜中に帰り、妻・母・嫁としての役割をこなしながらの1日では、自分の時間は45分位だったでしょうか。3年間1日も帰国できないなんてかわいそうね、と同情の声をかけていただきましたが、単身赴任ということは「24時間全部があなたの時間」と言われていることと同じ。なんてすばらしいことかと思いました。
私は、「私の外交」を展開しようと思いました。官僚として毎晩夜中に帰り、妻・母・嫁としての役割をこなしながらの1日では、自分の時間は45分位だったでしょうか。3年間1日も帰国できないなんてかわいそうね、と同情の声をかけていただきましたが、単身赴任ということは「24時間全部があなたの時間」と言われていることと同じ。なんてすばらしいことかと思いました。
― ポジティブに誠意を示す、まさに木全イズムの真骨頂。
木全 8時間は寝よう、8時間は外務省の訓令に従って真摯に外交に努め、あとの8時間は私の時間。この8時間×365日×3年間に、日本と外交関係のあるすべての国連加盟国に1~2名の親友を作ろうと思いました。選挙外交で激しく展開される Lunch外交、Dinner外交への対応はもとより、国連の会議場、Coffee Shop, 廊下、レストランなどでの時間をフルに活用して、意見交換をしました。週末、夏休み、年末年始の時間にも、ピクニックに誘われれば、日本のお弁当を友人の分も持参して日本の味をご紹介し、あらゆる機会を活用して友好親善関係の醸成に努めました。
― その成果はいかがでしたか?
木全 日本のような、本国の訓令を待って選挙に臨む先進国とは異なり、NYの各国代表部に委任されて投票に臨む国も多く、選挙当日、誰が投票の席に着くか、また、50か国のうち2か国が日本に投票しなかった場合にも、どこの国かが明確に見えていきました。
― 何気なくおっしゃるけれど、並大抵のエネルギーではないですね。
木全 普通は3年の勤務期間中に3回選挙を担当したらヘトヘトになると言われる中で、私自身の担当と他の方々の担当の選挙の応援を含めて、11回の選挙を体験することが出来たのは、非常に貴重な経験で感謝しています。
― それで11回の選挙にすべて当選!相手に合わせながら取り込んでいく賢さ、しなやかさは日本女性の代表ともいえます。
木全 私は福岡の出身で、「三歩下がって男の影を踏まず」という保守的な文化の中で育ちましたが、それが封建的だと批判するのではなく、そこから新しいリーダーシップを読み取り「三歩下がって、五歩前に行こう」を実践してきました。誰も傷つけない、しかし結果的にきちっと成果を生んでいけばと思うのですが…。
小売りの業界で社会変革活動を展開してみよう
― 官僚のあとは The Body Shop Japan の初代社長に。民間での経験はいかがでしたか?
木全 官僚は、45歳から50歳の間に現職を去るという傾向にありました。私が帰国したのは52歳の時。そのころ「21世紀は女性の時代」という言葉が飛び交い、キャリアを終えた女性を顧問に迎えて、アドバイザーとして採用するという会社がちらほらでてきました。私にもNY滞在中に、5つの会社からアプローチがありましたが、どの会社も「私に、何の役割を?」とうかがっても「お好きなように」という返事。しかも、どの会社の場合も、アプローチをされてこられたのはトップでは
なく、断られても傷つかない立場の方々でした。しかし、帰国後、労働省に戻り大臣官房審議官を拝命の折、1本の電話が。当時のジャスコの岡田卓也会長からでした。
― 幹部に女性が欲しいだけではない、熱い気持ちを感じますね。
木全 それが、私の心を動かしたひとつの要因でした。お目にかかると、岡田さんから、「The Body Shop の企業理念、創業者アニータ・ロディックの生きざま」等についてご説明があり、英国での新聞、雑誌などの切り抜きをドサッと渡されました。その後、その切り抜き記事を眺めていると「面白い、こんな企業が、こんな女性がこの地球上に存在するのだろうか」と気にかかり、全ての資料に目を通しました。
― 木全さんの志と合致したと。
木全 創業から13年、日本市場に全く関心を示していなかったアニータでしたが、アプローチのあった日本企業300社の中から4社を選び、各社のトップと面談するために来日しました。しかし、広告をうたない、包装紙も使わない、動物実験をしない、社会変革活動に積極的に取り組む等、十数項目もある企業理念の説明に、環境問題の「カの字」の意識もなかった当時の日本企業とは、入り口から話がかみ合いません。そこで、英国大使がジャスコの岡田さんを紹介。アニータの話に耳を傾けていた岡田さんは、「21世紀には、日本にもそのような企業が必要でしょう」と握手。「ただし、経営者は、所謂ルールを守り、前例を尊び、先輩を重んじる優秀とされる男にはできない、是非、女性を!」という要請を受けて、仮契約を交わしました。その流れの中で、私が、創業社長をお引き受けすることになったのです。
― お役所の反応はいかがでしたか?
木全 労働省で尊敬申し上げていた男性の先輩に話したら「君は、武士階層から、最下層階級の商人に落ちるのか」と言われました。更に、業種は化粧品・トイレタリーであることを説明すると、卑下したような反応、「日本中に星の数ほど店舗を作って、世界が直面している環境保護、人権擁護、動物愛護の問題について、スタッフ、お客様、そしてコミュニティの皆さんと一緒に社会変革活動を展開していきたい考えています」と説明すると、「とうとう木全は気が狂った」と(笑)。
― 最下層階級!そんな発想があったとは…。そして退任された翌日から仕事に打ち込まれ、1990年から10年の間に、お店を北海道から鹿児島まで広げました。
木全 130店のうち3、4店舗は直営。あとはフランチャイジーのお店(FC店)でしたが、「理念を理解し、賛同し、日々のビジネスの活動の中で、具体的な行動を通して理念を実現していくことのできる」FCさんを得ることは、決して生易し
いことではありませんでした。また、各地を訪問してスタッフと意見交換を繰り広げた「木全社長の全国ロードショウ」の思い出も忘れ得ないものです。素晴らしいFCさん、スタッフの皆さんに恵まれた10年であったと感謝いたしております。
日本の再生を願い、女性の活力を活かそう
― NPOを始められたのはなぜ?
木全 日本の高齢化社会を考えた時、60歳になったら、組織の長は次世代に譲っていかないと、この日本はジジババの社会になってしまいます。そうならないために、私は、結果的には63歳で辞めましたが、そのときに、「第一線を引いた男女は、社会との関わりのなかで、どのように生きていくべきか」と考えました。キャリアの時代に、男女同権の問題にタッチしたことがなかったので、私の友人の95%は男性。その人たちと、これからの日本について議論すると、「戦後のどん底の日本から、会社のため家族のために死に物狂いで働いてきて、世界第二の経済大国にまでしたのだから、もういいじゃないか」と。更には「アメリカの51州目になってもいいじゃないか」という発言を聞いた時、「こんな男性たちに、これからの日本を任せていいのだろうか」、男性に任せるのは、もうやめようと思いました。
― 「社会のために…」という人はいなかったと。
木全 その通り。それと同時に、人口の半分の女性たちはどうしてきたのかと、はじめて、女性について考えることを始めました。すると、日本の女性の高等教育進学率は世界一と言われているのに、卒業生の9割は、「高等教育で得たものを、生涯を通して社会にお返しし、貢献する」という国際社会の常識が、男にも女にもなく、自分の豊かな暮らしだけに満足していることに驚きました。
― 女性の在り方に危機感を覚えた。
木全 そこで、同じ問題意識を持つ男女22名が集まり、ブレーンストーミングと勉強会を行い「女性という人財を活用してこなかった、勿体ない日本の歴史にピリオドを打とう」という趣旨のもとに「NPO法人女子教育奨励会(※3)」を発足させ、活動を始めました。
【NPO法人女子教育奨励会】女子教育奨励会は、1886年、国の近代化への切なる願いの中で「日本婦人の国際化と社会参加」を目的に掲げ、伊藤博文、大隈重信、勝海舟、澁澤栄一など、時の指導者により設立された団体。その後国家主義への偏向が進み、願い半ばにして実ることなく100余年を経過。2002年に「21世紀版女子教育奨励会」として発足。現在の「認定NPO法人JKSK女性の活力を社会の活力に」として、21世紀の要望に応えて、日本全国各地で、同じ問題意識をもつ女性たちがリーダーシップを発揮し、日本再生の原動力になるための諸活動を展開する。
― その一方で、日本は、世界経済フォーラムの Gender Gap 指数が144か国中114位(2017年) と悪化しています。それをどう思われますか?
木全 先進国のなかで最低、多くの開発途上国と比べても悲惨なこの日本の実態、現状を政府関係者は、政治家は、企業経営者は、労働組合は、男性は、女性は、どのように認識しているのでしょうか?
気にしないという人が非常に多くおられますが、それを実感する機会、経験がないからではないでしょうか。年間2,000万人の日本人が海外に出かけています。外交、国際会議、商談、観光など、その目的はさまざまですが、多くの日本人は、その目的を達成する事だけに没頭し、訪問先、訪問国について関心を持ち、友人を作り世界に共通する課題について意見交換をするということをしません。従って、この日本における Gender Equality Ranking の現状について各国の意見に触れることもないのではないでしょうか。
かつて海外のジャーナリストから、日本の女性たちは、海外旅行を大いに楽しみ、ファッション・グルメには熱心だが、世界やアジア、更に日本社会の問題に関して意見交換を求めても、意見を持たない。要するに、日本の女性は「頭が空っぽなのよ」と言われたことがあります。このような国際社会の認識をどう思われますか。
健全でサステナブルな社会の維持・発展は、社会に存在するすべての能力を最大限に発揮、活用して、実現されるもの。世界は、大きく流動しています。日本の存続をかけて、多様な課題に真剣に取り組んでいかなければならないとき、男性だけに任せるのではなく、聡明な判断力、企画力、行動力、バランス感覚を持ち合わせている女性が、一緒になって対峙することが必須であると思います。更に、女性の問題というより、それ以上に、社会のリーダーをはじめ政治家、企業経営者である男性の、この問題に関する認識を徹底的に改めて行かねばならないのではないでしょうか。
気にしないという人が非常に多くおられますが、それを実感する機会、経験がないからではないでしょうか。年間2,000万人の日本人が海外に出かけています。外交、国際会議、商談、観光など、その目的はさまざまですが、多くの日本人は、その目的を達成する事だけに没頭し、訪問先、訪問国について関心を持ち、友人を作り世界に共通する課題について意見交換をするということをしません。従って、この日本における Gender Equality Ranking の現状について各国の意見に触れることもないのではないでしょうか。
かつて海外のジャーナリストから、日本の女性たちは、海外旅行を大いに楽しみ、ファッション・グルメには熱心だが、世界やアジア、更に日本社会の問題に関して意見交換を求めても、意見を持たない。要するに、日本の女性は「頭が空っぽなのよ」と言われたことがあります。このような国際社会の認識をどう思われますか。
健全でサステナブルな社会の維持・発展は、社会に存在するすべての能力を最大限に発揮、活用して、実現されるもの。世界は、大きく流動しています。日本の存続をかけて、多様な課題に真剣に取り組んでいかなければならないとき、男性だけに任せるのではなく、聡明な判断力、企画力、行動力、バランス感覚を持ち合わせている女性が、一緒になって対峙することが必須であると思います。更に、女性の問題というより、それ以上に、社会のリーダーをはじめ政治家、企業経営者である男性の、この問題に関する認識を徹底的に改めて行かねばならないのではないでしょうか。
― 改めて背筋が伸びました。これからも女性の活力を活かすために、ますます問題提起していただきたいと思います。人生100年時代です。今後の木全イズムの発露を期待しています。きょうは、ありがとうございました。
【インタビュー】
公益社団法人日本フィランソロピー協会
理事長 高橋陽子
(2017年12月20日 当協会会議室にて)
公益社団法人日本フィランソロピー協会
理事長 高橋陽子
木全ミツ様は、2021年12月16日に亡くなられました。
フィランソロピー推進の真髄を体現し、評議員・理事・顧問として長年にわたって当協会の組織運営をご指導くださった偉大で大切な師を失い、悲痛な思いです。心からの感謝とともにご冥福をお祈り申し上げます。
フィランソロピー推進の真髄を体現し、評議員・理事・顧問として長年にわたって当協会の組織運営をご指導くださった偉大で大切な師を失い、悲痛な思いです。心からの感謝とともにご冥福をお祈り申し上げます。
2021年12月
機関誌『フィランソロピー』No.384/2018年2月号 巻頭インタビュー おわり