Date of Issue:2018.8.1
<プロフィール>

1962年、石川県輪島市出身。1985年筑波大学芸術専門学群生産デザインコース卒。コクヨ株式会社を経て1987年桐本木工所入社。2015年家督を引継ぎ、商号を輪島キリモトとして代表に就任。木地の職人だけでなく、漆塗りを専門に手がける職人も加わり、産地内の創り手たちとの交流、都市部で暮らしを愉しむデザイナーとの取り組みなど、さまざまな可能性に挑戦している。
URL:http://www.kirimoto.net
◆ 特別インタビュー No.387
世の中に必要とされているか ~伝統をつなぐ革新への挑戦~
輪島キリモト
桐本 泰一 氏
9000年前の縄文時代から、日本の漆は、装身具や食器、調度品に利用され、日本文化の深層に関わる塗料だった。輪島塗は中世後期に生まれ、現在にいたるその集積から、1977年、全国の漆器産地で最初に重要無形文化財に指定された。その産地で、本来の漆の良さを再確認し、従来の高級漆器としてだけでなく、今の暮らしに親しみのある輪島塗を広めようと挑戦し続ける「輪島キリモト」の桐本泰一さん。輪島工房に、桐本さんを訪ねた
変革に挑む桐本家の家系
― 桐本さんは、輪島塗の木地屋として3代目。遡れば、江戸時代の1700年後半に創業した輪島塗を製造販売する漆器屋から7代目に当たるとか。輪島塗は、塗師屋(ぬしや)さんが注文を取り仕切り、各工程が分業※されて製品がつくられるそうですね。
【分業】「木地 」「下地」「上塗」「研ぎ」「蒔絵」「沈金」など細かく分業され、専門の職人がかかわる。
桐本 桐本家は、輪島漆器業界の木地業4業種(椀木地、曲げ物、指物、朴木地(ほうきじ))の中で、主に 朴(ホオ)の木 から形を刳りだすことを得意とする朴木地屋(ほうきじや)として約90年。これは、桐本家5代目の祖父が塗師屋から朴木地屋に転業したからですが、200年以上、木と漆の仕事に携わった「形」を生み出す創作意欲のある家系です。7代目の私は、市外では面白いと言っていただくのですが、地元では「変わったやつ」と言われます。塗師屋から木地屋、そして今は一貫生産、そうした血統のあることが、輪島市史からわかりました。
― 輪島の歴史から見ても代々「変わったやつ」ですか(笑)。
桐本 3代目の久太郎は、漆器屋の傍ら、明治の半ばに輪島漆器業界の漆工労組(小さな塗師屋と職人の労働組合)の組合長に選出されて、職人総代として賃上の嘆願書を出しています。しかし、願いがかなうことなく、その団体から推挙されて町議会議員選挙に打って出たようで、現状に満足することなく、変えようと闘ったことが残されています。
― 職人のための賃金抗争、熱い血を感じますね。
桐本 ところが選挙に落ちて、一気に家が傾いてしまったようです。その貧しさのなかで、5代目・私の祖父は、当時仕事の多かった朴木地屋に弟子入りし、若くして独立を許され、朝市通りに木工所を構えました。私の父は、成績もよく早稲田大学に入りたかったようですが、進学資金がなく、厳しい祖父に従い朴木地屋を継いで、特殊木地や家具も手掛ける設備を整えました。
― 桐本さんは、筑波大学へ進学されましたが、小さい頃からご家族の背中を見て、自然と漆の仕事を継ごうと思われたのですか?
桐本 輪島という町が非常に好きで、地元で作る漆器は気持ちがいいと思っていました。中学生のときにはモノを作りだすことが得意で、美術系の大学に行こうと考えていました。高校1年になると陸上部に所属する傍ら、毎週日曜日に、片道3時間以上かけて金沢の画塾に通い、筑波大学芸術専門学群生産デザインコースに入りました。
― 大学で工業デザインを学ばれて、いかがでしたか?
桐本 最初のデザイン概論の授業内容が心に刻まれました。
「これから習うデザインとは、今の暮らしのなかで、ほっとする瞬間を生み出すもの、気持ちのいいもの、便利なものは何かと、世の中に貢献することを考える学問だ」と言われ、きれいな色、かっこいい形というのはデザインの狭義の意味だと言われました。
「これから習うデザインとは、今の暮らしのなかで、ほっとする瞬間を生み出すもの、気持ちのいいもの、便利なものは何かと、世の中に貢献することを考える学問だ」と言われ、きれいな色、かっこいい形というのはデザインの狭義の意味だと言われました。
― ほっとして、気持ちよく、便利なもの。高級漆器とは、ちょっと違います。
桐本 高校生くらいから、今の自分は何を必要とされているかという「自分の立ち位置」を常に考えていましたから、「よっしゃ、目指す先が決まった」と思いました。これから学ぶデザインの考え方を伝統工芸に絡めていけば、今の暮らしのなかに漆を活かすことができ、新たな革新につながるんじゃないかと感じて、4年間やってきました
― でも、卒業後は企業に就職されたのですね。
桐本 いろいろな経験を積み重ね、人の釜の飯も食わないといけないと考えて、コクヨ株式会社に入社。大阪駅近くの32階建てインテリジェントビルの設計サポートに携わりました。
「従来の真っ白な壁、軽鉄構造に鉄とボードをはりつけた無機質な空間で、いい議論ができるだろうか。温かい質感がある漆の空間なら、どんなにほっとするだろう」とか「建築内装に本物の漆を入れ込むことで、気持ちよい空間になるのではないか」とか、そんなことばかり考えていました。
「従来の真っ白な壁、軽鉄構造に鉄とボードをはりつけた無機質な空間で、いい議論ができるだろうか。温かい質感がある漆の空間なら、どんなにほっとするだろう」とか「建築内装に本物の漆を入れ込むことで、気持ちよい空間になるのではないか」とか、そんなことばかり考えていました。
― それが漆の家具や建築内装の提案、創作につながっていきます。
分業・受注システムを超えて一貫生産に挑戦
― 輪島に戻られてからは、どうなさったのですか?

輪島工房での様子
その中で、「なぜ、この形が売れるのだろう。少し、遠近感がずれている…。なにか、おかしい」と感じていました。バランスがずれている蒔絵から、座卓をはじめ、茶道具など、これを使う人が世の中にどれほどいるのかと思うものまで、「輪島塗」という名称だけで売れました。
― 高度成長期の高級イメージのままに、モノが売れてしまったのですね。
桐本 一方で、世の中の景気が悪くなったころから、設計事務所やデザイナーなど、産地にいる人と違う人たちが、輪島から産みだす本当に良いモノをデザインしたいと来るようになりました。しかし、輪島塗を理解していない人の書いた図面なので、そのままでは使えません。例えば、輪島塗の家具は塗り厚が約1ミリ付くので、木地作りには再調整が必要です。わたしはクリエイターと職人の間に立ち、コーディネートを始めました。
― デザイナーの言語と職人の言語を翻訳できる人が、桐本さんだった!
桐本 特殊なものを求められ、うちでは新しい木地提案を始めました。図面を提案するとほぼ100パーセント決まり、この頃はまだ大きく売り上げが落ちることはありませんでした。それで1991年、結婚したばかりでしたが、イタリアの伝統工芸を巡る3週間のツアーがあったので、世界を見るチャンスだと、新妻を置いて参加しました。
― お一人で、ですか(笑)。
桐本 20人ほどのツアーで、イタリアの工房では、職人自身が堂々と人前で語ることに感激しましたが、一方で「日本のモノづくりのほうが質は高い。うちの工場の家具なら、もっと緻密なものができる」と思ったのです。
― ヨーロッパで技術を誇るイタリアで、日本の技術の高さを再認識したのですね。
桐本 輪島に戻ると、ツアー仲間で、さっそく伝統工芸の展示会をやることになりました。ところが、うちは木地屋ですから、下請けばかりで出展するものがない。自分で書いた家具の図面があったので、初めて完成させた家具の木地に、漆を塗り完成させて、展示会に出しました。
新作の座卓が2台売れて嬉しかったですね。大学1年で思ったこと、会社の設計サポートで思ったことが結実しました。
新作の座卓が2台売れて嬉しかったですね。大学1年で思ったこと、会社の設計サポートで思ったことが結実しました。
― 問屋の受注システムを超えて、自分自身のモノづくりで販売もする一括生産に挑戦したのですね。
桐本 生業の木地屋の傍ら、自分の商品の販路は、人と会い百貨店やギャラリーを紹介していただいて、広げていきました。
苦難のとき、そして再び打ってでる
― 地域での継承者を育てる勉強会も、そのころからですか?
桐本 1995年から輪島漆器商工業協同組合の勉強会で、コーディネーターをやりました。そこで、大学や会社で学んだことを伝え、モノを作るときのデザインの流れを徹底的に知っていただきました。
― 輪島塗は、伝統的なシステムを堅持してきたと聞きます。反対する人もいたのでは?
桐本 1999年に、勉強会は理事長の交代とともに打ち切られました。その理由は、「輪島で先人たちが培ってきたことと、君たちのいう『デザイン』という考え方は相入れない」ということでした。さらに「モノづくりを冒涜している」とまで。これには、正直参りました
― いい流れができそうだったのに、残念です。その後は?
桐本 2000年、新たに「ギャラリー・わいち」を始めました。輪島の一番になろうと命名した、わいち商店街の理事長さんに声を掛けていただき、面白いことをやりたいと思う輪島市内の創り手さんや、デザイナー9人で運営を始めました。
― 応援してくださる方もいます。信条を曲げずに伝えることは、大事ですね。
桐本 そこで並べる商品には、各々創り手の名前を入れました。全国のアーティストや伝統工芸を支える創り手たちの企画展をやり、輪島の創り手や学ぶ若手と交流できる場を設けました。しかし、そこでまた壁にぶつかりました。商品を一括生産したことで、「木地屋なのに、変わったことをしている」と言われはじめ、そのうちに、生業の木地の注文が減ってきたのです。
バブルのころを100とすると、木地の売上で45減らしました。3人目の子どもが生まれたばかり、祖母が認知症になり家族も大変でしたから、新しいことをやったことでダメになるのかと思うと、情けなかったですね。
バブルのころを100とすると、木地の売上で45減らしました。3人目の子どもが生まれたばかり、祖母が認知症になり家族も大変でしたから、新しいことをやったことでダメになるのかと思うと、情けなかったですね。
 ― 輪島塗が売れない時代に入り、反感をかってしまったのですね。体も壊されたとか?
― 輪島塗が売れない時代に入り、反感をかってしまったのですね。体も壊されたとか?
桐本 ストレスと酒で壊しました。でも、いいこともありまして、痩せたことですね(笑)。
― ご家族も大変だったでしょう。でも、桐本さんの目標に理解があったのですね。
桐本 これは負けていられないと。
― 桐本家の血が蘇りました(笑)。
桐本 またどんどん市外に打ってでて、いまに至っています。
先ほどから入ってくる電話は、百貨店や飲食店、ギャラリーをやっている人たちからです。できるだけいろいろな人たちとともに、新しい取り組みをするべきだと思って、能登半島地震ではルイ・ヴィトンとのチャリティイベントを推進したり、『いつものうるし』という本を出版したり、様々な挑戦を手掛けてきました。
先ほどから入ってくる電話は、百貨店や飲食店、ギャラリーをやっている人たちからです。できるだけいろいろな人たちとともに、新しい取り組みをするべきだと思って、能登半島地震ではルイ・ヴィトンとのチャリティイベントを推進したり、『いつものうるし』という本を出版したり、様々な挑戦を手掛けてきました。
― 新しい商品、イベントや販路だけでなく、同時に、新しい技術にも取り組まれています。
そのひとつ蒔地技法※(まきじぎほう) は、2015年放送のNHKの朝ドラ「まれ」に取り上げられ、全国に紹介されました。傷がつきにくく、使いやすい漆塗りを目指した輪島キリモト独自の技法ですが、産地での反応はいかがでしたか?
そのひとつ蒔地技法※(まきじぎほう) は、2015年放送のNHKの朝ドラ「まれ」に取り上げられ、全国に紹介されました。傷がつきにくく、使いやすい漆塗りを目指した輪島キリモト独自の技法ですが、産地での反応はいかがでしたか?
【蒔地技法】これまでの下地の蒔地技法を応用し、下地を施した後、表面に近い部分でもう一度「輪島地の粉」を使用し、漆を塗り重ねて仕上げる。金属のスプーンなどを使っても傷がつきにくくい。詳しくは、輪島キリモトのウェブサイト をご参照ください。

革新から生まれる伝統、若い力への期待
― さまざまなご苦労もありながら、漆を現代の暮らしのなかで親しみあるものにしたいと尽力されています。今の伝統工芸における課題は、なんだとお考えですか?
桐本 よく言われていることですが、伝統は、常に今の時代に合わせたものを改良していくことで伝統になる。同じことを受け継ぐだけならば、単なる伝承です。
伝統工芸では、お客さんが見えなくなったことがあると思います。高度成長期に運送が発達し販路が拡大しました。日本独特の問屋システムのなかで、創り手は前面にでることがなくても、バブル経済で伝統工芸が売れてしまった。そのとき、なぜ売れるのかと考えることもなく、その後売れなくなったときにも、なにもしなかったことで、行く末が見えなくなったのではないかと思います。
伝統工芸では、お客さんが見えなくなったことがあると思います。高度成長期に運送が発達し販路が拡大しました。日本独特の問屋システムのなかで、創り手は前面にでることがなくても、バブル経済で伝統工芸が売れてしまった。そのとき、なぜ売れるのかと考えることもなく、その後売れなくなったときにも、なにもしなかったことで、行く末が見えなくなったのではないかと思います。
― それで、桐本さんは売り場に立つことにこだわっておられる?
桐本 お客さんの声が聴ける場所に出て、自分の立ち位置はどうかと、しっかり把握するためです。先人たちの努力で売れたのだから、輪島塗は悪いものではありません。今一度、売り方を考え直してみる。特性をしっかり説明したか、修理のこと、洗い方について伝えたかと反省して、はじめからやるべきだと思っています。販売し、反省し、それを反映することで、新しいものが生まれます。
「輪島キリモト」もまだまだ大変な状況ですが、いつも自分の立ち位置を考えていれば、手ごたえがあり、可能性があると感じます。しかし、「輪島キリモト」だけでは限りがあります。連携できる異業種の伝統工芸の人と交流し、情報交換して一緒にやる。いい意味での戦いができる人たちと連携したいですね。
「輪島キリモト」もまだまだ大変な状況ですが、いつも自分の立ち位置を考えていれば、手ごたえがあり、可能性があると感じます。しかし、「輪島キリモト」だけでは限りがあります。連携できる異業種の伝統工芸の人と交流し、情報交換して一緒にやる。いい意味での戦いができる人たちと連携したいですね。
― 同業は難しいですか?
桐本 それに越したことはありませんが、なかなか手のうちを明かさないところがありますね。
― 若い人たちはどうですか?
桐本 輪島キリモトには、他の工房から移ってきた職人もいます。彼らは、建築内装の仕事ができます。また、契約している30代から40代の若いデザイナーは、今の暮らしの中で気持ちいいものを、どうやって産地の人間と一緒につくりだすかを考えていて、販売ルートも親身になって考えてくれます。
漆には、明らかにほかの素材とは違う質感があります。空間でも器でも、心豊かで温かい気持ちになれます。本物の漆を、これまでの伝統ではなく、革新を生む新しい素材として、日本のモノづくりがいいと感じる若い人たちに訴えていく。そうすれば、伝統工芸に新しい領域が生まれ、人を引き寄せ、爆発的には売れはなくても、継続していくだろうと思っています。
漆には、明らかにほかの素材とは違う質感があります。空間でも器でも、心豊かで温かい気持ちになれます。本物の漆を、これまでの伝統ではなく、革新を生む新しい素材として、日本のモノづくりがいいと感じる若い人たちに訴えていく。そうすれば、伝統工芸に新しい領域が生まれ、人を引き寄せ、爆発的には売れはなくても、継続していくだろうと思っています。

桐本 去年から勉強会を再開しました。輪島漆再生プロジェクト委員会という組織で、輪島で採った漆で商品をつくる「輪島クリエイティブデザイン塾」を始めました。漆芸研修所で学ぶ人たち、新しいものを考えたい創り手さん、グラフィックデザイナー、町の動きに興味のある人たちなどが20人ほど。商品をつくって販売につなげることと、交流を目的にしています。漆は楽しくて面白い、可能性があると思う仲間をつくります。
― 心強い息子さんもいらっしゃいますね。
桐本 彼なりに「漆っていいと思う」といっていて、文部科学省のトビタテ留学JAPAN制度を使い、パリで日本の伝統工芸を扱うショップで、マネージャーを経験しました。そこでは輪島キリモトの商品も扱い、定点でお客様に説明し販売できたことで、輪島塗への信頼にもつながりました。
― 若くして世界も見て、多様な価値観との対話や葛藤から、新しい感性が輪島塗に反映されそうですね
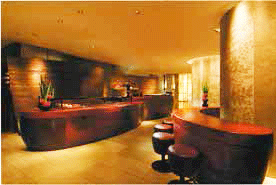
― スプーンでカリカリしても大丈夫、中性洗剤で洗える蒔地技法の器は、ざらっとしながら深みのある質感。使い続けると光沢がでて独特の風合いになりますね。
桐本さんの伝統をつなぐ革新、新しい輪島塗の展開に、心よりエールを送ります。そして、わたしたち消費者も伝統工芸を身近に感じて愛用し、新たな需要を作りださないといけないですね。きょうはありがとうございました。
桐本さんの伝統をつなぐ革新、新しい輪島塗の展開に、心よりエールを送ります。そして、わたしたち消費者も伝統工芸を身近に感じて愛用し、新たな需要を作りださないといけないですね。きょうはありがとうございました。
※桐本さんは、産地の活性化と改革に取り組んだことで、2018年「三井ゴールデン匠賞」グランプリを受賞されました。
【インタビュー】
公益社団法人日本フィランソロピー協会
(2018年6月25日 輪島工房にて)
公益社団法人日本フィランソロピー協会
(2018年6月25日 輪島工房にて)
機関誌『フィランソロピー』No.387/2018年8月号 特別インタビュー おわり

