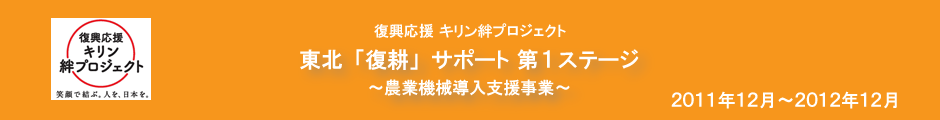
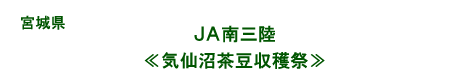
日時: 平成24年(2012年)9月8日(土)■11:00~13:00
場所: JA南三陸 階上大谷地区ライスセンター
場所: JA南三陸 階上大谷地区ライスセンター

(1)収穫作業の紹介
最初に、会場前の茶豆圃場にて、収穫作業の紹介が行われました。
佐藤美千夫 様
階上生産組合(茶豆生産農家代表)
 今年は猛暑が厳しく、茶豆の成長が芳しくありませんでした。しかし収穫前に雨が3日ほど降ったおかげで、どうにか収穫祭に間に合わせることができました。
今年は猛暑が厳しく、茶豆の成長が芳しくありませんでした。しかし収穫前に雨が3日ほど降ったおかげで、どうにか収穫祭に間に合わせることができました。気仙沼茶豆は寒暖の差が大きくなると、豆がよりいっそう甘くなります。収穫適期は朝夕の気温が下がり、涼しさを感じられるようになる9月中旬頃。本日は収穫祭に合わせ、少し早めに収穫したものを召し上がっていただきます。でも、もう少し経ってから収穫した茶豆は、もっと風味が増すはずですので、ぜひ改めて味わっていただきたいですね。

(2)出荷調整作業の紹介
次に、寄贈された農機具を使用して収穫した茶豆を、箱詰めするまでの作業を見学しました。
尾形 政司 様
JA南三陸 常務理事
 私どもが流失した農機具はコンバイン2台、乾燥機5台、トラクター3台、枝豆ハーベスター2台。しかし今回キリンビール様より、枝豆ハーベスター3台、枝豆選別機1台、枝豆洗浄器1台をご支援いただき、大変助かりました。使い心地は非常に良いですよ。
私どもが流失した農機具はコンバイン2台、乾燥機5台、トラクター3台、枝豆ハーベスター2台。しかし今回キリンビール様より、枝豆ハーベスター3台、枝豆選別機1台、枝豆洗浄器1台をご支援いただき、大変助かりました。使い心地は非常に良いですよ。収穫作業の手順ですが、まずは枝豆ハーベスターで刈り取り、茎からさやの部分を切り離します。作業スピードは3時間で10a程度。1日で収穫できるのはだいたい15a~20a分です。相応に時間はかかりますが、これ1台でさやの切り離しまで行えるため、作業効率は良いです。
次に枝豆選別機を使用しながら、手作業で残った茎や葉、豆の入っていないさやなどを取り去ります。その後、枝豆洗浄器で15分間ほど豆を洗い、脱水機で水を切った後、箱に詰めて完了です。
「気仙沼茶豆」は、冷凍せず全て生で出荷しています。そのため収穫は雨が降っても風が吹いても10日間できっかり終わらせ、すぐに出荷する必要があります。しかしその甲斐あってか、近頃は美味しいと評判で、ずいぶん引き合いが増えているんですよ。北は北海道、南は大阪まで出荷しています。


その後、9月6日に完成したばかりの「階上大谷地区ライスセンター」にて、式典が行われました。


(3)開会
(4)主催者挨拶
高橋 正 様
南三陸農業協同組合 代表理事組合長
 農業施設が甚大な被害を受けた中、この建物も9月6日に落成式を行ったばかりです。「農業復興の際はこの施設が必要だ」と各所からいただく言葉に勇気付けられながら、復興を誓い建設をいたしました。このほかの農業施設も素晴らしいスピードで復旧が進んでおり、着々と復興へ向け環境が整ってきたところです。
農業施設が甚大な被害を受けた中、この建物も9月6日に落成式を行ったばかりです。「農業復興の際はこの施設が必要だ」と各所からいただく言葉に勇気付けられながら、復興を誓い建設をいたしました。このほかの農業施設も素晴らしいスピードで復旧が進んでおり、着々と復興へ向け環境が整ってきたところです。震災前の南三陸町は農業振興計画の最中にあり、半農半漁の中山間地帯でありますが、地域の皆さまと共に、小さくてもきらりと光る地域づくりを実践してきました。地産地消を掲げ、海の幸・山の幸、そして観光資源と連動させつつ、三陸の素晴らしい景観を生かした地域ブランド品作りを目標としてきました。
地元の方が大切に守り育ててきた、“葉が5枚”という特徴の枝豆を「気仙沼茶豆」としてブランド化。また南三陸で春に収穫する各種の葉野菜を「南三陸 春告げ野菜」として打ち出し、県内外に浸透させてきました。震災に見舞われたのは、こうした農業振興が「いざ本番」という時期だったのです。
一瞬のうちに全財産を流失し、優秀な生産者も犠牲となり、私たちは苦しみと悲しみの中にありました。しかし「1人でも2人でもいい。一日も早く生産を再開すべき」と考え、勇気を出して話し合いを持ったところ、生産者のリーダーの皆さんから「ぜひ我々が復興する。組合長、応援してほしい」という力強い言葉をいただきました。そしてようやく本日の収穫祭が実現させることができたのです。皆さまに心より感謝を申し上げたいと思います。
今回の「キリン絆プロジェクト」では全農様を通じ、キリンビール様より農機のご支援を、また本日の収穫祭においても「キリンビールで“乾杯”を」とのご好意をいただきました。心より御礼を申し上げます。
松本 克彦
キリンビールマーケティング株式会社
東北統括本部 宮城支社長
数日前には茶豆の生育に大切な雨が降り、そして本日の収穫祭では素晴らしい天候に恵まれ、皆さまの熱意が天に届いたのだなと感じております。東北統括本部 宮城支社長
さてキリングループでは、復興支援策といたしまして 「復興応援 キリン絆プロジェクト」 を立ち上げました。食に携わる企業として、また、宮城県仙台市でビールを作る企業として、どうにかお力添えができないかと考え、地域ブランドの活性化、そして販路の拡大に向けご協力をさせていただく次第でございます。生産面では農業機械の支援を、また営農面では、JAの皆さまのご協力を仰ぎつつさまざまな復興支援をさせていただいております。「気仙沼茶豆」につきましては、グループ会社のレストラン「キリンシティ」全国38店舗と、仙台工場内にある「キリンビアポート仙台」で、9月10日から2週間にわたりまして、「復興応援・気仙沼茶豆」と銘打ち、気仙沼茶豆をお客様にご提供していきたいと思っております。
お聞きしましたところ、この時期枝豆を作っている農家は全国でも少ないそうです。そうした希少な地域ブランドの販路拡大にお力添えができることを、私たちも大変うれしく思っております。
最後にビールと茶豆の相性は非常に素晴らしく、何より美味しい組み合わせであると思います。そして、特にビールは“上を向いて笑顔で楽しむ”お酒です。ぜひキリンビールを片手に気仙沼茶豆をつまみ、復興へ向けて頑張っていきましょう。
(5)来賓挨拶
大江 真弘 様
気仙沼市副市長
 私は京都府の丹後半島というところの出身でございまして、気仙沼と同様、海と山の広がる環境で育ちました。農業従事者の減少や高齢化という悩みを持つことに関しても同様です。
私は京都府の丹後半島というところの出身でございまして、気仙沼と同様、海と山の広がる環境で育ちました。農業従事者の減少や高齢化という悩みを持つことに関しても同様です。しかしながら、気仙沼の皆さまはこうした問題にさまざまな取り組みでもって、町を、そして生産を盛り上げていこうと、多くの方が努力されている状況にあるかと思います。気仙沼茶豆に関しましても、皆さまの努力がこうして実を結び、私どもはむしろ「ありがとうございます」とお礼を申し上げる立場で出席をさせていただいております。これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。
本日市長があいにく欠席のため、祝辞を預かってまいりました。ここで読ませていただきたいと思います。
気仙沼茶豆収穫祭にあたりまして、ひと言御礼を申し上げます。まず、過日の東日本大震災で被災されました農家の皆さま方に対しまして、お見舞いを申し上げます。
本日の収穫祭を開催するにあたりまして、この階上大谷地区穀物乾燥調整施設をはじめ、東日本大震災で被災をいたしました農業施設、機械の復旧などにご尽力を賜りました南三陸農業共同組合の組合長様をはじめ、役職員の皆さまへ心より敬意を表しますとともに、お集まりの皆さまには農地農業の振興に格別なるご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
また生産者の皆さま方におかれましては、自宅あるいは農地農機具に甚大な被害を受けながらも、ここまで生産施設を復旧するまでに、大変ご苦労があったことと拝察をし、あらためてそのご努力に敬意を表するものであります。
また本日、全農様、あるいはキリンビールの皆さまにも、この場にお集まりをいただき、これまでのご尽力に対しましても改めて敬意を表します。
この震災においても途切れることなく、復興のシンボルとして地域ブランドである気仙沼茶豆生産に取り組み、本日の収穫祭を迎えたことは、大変意義深いことであると考えております。「本日をもって復旧完了」となる日はまだ先になるとは思いますが、本市としましても関係機関と連携を取り、着実に作業を進め、一日も早い復旧を目指していく所存でありますので、今後ともなお一層のご支援とご協力を賜りますことをよろしくお願い申し上げます。
また住まいの復興につきましても、現在皆さまのご協力をいただきながら、集団防災移転やその他の住宅手配についても進めているところでございますので、この点につきましてもご支援ご協力をいただきますよう、お願い申し上げます。
気仙沼茶豆が今年も全国の多くの人に愛され、気仙沼ブランドとして一層評価が高まりますよう期待をし、また皆さま方のご発展とご健勝を祈念いたしまして、お祝いの言葉と代えさせていただきます。
本日の収穫祭を開催するにあたりまして、この階上大谷地区穀物乾燥調整施設をはじめ、東日本大震災で被災をいたしました農業施設、機械の復旧などにご尽力を賜りました南三陸農業共同組合の組合長様をはじめ、役職員の皆さまへ心より敬意を表しますとともに、お集まりの皆さまには農地農業の振興に格別なるご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
また生産者の皆さま方におかれましては、自宅あるいは農地農機具に甚大な被害を受けながらも、ここまで生産施設を復旧するまでに、大変ご苦労があったことと拝察をし、あらためてそのご努力に敬意を表するものであります。
また本日、全農様、あるいはキリンビールの皆さまにも、この場にお集まりをいただき、これまでのご尽力に対しましても改めて敬意を表します。
この震災においても途切れることなく、復興のシンボルとして地域ブランドである気仙沼茶豆生産に取り組み、本日の収穫祭を迎えたことは、大変意義深いことであると考えております。「本日をもって復旧完了」となる日はまだ先になるとは思いますが、本市としましても関係機関と連携を取り、着実に作業を進め、一日も早い復旧を目指していく所存でありますので、今後ともなお一層のご支援とご協力を賜りますことをよろしくお願い申し上げます。
また住まいの復興につきましても、現在皆さまのご協力をいただきながら、集団防災移転やその他の住宅手配についても進めているところでございますので、この点につきましてもご支援ご協力をいただきますよう、お願い申し上げます。
気仙沼茶豆が今年も全国の多くの人に愛され、気仙沼ブランドとして一層評価が高まりますよう期待をし、また皆さま方のご発展とご健勝を祈念いたしまして、お祝いの言葉と代えさせていただきます。
気仙沼市長 菅原 茂
(6)協力団体挨拶
千葉 和典 様
全国農業協同組合連合会 宮城県本部長
 本日は、気仙沼茶豆収穫祭がこのように盛大に開催されましたことに、お祝いを申し上げます。
本日は、気仙沼茶豆収穫祭がこのように盛大に開催されましたことに、お祝いを申し上げます。そして生産者、JA様、そして地元業者が連携をして復興へ向け取り組んでおられる姿に、敬意を表したいと思います。
キリンビール様より「東北『復耕』サポート」と銘打った農業機械の支援、そしてキリングループ店舗での生産物の販売、さらにはそのブランド化へ向けての事業支援という形で、現場を中心としたご支援をいただいたことに心からの感謝と、ご尽力に対しての敬意を表したいと思います。農機具の支援に関しましては、できるだけ多くの被災者に届けたいということから、全国から希望する農機具の募集をかけ、全国のJAの協力の下、宮城・岩手・福島に農機具を集め、キリンビール様からのご支援と引き換えてお届けするとことができました。また、JA南三陸には津波に浸かった「枝豆ハーベスター」、また茶豆販売へのご助力をいただき、現場にとって本当にありがたい支援になったと思います。
私どもはこの「キリン絆プロジェクト」の取り組みを復興のシンボルの一つと位置づけております。仙南の亘理エリアで栽培しております「仙台いちご」の復興プロジェクト、そして伝統野菜である「仙台白菜」の復興プロジェクトなど、できる限り生産者が元気になるような動きに取り組んでいく所存です。あわせて被災した生産者を主体とした復興事業を、影ながら応援させていただきたいと思います。
(7)初出荷セレモニー
関係各位によるテープカットの後、気仙沼茶豆の箱を積み込んだトラックが旅立ちました。


(8)気仙沼茶豆試食会
冷たいキリンビールを片手に乾杯のコールを行った後、参加者らは笑顔で新鮮な気仙沼茶豆に舌鼓を打ちました。
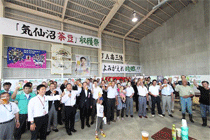

(9)復興へのエール交換
今回の収穫祭の後援である いたがき 取締役本部長・氏家智夫様、茶豆生産農家代表として階上生産組合・佐藤美千夫様、本吉農業改良普及センター・末長重男様より、それぞれエールの交換がありました。



(10)閉会挨拶
尾形 政司 様
JA南三陸 常務理事
 実は本日の収穫祭を控え、私どもには一抹の不安がありました。豆が大きくならないのです。今夏の雨不足には非常に悩まされまして、直前まで「延期か中止か」という話が出ていたほどです。しかし職員たちが雨乞いをしたおかげか、ようやく3日間ほど雨が降り、どうにか本日のイベントに間に合わせることができました。
実は本日の収穫祭を控え、私どもには一抹の不安がありました。豆が大きくならないのです。今夏の雨不足には非常に悩まされまして、直前まで「延期か中止か」という話が出ていたほどです。しかし職員たちが雨乞いをしたおかげか、ようやく3日間ほど雨が降り、どうにか本日のイベントに間に合わせることができました。今年の気仙沼茶豆は、まさしく“幸運の茶豆”でございますので、ぜひ皆さんにもたくさん召し上がっていただきたいと思っております。
出席者インタビュー
畠山 盛信 様
JA南三陸 理事
「茶豆」の呼び名は、さやに生えている毛が茶色いことに由来します。収穫作業は毎年8月末から9月25日の期間の内、約10日間。それを過ぎると豆熟(とうじゅく)し、大豆になってしまいます。実は以前、豆熟した気仙沼茶豆で豆腐を作ってみたのですが、残念ながらあまりおいしいものではありませんでした。“大豆”としては、あまり風味の良い品種ではないようです。しかし“枝豆”として食べるには、この上なくおいしいと自負しています。雨不足の中、収穫直前になってようやく数日間の雨にも恵まれたおかげで、今年の出来は非常によいですよ。
枝豆は連作障害(同一の圃場で同一の作物を繰り返し栽培すると、次第に生育不良となる現象)があるため、85haある畑を22~23haずつローテーションさせながら作ってきました。しかし津波でその半分ぐらいがやられ、ローテーションができなくなっています。今年収穫したところにも、一部連作障害が出て、葉が黄色くなってしまっていました。現在作っている場所には来年水稲を植え、茶豆は新たな場所で作付けする予定です。
佐藤 広美 様
みやぎ野菜ソムリエの会 野菜ソムリエ
 秋の風物詩であった「気仙沼サンマまつり」ですが、震災の影響でここ2年ほど中止になっています。そこで“気仙沼サンマの火を絶やしたくない”と考える有志たちが、代わりに企画したのが「気仙沼ベジフルさんままつり」。
秋の風物詩であった「気仙沼サンマまつり」ですが、震災の影響でここ2年ほど中止になっています。そこで“気仙沼サンマの火を絶やしたくない”と考える有志たちが、代わりに企画したのが「気仙沼ベジフルさんままつり」。主催メンバーは「全農みやぎ宮城県園芸作物ブランド化推進協議会」「おさかな市場」、そして私が所属する「みやぎ野菜ソムリエの会」です。昨年実施したところ大変好評を得て、今年は10月8日に第2回目の開催が決まりました。
今回こちらの収穫祭にお招きいただいたのは、「気仙沼ベジフルさんままつり」で気仙沼茶豆を紹介するためです。今日はサンマと茶豆をおいしく一緒にいただくためのヒントを、ぜひ見つけたいと思っています。
昨年の「気仙沼ベジフルさんままつり」は、地元の元気を応援することを主軸に実施しましたが、今後は気仙沼の観光資源を県内外にPRしつつ、より「楽しさ」を打ち出せたらと考えています。ぜひ多くの方に足を運んでいただきたいですね。
さる6月6日のJA南三陸贈呈式でインタビューをした菊農家の佐藤隆雄さんに、その後の状況をうかがいました。6月6日のインタビュー内容は、こちら をご覧ください。
佐藤 隆雄さん
JA南三陸農協花卉部会 部会長
 菊作りは7月から9月までの出荷分を露地で、それ以降はハウスで行います。ハウス内は3つのブロックに分けていて、その内1つは11月出荷分の栽培に使用中。現在2つは休ませていますが9月になったら来年8月出荷分の苗作りをスタートさせます。
菊作りは7月から9月までの出荷分を露地で、それ以降はハウスで行います。ハウス内は3つのブロックに分けていて、その内1つは11月出荷分の栽培に使用中。現在2つは休ませていますが9月になったら来年8月出荷分の苗作りをスタートさせます。露地では8月のお盆時期に向け、3品種の菊を栽培していました。しかしブラジル産の1品種が予定より成長が早く、7月で咲ききってしまったんです。そのため出荷できたのは残りの2品種だけでした。
ところがこの2品種に、結構高値が付いたんですよ。例年は平均1本60円のところ、今年は70円で売れました。おそらく梅雨に雨が多過ぎたことと猛暑の影響で、市場にものが不足していたからでしょう。あいにく私の畑では、梅雨時期の雨が少なかったことが幸いしました。
 現在、露地ではお彼岸用に9月出荷分を栽培しています。ですが、8月分とは逆に雨不足に悩んでいます。露地栽培では通常、水撒きをしません。ところが今は週3回ペースで水撒きをしても間に合わないぐらいなんです。特に今年の雨は降ってもごく局地的で、自宅周辺では降ったのに、1kmも離れていない畑では降らない、という皮肉なこともありました。また菊は7月から9月の間、夜に20度以上ある日が続くと生育が遅れがちになるのですが、その影響も出ているようです。
現在、露地ではお彼岸用に9月出荷分を栽培しています。ですが、8月分とは逆に雨不足に悩んでいます。露地栽培では通常、水撒きをしません。ところが今は週3回ペースで水撒きをしても間に合わないぐらいなんです。特に今年の雨は降ってもごく局地的で、自宅周辺では降ったのに、1kmも離れていない畑では降らない、という皮肉なこともありました。また菊は7月から9月の間、夜に20度以上ある日が続くと生育が遅れがちになるのですが、その影響も出ているようです。おそらくこの調子では9月の出荷は間にあわないでしょう。その場合は残念ながら、畑に漉き込んで緑肥にするしかありません。ハウス栽培の11月出荷分は順調に生育しているので、こちらに期待をかけたいところです。
 ハウスは津波で壊滅しましたが、新しく建て直すことができました。当初、引渡し予定日は5月でしたが、当時ハウスを建てる人材が不足していたことと、ハウスで使用する電気の使用申請が集中し、許可がしばらく下りなかったことで、最終的に6月29日の引渡しとなりました。実は5月の引渡しを見込んで苗を育てていたのですが、それを全部ダメにしてしまったのは痛かったですね。
ハウスは津波で壊滅しましたが、新しく建て直すことができました。当初、引渡し予定日は5月でしたが、当時ハウスを建てる人材が不足していたことと、ハウスで使用する電気の使用申請が集中し、許可がしばらく下りなかったことで、最終的に6月29日の引渡しとなりました。実は5月の引渡しを見込んで苗を育てていたのですが、それを全部ダメにしてしまったのは痛かったですね。来年は今年の3倍の出荷を目指します。実は津波をかぶった300坪分の畑が手付かずの状態。さらに除塩は終えたものの、使用せず休ませていた分が600坪ほどありました。来年は満遍なく作付けできるよう、今から苗作りを頑張りたいですね。
近頃仏花は価格の安い中国産に押されていますので、今後は輸出も視野に入れたいと考えています。