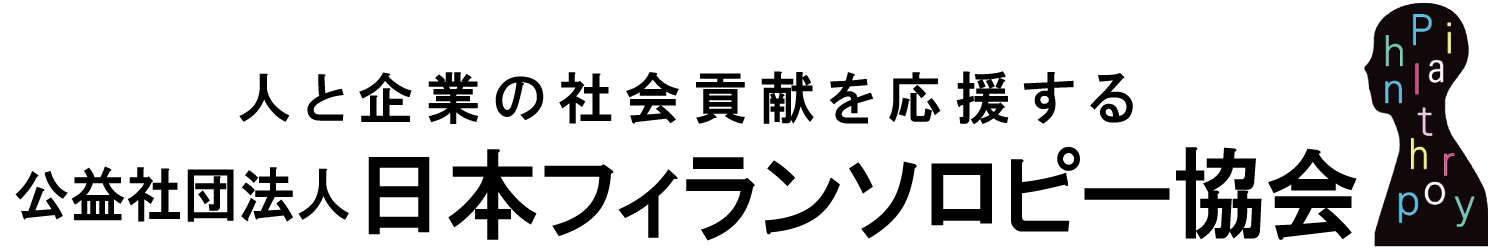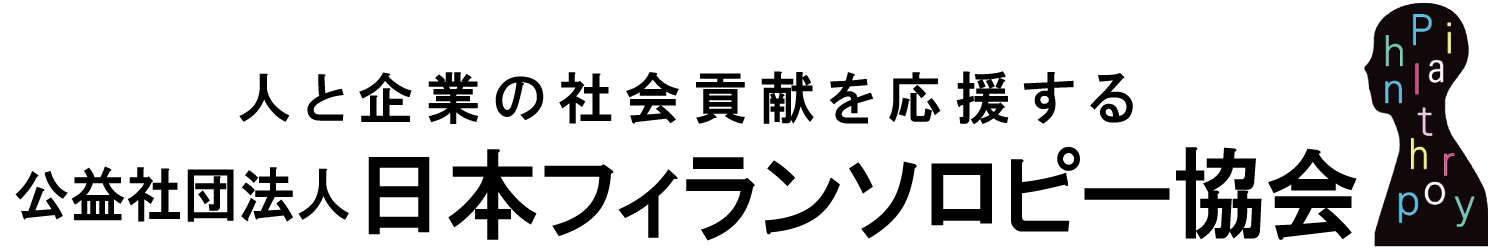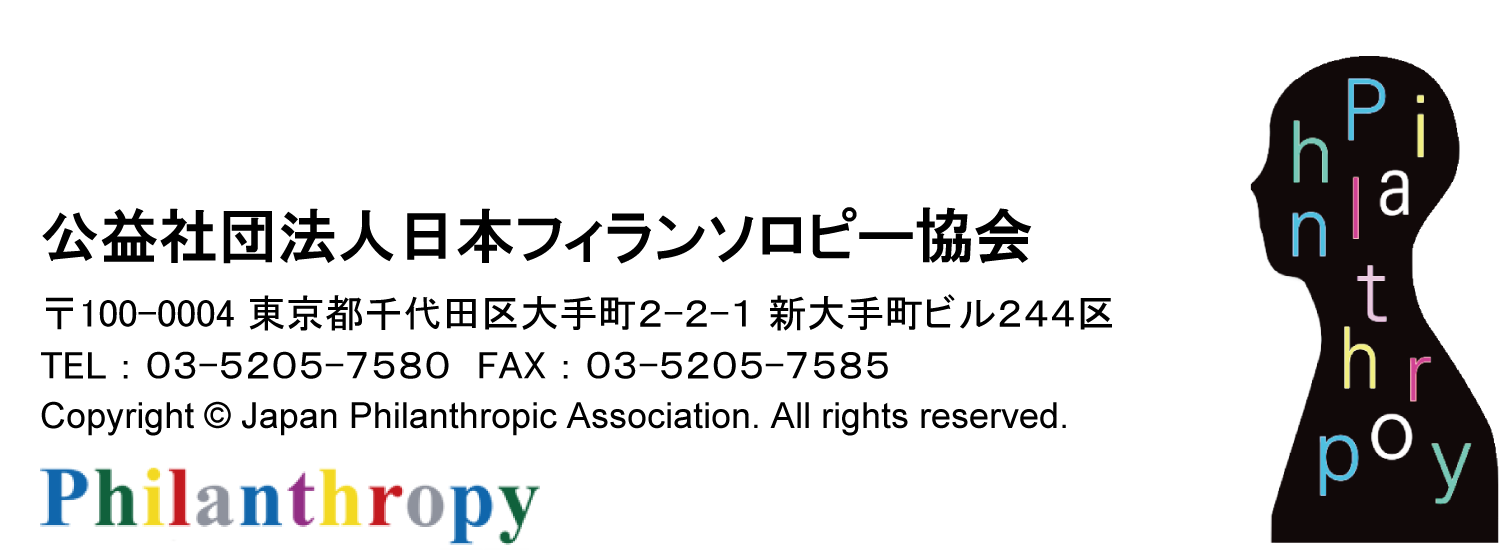今日から2022年度が始まった。昨年度は、30周年事業に没頭していて、気づいたら・・・。
今年度は、これまでの事業を生かし、点から線へ、そして面へと拡げていかなければ、と思っている。
SDGsの「誰も取り残さない社会づくり」の実現のために当協会ができることは何か、と考えたとき、属性を超えた「共感」を軸に、それぞれの個人や企業が社会課題のリアルを伝え、課題解決のための実行可能な方策を共に見出し、実行に移すためのコーディネートや伴走か。取り残されがちな人も含めて誰もが、社会参加・社会貢献ができる機会の創出をめざしたいと思っている。
昨年度実施し、今年度に繋げ発展させたい事業をご紹介しよう。
一つは、久里浜少年院での「花育」。少年たちが独居室でミニ胡蝶蘭の花を咲かせ、それをNPOや施設などに寄贈するというもの。昨年12月には、花の寄贈先である団体の方に同少年院に来ていただき、贈呈式を行なった。少年たちは、その準備のために、絵を描いたり紙で花飾りを作ったり、贈呈式を楽しみに準備していたそうだ。
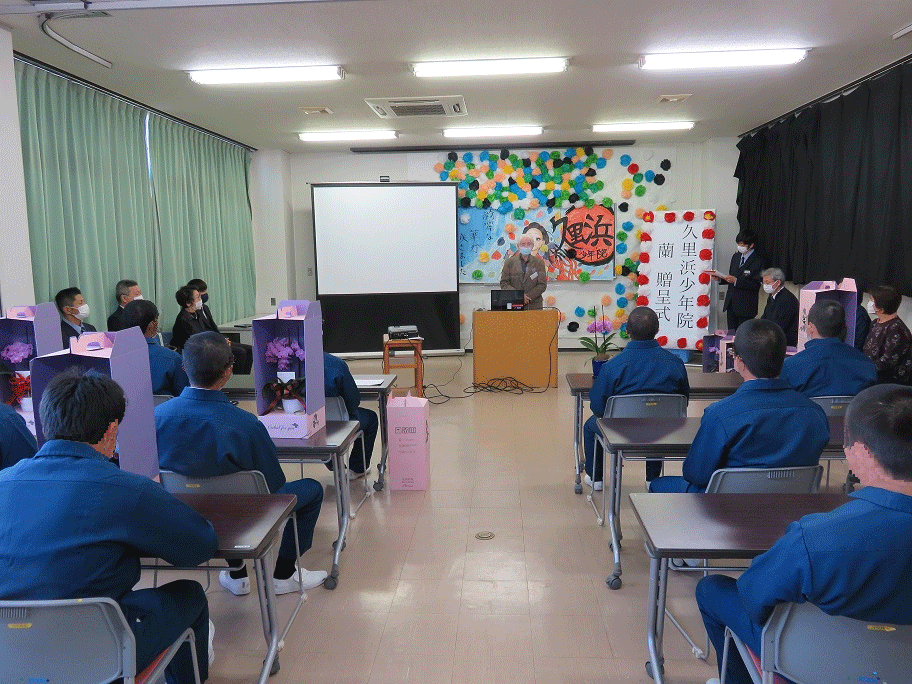
久里浜少年院での「蘭」贈呈式
詳細は
こちら をご参照ください。
“相棒”となった花と別れるのが寂しい、と異口同音に言っていた。そして、寄贈先の神奈川県立こども医療センターの動画で病気の子どもたちの様子を見た後、「この花を見ている時は、せめて病気の苦しみを忘れてほしいです」と言う。
この子たちは100%、残酷な虐待を受けてきた子どもたち。親に、大人に、社会に、そして自分に絶望して少年院に入ってくると聞いた。出院までに、少しでも「信頼と希望」を感じてもらいたい、と思っている。花を咲かせ、人が喜んでくれる、という体験をして、自分にも人を思いやる心がある、自分を応援している人がいることを実感しつつ実社会に戻って、就職しささやかでも幸せを実感できる人生を送ってほしい、と祈るばかりである。
もう一つは福島県郡山市の委託事業としての 農福連携事業。昨年度まで3年間にわたり実施した。障がい者や引きこもりなど就労困難者の仕事づくりと農家の人手不足・後継者不足の解決にも資するためのパイロット事業であった。先ほどの少年院出院者に関していえば、仕事をしていない人の再犯率は就労している人の3倍と言われている。少子高齢化の中、まさに社会の損失である。タックス・イーターではなく、タックス・ペイヤーを増やし、本人たちの生きがいにもつなげたいと思う。

農福連携事業の就労サポーター育成研修
研修生が障がい者の収穫作業を見ています。
詳細は
こちら をご参照ください。
そこで見えてきた課題は、農家も福祉側も共に人手不足だということ。そこで、農福連携事業のサポーターを増やす必要性を実感し、カリキュラム作りとパイロット研修を実施した。カリキュラムをさらに改良しながら、企業ボランティアを中心に、各地でサポーター育成研修を行いたいと思っている。このところ、企業の社会貢献として、従業員のボランティア参画への関心が高まっている。今年度は、東京はじめ全国の数か所でサポーター育成のための研修事業を実施する予定である。農業や就労困難者の伴走に関心のある方々の参加を期待したい。
今年度は「取り残されがちなひと」の可能性と魅力を広く一般の人たちにも伝え、参画を促しながら、コミュニティ全体が優しく元気になるよう、面的な拡がりをめざしてスタッフとともに力を尽くしたい。