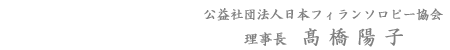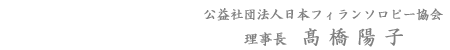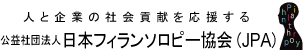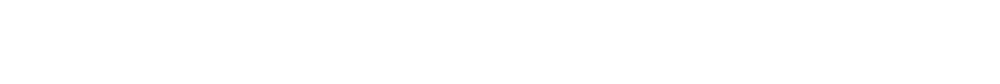当協会機関誌 『月刊フィランソロピー』 2011年2月号に掲載
当協会機関誌 『月刊フィランソロピー』 2011年2月号に掲載
 2011年1月8日、当協会理事・横澤彪(よこざわ・たけし)さんが亡くなられました。昨年秋の理事会でお目にかかったのが最後でした。ちょうど『月刊フィランソロピー』2011年2月号 は「笑い」をテーマにしていましたので、お話を伺いたかったのですが、体調を崩されたということだったので、年明けに全体のコメントをと思っていた矢先の訃報でした。年賀状には、「1月24日に終の棲家として、バリアフリーのマンションに引っ越すので、また遊びにいらっしゃい。」と書かれていました。横澤さんらしく、闘病生活にもまっすぐに向き合い、最後まで弱音を吐かず、笑いながらさよならをなさったような気がします。さわやかな幕引きと言うべきでしょうか。
2011年1月8日、当協会理事・横澤彪(よこざわ・たけし)さんが亡くなられました。昨年秋の理事会でお目にかかったのが最後でした。ちょうど『月刊フィランソロピー』2011年2月号 は「笑い」をテーマにしていましたので、お話を伺いたかったのですが、体調を崩されたということだったので、年明けに全体のコメントをと思っていた矢先の訃報でした。年賀状には、「1月24日に終の棲家として、バリアフリーのマンションに引っ越すので、また遊びにいらっしゃい。」と書かれていました。横澤さんらしく、闘病生活にもまっすぐに向き合い、最後まで弱音を吐かず、笑いながらさよならをなさったような気がします。さわやかな幕引きと言うべきでしょうか。
1998年に、(当協会が)『まひるのほし』という知的障害者のアートと生活をテーマにしたドキュメンタリー映画を作りました。この映画は製作委員会形式をとっていましたが、その委員長を横澤さんにお願いしました。当時は、吉本興業の東京支社長で、多忙を極めておられましたが、製作前の委員会、そして撮影が終わってからも、試写室に何度も足を運んで編集にも立ち合って下さいました。最初に、どういう映画にしようかという話になった時、横澤さんは、「笑える映画にしよう」とおっしゃったのです。そして、その通りになりました。朝日新聞のコラムでも紹介していただきましたが、その中でも「知的障害を抱える3人のアーティストが主人公である。彼らの職場、地域社会、家族との関わりを追求することによって、生きるとはどういうことなのかを考えさせてくれる。笑えるシーンが多いというのは、この種の映画では画期的なことだ。佐藤真監督の非凡な感性から生まれたものだろう。」 でき上がった時、完成度の高い映画だと褒めてくださいました。そして、『月刊フィランソロピー』で映画の特集をした時にも、コメントを書いて下さいました。私は、その文章が好きでした。
タイトルは「利口と馬鹿を超越した存在」
タイトルは「利口と馬鹿を超越した存在」
自分を利口だと思っている人は意外に多いものだ。いや、正確にいえば、利口だと思わなければ生きていけない人が多いのだ。青年だったら、小生意気だが元気があっていいぐらいで済むが、年をとってもまだ自分を利口だと思っている人は、本当に始末が悪い。世の中をダメにするからだ。逆に、自分を馬鹿だという人は少ないが、屈折した精神の人が多いから、油断すると痛い目に会う。この映画の主人公たちは、世の中から知恵おくれという烙印を押されているが、決して自分からは利口とも馬鹿とも言わない。全エネルギーをアートにぶつけているだけだ。その創造力の奥深さに圧倒される。利口と馬鹿を超越しているからだ。
この映画での笑いは、意外と横澤さんが追求していた笑いを創造する仕事に共通するのかも知れないと思いました。全身全霊を傾けて番組を作る。そして制作は、単なる役割分担の集合ではなく、裏方さんも表に出し、総力で番組を視聴者に投げる。それを視聴者は自分なりに受けとめ、応える。その相互作用を生みだすために覚悟を持ってボールを投げる。それが横澤さんのプロデユーサー魂だったように思います。
横澤さんの人生のテーマは「笑い」だとおっしゃっていました。多くの芸人を育てた名プロデユーサーとして有名だったことは皆さんよくご承知ですが、人間へのあくなき愛情と冷徹な観察眼を共に持ち合わせた方だったと思います。
ユーモアある笑い、情のつまった笑い、人を突き放しているようで実は丸ごと包み込む笑い。そんな笑いに満ちた社会ができたら、うれしいなと思います。横澤さんは、21世紀は個性の時代だと言っておられました。自分のためだけでなく、社会のために個性を発揮するという心構えが大事とも。
ユーモアある笑い、情のつまった笑い、人を突き放しているようで実は丸ごと包み込む笑い。そんな笑いに満ちた社会ができたら、うれしいなと思います。横澤さんは、21世紀は個性の時代だと言っておられました。自分のためだけでなく、社会のために個性を発揮するという心構えが大事とも。
横澤さんとの出会いは、当協会が日本フィランソロピー協会として発足するという新聞記事を見て、以前から前理事長とお知り合いだった横澤さんが、わざわざ電話をかけてきてくださって、「できることがあったら何でもお手伝いしますよ。」と言ってくださった時でした。それから、全国各地への講演会やイベントにも、快くご一緒してくださいました。
名プロデューサーの思いを、きちんと受け止めて仕事ができているだろうかと、心に問い直しています。恩返しができないで終わってしまいました。「笑い」の満ちた社会を次世代の子どもたちに手渡すことができるよう、一人ひとりの善の個性を生かすために、コツコツと、プロセスにも笑いとユーモアを満たしながら努力を積み重ねることで恩に報いたいと思います。心からの感謝とともに、ご冥福をお祈りいたします。
2011年2月1日