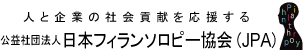Date of Issue:2018.12.1
<プロフィール>
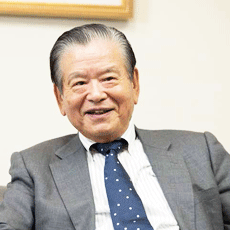
1936年大阪府生まれ。早稲田大学時代からサッカー日本代表チームで活躍。1961年古河電工に入社しサッカー部でプレー。1964年東京オリンピック日本代表チームで活躍。1991年にJリーグ初代チェアマン就任。2002年、日本サッカー協会会長に就任。名誉会長、最高顧問を経て、現在は同協会の相談役を務める。
2015年からは国際バスケットボール連盟の要請を受け、日本バスケットボール界の改革のためのタスクフォースチェアマンとしてBリーグ立ち上げに手腕を発揮。
◆ 巻頭インタビュー/No.389
自分のためではないから言いたいことが言える
川淵 三郎 氏
公益財団法人日本サッカー協会(JFA)相談役の川淵三郎さんは、当協会の2017年度「第20回まちかどのフィランソロピスト賞」の「特別賞」を受賞されました。「サッカーを通じて社会の発展に貢献する」というJFAの理念の実現のためにも、日本の寄付文化を広げなければと、ご自身でも誕生日に寄付を続けておられます。
ちょっと痛い金額を寄付
― 12月3日がお誕生日なんですね。ご自分の誕生日に、寄付を長く続けていらっしゃるとか?
川淵三郎氏(以下敬称略) Jリーグが開幕してことしで25年になるので、その前からですから25年以上です。
― その寄付の金額の決め方が、心に響きました。「どれくらい出したらいいですか」という質問に、寄付先の「公益財団法人さわやか福祉財団」理事長の堀田力先生(ほった・つとむ/現・会長)が、「ちょっと痛いなと思う金額を」と答えられた。普通なら、「無理のない範囲で」と言いがちです。
川淵 印象深いですね。無理のない形だと、人のためになっている気がしない。「ちょっと痛い」ってところで、人のためになっているという認識ができます。
― 「さわやか福祉財団(当時は任意団体「さわやか福祉推進センター」)」に寄付なさるようになったきっかけは?
川淵 Jリーグをつくろうとしていたときから寄付をしたいという想いがありました。それがあったので、新聞記事で、堀田先生が検事を辞めて、福祉の道に転身されたことを知って、手帳にその住所を書き留めました。訪ねたときは、まだJリーグのスタート前。堀田先生も、ぼくのことをご存知なかったけれど、寄付できるようになったら受け取ってもらえますかと聞くと、喜んでというところがスタートです。
― 堀田先生も福祉の世界に入られたばかり。そこにJリーグの寄付と、ご自身の「ちょっと痛い金額」の寄付を申し出られた。感激されたでしょうね。
川淵 宝くじが当たったときに、多くの団体が寄付の依頼にきて、寄付先の選択に困るということを聞いていました。堀田先生のところは老人福祉。人はみんな歳を取るから、そこに寄付することは全員に行きわたることだと考えて、Jリーグでは老人福祉に寄付することにしました。
― 合理的ですね。続けてきて、どう感じておられますか?
川淵 一番には、安心して任せられる寄付先があることの喜びです。寄付の対象を見出すのは、難しいところがあるので、それができることがよかったと思っています。
― それで25年以上、個人的にもお誕生日に寄付をなさっていると。
川淵 自分の誕生日は忘れないし、誕生日に貢献できることで、少しは世の中のためになっているという想いにつながります。個人的に寄付したいけれど、面倒でもあり、どこにしようかなというときに、誕生日は寄付する日だと決めれば、行動の基点になる。ぼくなんか、秘書が「そろそろ」と知らせに来るから忘れません(笑)。
アメリカから学んだ寄付とボランティア精神
― Jリーグでの寄付がはじまったのは、どのような経緯からですか?
 川淵 Jリーグが開幕したのは1993年。当時、ファーストステージ(リーグ前期)は、サントリー株式会社の冠で「サントリーシリーズ」。セカンドステージ(リーグ後期)は、日本信販株式会社(現:三菱UFJニコス株式会社)による「NICOSシリーズ」でした。
川淵 Jリーグが開幕したのは1993年。当時、ファーストステージ(リーグ前期)は、サントリー株式会社の冠で「サントリーシリーズ」。セカンドステージ(リーグ後期)は、日本信販株式会社(現:三菱UFJニコス株式会社)による「NICOSシリーズ」でした。そのNICOSの社長さんが、各クラブのチケット購入などで使う「NICOSJリーグオフィシャルカード」の利用金額の一部を寄付すると言ってくれました。
それがどれくらいの金額になるのか、さっぱりわからなかったけれど、こういうときこそ、その寄付はJリーグが貰うのでなく、堀田先生のところへ寄付しようと。そのオフィシャルカードの売上の寄付額が、初年度でいきなり1,000万円以上。Jリーグからも寄付することにして、毎年2,000万円ほど寄付してきました。
― すごい金額! 初年度から寄付することを、理事会が承認したのも、すばらしいですね。
川淵 ぼく自身は、反対があっても通すつもりだったけれど、「各クラブが利益をあげられるとは限らないから、寄付などせずに、クラブに分配するべきだ」と言う人もいました。そのときに、「このような公の団体は寄付するべきです!」と、バシッと言ってくれた女性理事がいて、全員賛成に(笑)。
― まさにJリーグの在り方の原点。
川淵 少しでも世の中のプラスになることだから、寄付は、はじめからやりたいと考えていました。
― 企業の利益や、宣伝のための企業スポーツ全盛のころ、スポーツ振興に社会貢献を結びつけたのは?
川淵 Jリーグがどうあるべきかと考えていたときに、アメリカの「スーパーボウル」で社会貢献の話を知りました。
ナショナル・フットボール・リーグ(NFL)の全米1を決める「スーパーボウル」は、テレビの放映権や観客動員の点で、世界で一番のビッグゲーム。1993年に、カリフォルニア州パサデナのローズボウルで行われた「スーパーボウル」を観に行ったときでした。
ナショナル・フットボール・リーグ(NFL)の全米1を決める「スーパーボウル」は、テレビの放映権や観客動員の点で、世界で一番のビッグゲーム。1993年に、カリフォルニア州パサデナのローズボウルで行われた「スーパーボウル」を観に行ったときでした。
― チケットは、なかなか手に入らないとか。高額なんでしょうね。
川淵 チケットは175ドルでした。スーパーボウルを招致するために、各都市は相当なお金をかけてNFLに働きかけるのですが、そこでNFLの事務局は、開催都市に対してチケット何千枚かの販売権を渡すんです。市は、それをいくらで売ってもいい。当時、知り合いだったアメリカンフットボールの評論家を通じてチケットを買ってもらったところ、円換算で5万円くらいかなと思っていたら、50万円でした。
― まあ、そんなに!
川淵 それでも観たい人がいるんだから、金額の多寡には関係ないのでしょう。それだけに市は、最高級のもてなしをしてくれました。1週間のスーパーボウルウィークの間に、記者会見をはじめ、監督の部屋やスタープレーヤーのロッカールーム、そのほか、町中でやるすべてのイベントを観せてもらいました。市庁舎で、開催内容の説明も丁寧にしてくれて、50万円の値打ちは十分ありました。かいぎょう
そこで、ハンディキャップのある子どもたちを招待するために、チケットを1枚1,000ドルで売ったら、あっという間に売り切れたという話を聞きました。それだけでなく、お金を出した人たちは、子どもたちを招待させていただき、ありがとうございましたという。そんな話を聞いて感動しましたね。
― アメリカのボランタリズムの底力ですね。
川淵 その年(1993年)の5月15日に、Jリーグの開幕戦があったので、すぐに東京に電話しました。
招待券はすでに配ってしまったけれど、障がいのある人たちを招待したいので、スポンサーからチケットを譲ってもらえないかと。すると、サントリーさんが500枚ほど提供してくれました。アメリカを通じて、奉仕の精神、寄付やボランティア精神を学び、Jリーグでも同じことをやろうと思いました。
招待券はすでに配ってしまったけれど、障がいのある人たちを招待したいので、スポンサーからチケットを譲ってもらえないかと。すると、サントリーさんが500枚ほど提供してくれました。アメリカを通じて、奉仕の精神、寄付やボランティア精神を学び、Jリーグでも同じことをやろうと思いました。
スポーツ界の抱える問題とは
― 企業スポーツ全盛のなかで、日本ではじめての、地域密着型クラブ・スポーツの発展に尽くされた川淵さんは、2005年に、「サッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、人々の心身の健全な発達と社会の発展に貢献する」という日本サッカー協会の理念を宣言されました。
川淵 スポーツの存在価値は、子どもたちの健全な育成や、地域社会の活性化に直結します。日本サッカー協会、そしてJリーグは何のためにあるのかということです。
例えば、バスケットボールのbjリーグ(日本プロバスケットボールリーグ)は、10年間も日本バスケットボール協会とうまくいかなかった。それは、何のためにやっているのか、その目的意識がなかったことが原因です。
例えば、バスケットボールのbjリーグ(日本プロバスケットボールリーグ)は、10年間も日本バスケットボール協会とうまくいかなかった。それは、何のためにやっているのか、その目的意識がなかったことが原因です。
― 川淵さんは、分裂していたふたつのトップリーグを統合し、バスケットボール「Bリーグ」の立ち上げにも尽力されました。そこで大切なことは、目的意識だと。
川淵 理念を定め、しっかりした経済活動をして、そこで上げた利益を社会に還元していこうという目的意識があれば、働くことも辛くない。ところがbjリーグは、「代表強化はどうでもいい」というスタンスで、しかも赤字で先行きが見えないまま、自転車操業でやっていた。はじめにビジョンを持てと言ったのは、そういうことです。目的を強く意識することで、努力する力も湧いてくる。だから一喝しました(笑)。
― いま、スポーツ界では、さまざまな問題が露呈していますから、一喝していただきたいところが、たくさんありますね(笑)。問題は、どこにあるのでしょうか。
川淵 問題になっていることは、昔からあることです。それが、こういう時代になって、顕在化しただけ。根本的な問題は、人材がいないことです。その競技で活躍したOBが、そのまま協会の幹部になって運営する。競技の普及振興、代表の強化、財政の確保に関してどうするかについて、考えもなくやっている人が多い。経営のプロがいないことが問題なんです。
今、問題が起きているところは、ガバナンスが欠如している。必要なのは、組織を運営することのできる人材です。しかし、その人材を雇うお金がない。優秀な人材はボランティアでは集まりません。財源が豊かでない、豊かでないから人が集まらないという悪循環があります。
日本のスポーツは、アメリカのそれと比べれば遅れています。言い換えれば、日本のスポーツは、いい人材がいればもっともっと発展する。その意味で、今のスポーツ界は、大きな「伸びしろ」があります。
今、問題が起きているところは、ガバナンスが欠如している。必要なのは、組織を運営することのできる人材です。しかし、その人材を雇うお金がない。優秀な人材はボランティアでは集まりません。財源が豊かでない、豊かでないから人が集まらないという悪循環があります。
日本のスポーツは、アメリカのそれと比べれば遅れています。言い換えれば、日本のスポーツは、いい人材がいればもっともっと発展する。その意味で、今のスポーツ界は、大きな「伸びしろ」があります。
― そこで大切なのは、ビジョン。ビジネスはビジネスとして、社会貢献は別ということではなくて、同じ方向を向いてやっていく。川淵さんから明確に伝わるのは、明らかに「自分のため」ではないことです。
川淵 そうじゃないから、いろんなことが言えます。
― 忖度せず、ですね。
孤独なリーダー
― はっきりもの申すところは、会社にいらしたときからですか?
 川淵 新入社員で会社に入ったとき、決まったことに対しては逆らわなかったけれど、これから決まることに対しては、どんどん意見を言いました。上司から見たら、こんな部下はいてほしくないと思ったかもしれません(笑)。
川淵 新入社員で会社に入ったとき、決まったことに対しては逆らわなかったけれど、これから決まることに対しては、どんどん意見を言いました。上司から見たら、こんな部下はいてほしくないと思ったかもしれません(笑)。自分のことを言ったのは、職場で現場の人が足りなくなり、現場に出ろと言われたとき。工場では、そういうことはよくあるけれど、「重要な仕事をしていたら、現場に出ろとは言わない。普段の仕事が役に立っていないなら、ちゃんとした職場に変えてほしい!」と、人事課長に強く抗議したことがあります。そういうことは、我慢がならなかった(笑)。
― そんな会社生活30年、日本サッカーの普及振興を経て、バスケットボールプロリーグを立ち上げられた。
川淵 みんなでJリーグを立ち上げ、その機関車役をやってきた経験があったので、日本のバスケットボール界を短期間で改革することができました。年齢も重ねていたし、みんなが一目置いてくれている。だからこそ利己的でなく、「全体の幸せのためにどういう方向に向くか」について明確に示す。そのときに右往左往しているようでは、リーダーにはなれません。
― そこで思い出すのが、Jリーグが開幕してすぐ、マスコミを賑わせた読売新聞の渡邉恒雄社長(当時)との論戦。川淵さんの目的意識が、はっきり示されました。
川淵 渡邉さんとの論争が起きたときには、どう対応していいかわからなかった。たじたじ感はありました。といって、まわりが助けてくれるわけではない。その経験が自分を強くしましたね。
― 地域社会に密着したクラブ・スポーツの実現を目指す川淵さんと、プロ野球と同じように、親会社がチームを所有して、利益や宣伝につながる組織を目指した渡邉さん。「犬猿の仲」と目されました。ヴェルディ川崎か、読売ヴェルディか。スポーツの在り方を問う論戦で、川淵さんの支えになったのは、何ですか?
川淵 誰かに相談したという記憶は、あまりありません。よく覚えているのは、渡邉さんがぼくのことを「独裁者」と呼び、売り言葉に買い言葉で「独裁者から独裁者と言われて光栄です」と言い返したこと。それに対して、まわりが「ちょっと言いすぎた」と謝った。その必要はまったくなくて、あのときに謝ってしまうのは、ぼくの立場を慮っていない。
だからトップは孤独で、自分がしっかりしていなくてはダメだ、自分で解決するしかないと思いました。
だからトップは孤独で、自分がしっかりしていなくてはダメだ、自分で解決するしかないと思いました。
― 腹を据えれば。
川淵 渡邉さんに怯んだことは、一度もありません。あの強い渡邉さんに刃向うチェアマン。それで、世間が認めてくれました。
― ぶれないところが、信頼につながります。
川淵 その意味で、感謝しなくちゃいけないと思っています。結果的に、ぼくを強くしてくれたし、Jリーグの「理念」や「ビジョン」を、世の中に説明するチャンスを与えてくれました。そのときは本当に嫌でしたけどね(笑)。
― 著書「黙ってられるか」には、対談が掲載されているそうですね。。出版社から対談相手を聞かれて、真っ先に渡邉恒雄・読売新聞グループ主筆を挙げたとか。そういうところがカッコいいです。あの論戦で、渡邉さんご自身も、川淵さんを信頼なさったんじゃないですか。
川淵 対談では、そういうことを言っておられました。哲学者で知性と教養の固まりの人です。そういう方と侃々諤々とやれたのは、振り返れば非常によかった。
笑うから幸せになれる
― 日本になかなか現れないリーダーの筆頭たる川淵さんは、どんなお子さんだったのですか?
川淵 ナイーブで、自分の主義を主張するより、その人がどう思っているのかと、人の気持ちを慮るところがありました。それとは別に仕切り屋でもあり、野球をやるにも、みんなを集めて全部仕切ってました。
― 小さいときから、プロデュース力があったのですね。
川淵 暴力で従わせるガキ大将ではないから、喧嘩したことは1回か2回しかありません。それも、向こうがかかってきたからやっつけただけ。
― オペラの「椿姫」で、ヒロインが、青年貴族の父親から息子と別れるように言われて去る場面では、いつも感動して泣くというお話も興味深いです。
川淵 その女性の気持ちを想うと、切なくて感動します。
― そんな川淵さんを育てたお母様は、どんな方なのですか?
川淵 親父は偏屈なほうだったけれど、お袋は明るかったな。ぼくは、お袋似ですね。
― 幸せだから笑うのでなく、笑うから幸せになるといいます。お母様は、まわりの人を楽しくさせようと思う方だったのですね。その明るさと思いやりが、川淵少年にも受け継がれました。
川淵 古河電気工業株式会社のサッカー部の監督をしているとき、あいさつすると、毎回硬い表情であいさつを返す人がいました。なぜ、そんな怖い顔をしているのかと思ったものです。それが、2年ほどして監督を辞めてからは、相手の表情が変わった。そのときはじめて、ぼくが怖い顔をしていたから相手に怖い顔をさせていたんだとわかりました。
― そこに気づかれたのが、すごい!
川淵 ぼくの表情を見て、向こうが不愉快になった。申し訳なかったなと思いました。昔、「ニコニコぶっちゃん」と呼ばれていたけれど、ニコニコぶっちゃんが、なぜ怖い顔になったのか。そこに、自分で気がつきました。
― 企業チームの監督としてのプレッシャーは、大変なものなのでしょうね。その後、サッカーを通じたスポーツ文化振興と社会貢献の道に進まれた。いま、川淵さんは、いい笑顔をしていらっしゃいます(笑)。
川淵 世のため、人のためにやったことは、自分にとって気持ちがいいものです。自分のやったことで多くの人に喜んでもらえて、役に立てたという想い。それは、フィランソロピー精神の大元でもあります。人間の心には、そういうものがあるんじゃないかと思います。
― 地域密着型で社会の発展に貢献するスポーツという、新しい考え方を普及してこられました。リーダーとは、「利己的でなく、全体の幸せのためにどういう方向に向くか」ということを明確に示すこと。深く心に刻みました。
きょうは、ありがとうございました。
きょうは、ありがとうございました。
【インタビュー】
公益社団法人日本フィランソロピー協会
理事長 高橋陽子
(2018年9月21日 公益財団法人日本サッカー協会にて)
公益社団法人日本フィランソロピー協会
理事長 高橋陽子
機関誌『フィランソロピー』No.389/2018年12月号 巻頭インタビュー おわり