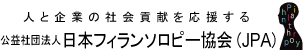Date of Issue:2022.12.1
◆ 特別インタビュー/2022年12月号

© Tatsuo Watanabe
オフィシャルサイト:
https://essay.tokyo/
現実に起きたこと、先人たちが体験したことを伝えたい
映画監督
川瀬 美香 さん
2022年8月5日、映画『長崎の郵便配達』が全国公開されました。英国人ジャーナリストのピーター・タウンゼント(Peter Townsend)氏が、16歳で郵便配達の途中に被爆した谷口稜曄(たにぐち・すみてる)さんと出会い、生涯をかけて核廃絶を世界に訴え続けた谷口さんを取材してまとめた本を題材に、タウンゼント氏の娘で女優のイザベル・タウンゼント(Isabelle Townsend)さんが、長崎で父の足跡をたどる物語。この作品を撮った映画監督の川瀬美香さんに、制作のきっかけや作品に込めた思いを聞きました。
タウンゼント氏の著書の復刊を願った谷口さん
― 『長崎の郵便配達』を観た後、静かな感動を覚えました。「平和」や「戦争反対」を前面に出すのではなく、立場や境遇の違いを超えた人と人とのつながりがあり、この映画を観た一人ひとりが平和を願い祈る。共感することの大切さを感じました。
谷口さんは郵便配達の途中で被爆され、背中一面を原爆の熱線で焼かれました。その写真や、絵画「赤い背中」で世界に知られました。日本原水爆被害者団体協議会の代表委員も務められ、2015年の国際平和地球会議(※)でスピーチもされています。谷口さんとの出会いが、この映画をつくるきっかけだったのでしょうか。
谷口さんは郵便配達の途中で被爆され、背中一面を原爆の熱線で焼かれました。その写真や、絵画「赤い背中」で世界に知られました。日本原水爆被害者団体協議会の代表委員も務められ、2015年の国際平和地球会議(※)でスピーチもされています。谷口さんとの出会いが、この映画をつくるきっかけだったのでしょうか。
※国際平和地球会議:2015年米国・ニューヨークで開催された核拡散防止条約(NPT)再検討会議に先立ち、各国のNGOが企画した会議。
川瀬 映画をご覧いただき、ありがとうございます。私は日本で生まれ育ちましたが、広島や長崎には親戚や友だちもいませんし、原爆投下についても学校の授業で教わる日本の歴史という程度の理解でした。2014年に初めて谷口さんにお目にかかったとき、その人生観に圧倒されました。1984年にタウンゼントさんが谷口さんをモデルに書いた小説『THE POSTMAN OF NAGASAKI』を復刊したいという強い希望をお持ちでした。私はその本のことを知らなくて、慌てて図書館で取り寄せて読みました。英国人という視点も斬新でしたし、原爆が落ちたことで終わるのではなく、被爆した谷口少年が生き延びて、家族を持つところまで描いている。そこに共感しました。復刊については、知り合いの小さな出版社が快く引き受けてくれましたが、映像にするには大きすぎて、自分では向き合いきれない、手に負えないテーマだと感じていました。

©長崎の郵便配達製作パートナーズ
― 本の復刊が先にあったのですね。海水浴に行ったときにお子さんたちに背中を見せるシーンがありましたが、稜曄さんは「何も悪いことはしていないのだから、恥ずかしがることはない」と言われました。生き抜いてきた苦しみの中から生まれた覚悟や、怒りや悲しみもきちんと伝えなければならないという使命感がある。
川瀬 あのシーンは、稜曄さんが自分を隠さないと覚悟してお子さんに見せた、彼の人生の中でも節目だったのだろうと思います。とても強いハートをお持ちで、生きることに対して、力を振り絞っている。象徴的な場面として、大切に描いたつもりです。お子さんたちだけではなくて、私たちにも伝えていると感じます。
イザベル・タウンゼントさんとの運命的な出会い
― イザベルさんとはどのような出会いだったのでしょうか。
川瀬 タウンゼントさんの著書を復刊する際に連絡先を探して、谷口さんのご親族に手紙を書いてもらって送りました。2か月後ぐらいに突然返事が来たときは、皆でどよめきました(笑)。その後2016年に私がイギリスに行くことになったので、彼女と会う約束を取り付けたんです。初対面なのに「このまま父の書斎に行きませんか?」と誘ってくださって、ご実家にうかがいました。書斎は、タウンゼントさんが生前に使われていたままの状態でした。イザベルさんも書斎に入るのが久しぶりだったようで、そこで共通の思いが浮かびました。
― イザベルさんとの出会いでスイッチが入ったんですね。
川瀬 お父さんが亡くなって何年も経つのに、日本から突然連絡があったことにタウンゼント家では驚いたそうです。書斎には、広島や長崎のことが書かれた本がたくさんあって、資料として読み込まれたことがわかりました。ほかにも写真集やお土産のタペストリーなどがあって、日本人の私としては、ありがたいな、仲間がいるなという印象でした。カメラを持っていたので、出会った日に彼女のインタビューを撮りました。映画の冒頭に少し入れてあります。
― 意気投合したんですね。イザベルさんも川瀬さんに対して「この人とならば」と感じたのでしょう。
川瀬 共通のテーマが見つかったような感覚ですね。別れる時に彼女は「our film」と言ってくれました。
― お父さんのことをもっと知りたいという思いもあったのでしょうね。

©坂本肖美
川瀬 そうですね。彼女は父親の本のモデルになった少年が生きていることは知りませんでした。だからイザベルさんが稜曄さんと出会うところを撮ろうと話していたんです。帰国してすぐに稜曄さんに話したら、入院中は格好悪いから、秋に会おうということになりました。稜曄さんは、夏の時期はあまり体調がすぐれないと聞いていたので心配していたのですが、その夏の終わりに亡くなられました。2017年のことです。
― 稜曄さんからバトンを手渡されたのですね。イザベルさんはご家族で来日されたそうですが、お子さんたちはどんな思いだったのでしょうか。
川瀬 2018年にご主人と娘2人を連れて来日しました。文化の違いに戸惑うこともあったと思いますが、今はわからなくても大人になったらきっとわかるだろうという判断だったようです。原爆資料館の見学シーンもありますが、リアルな展示もありますから大丈夫かと確認しましたが、ご夫婦とも「連れていきます」と即答されたので一緒に入ってもらいました。
― 稜曄さんの精霊船を谷口家の皆さんとイザベルさんが押していくシーンがすごく自然で、淡々とした描写が非常に印象的でした。
川瀬 あの日を中心にロケを組みました。生前に会うことは叶いませんでしたが、精霊船は初盆の時だけの行事ですから、稜曄さんを見送りに行こうかということで。でも船を押してくれとは言っていなかったので、彼女が押してきたことにびっくりしました(笑)。
不変的で長く愛される映画に
― 中学校や高校でも上映会をされていますね。
川瀬 学校での上映会は積極的に増やしたいと思っています。ウクライナのことがあって、皆が戦争について身近に感じるようになっていますし、危機感も高まっています。日本でも77年前は戦争状態にあったんだという事実を知ってもらいたい。こうした現実があったことを多くの人たちに配達するのが私の仕事だと思っています。
― それがドキュメンタリー映画として集大成されたんですね。
川瀬 戦後生まれで経験がない世代は自分なりに想像することしかできません。だから、当初はこのテーマで作品をつくることはできないと思ったのですが、途中で、現在の自分の時間軸でつくってもいいのではないかと気が付きました。ならば、不変的で長く愛される映画をつくろう。そのことを重んじてつくったつもりです。
― この映画で、イザベルさんから未来に向かう明るさと意欲を感じました。
川瀬 彼女はすごくタフなんです。制作過程でさまざまな困難にぶつかりましたが、そのたびに励まされました。決してあきらめない。初めて会ったときに、子どもたち、未来の人たちに向けて作ろうと言っていたのですが、その思いは最後までぶれませんでした。力強さの一方で、穏やかでホスピタリティがあって、何より清潔感にあふれている。もともと『VOGUE』や『ELLE』 の表紙を飾るようなスーパーモデルで女優でもありますが、衣装もメイクも素のままです。面倒なのではなくて、今の時代はこうでなくてはならないという信念がある。とても共感できますし、見習うべきところがたくさんありました。
― 生き方、生き様ですね。素敵です。出来上がった映画を観たイザベルさんの感想は?
川瀬 日本に来て初めて大きなスクリーンで観たのですが、とても興奮していました。長崎では2人でこっそり映画館に行って一般の人に混じって観ていたのですが、見終わった時に皆さんが私たちを見つけてくれて、立ち上がって拍手してくれました。まるで映画祭のようで、とても感動的でしたね。
― 長崎の皆さんもうれしかったのでしょうね。今は戦争を知らない世代がほとんですから、未来に向けて私たちが伝えるメッセージ、郵便配達のような役割があるのだということを改めて思いました。
ドキュメンタリー映像を撮るということ
『長崎の郵便配達』
1984年ノンフィクション小説『THE POSTMAN OF NAGASAKI』が出版された。著者はピーター・タウンゼント氏。戦時中、英空軍のパイロットとして英雄となり、退官後はイギリス王室に仕え、マーガレット王女と恋に落ちるも破局。映画『ローマの休日』のモチーフになったとも言われている。その後ジャーナリストに転じた彼が、長崎で出会ったのが、16歳で郵便配達の途中に被爆した谷口稜曄(たにぐち・すみてる)さんだった。タウンゼント氏は、生涯をかけて核廃絶を世界に訴え続けた谷口さんを取材し、その生き様を一冊の本をまとめた。
この映画は、タウンゼント氏の長女で女優のイザベルさんが、父が残した取材テープでその声を聴き、長崎でその足跡をたどる旅を通して、二人の友情と平和への願いをひもといていく物語である。
『長崎の郵便配達』公式ホームページ
https://longride.jp/nagasaki-postman/
1984年ノンフィクション小説『THE POSTMAN OF NAGASAKI』が出版された。著者はピーター・タウンゼント氏。戦時中、英空軍のパイロットとして英雄となり、退官後はイギリス王室に仕え、マーガレット王女と恋に落ちるも破局。映画『ローマの休日』のモチーフになったとも言われている。その後ジャーナリストに転じた彼が、長崎で出会ったのが、16歳で郵便配達の途中に被爆した谷口稜曄(たにぐち・すみてる)さんだった。タウンゼント氏は、生涯をかけて核廃絶を世界に訴え続けた谷口さんを取材し、その生き様を一冊の本をまとめた。
この映画は、タウンゼント氏の長女で女優のイザベルさんが、父が残した取材テープでその声を聴き、長崎でその足跡をたどる旅を通して、二人の友情と平和への願いをひもといていく物語である。
『長崎の郵便配達』公式ホームページ
https://longride.jp/nagasaki-postman/
― ところで川瀬さんは、『紫』『あめつちの日々』というドキュメンタリー作品も撮っておられます。いずれも伝統工芸、職人の手仕事を伝えていくもので、今回の作品とも通じるものがあります。
川瀬 もともと映画監督を目指していたわけではないんです。長編に取り掛かってまだ10年ほどですが、自主制作にこだわって、仲間と一緒に自分たちなりのスタイルで作ってきました。ドキュメンタリーは、ある人物や事柄に付き添って切り取るものですから、対象者や対象物と一生付き合えるかどうか、覚悟を決めて撮ってきたつもりです。ですから、上映についても自分たちで責任を持って回り、観てくれた人の顔が見えることを大事にしてきました。
『紫』を撮っていた時に、感じたのは伝統工芸には未来があるということです。私たちは、人間も世の中も日々進化するものだと思っている。でもそれは勘違いで、1200年前の奈良時代に作られていたものが、現代人には作れない。つまり退化しているのではないか。歴史を勉強すると未来がわかるということに気付きました。でも自分が撮りたいと思ったものを作品にしたので、このスタイルがイコール映画監督かというとそれはわかりません。
『紫』を撮っていた時に、感じたのは伝統工芸には未来があるということです。私たちは、人間も世の中も日々進化するものだと思っている。でもそれは勘違いで、1200年前の奈良時代に作られていたものが、現代人には作れない。つまり退化しているのではないか。歴史を勉強すると未来がわかるということに気付きました。でも自分が撮りたいと思ったものを作品にしたので、このスタイルがイコール映画監督かというとそれはわかりません。
― 自分の好奇心の赴くままに撮った。考え方がシンプルです。
川瀬 テーマとしては『長崎の郵便配達』も同じだと思っています。伝えたいこと、知ってほしいこと、その人の気持ちに触れたことを重要視しています。これは自主制作でないとできません。でも今回の作品は、ありがたいことに配給会社がついてくだって、今後も上映予定の映画館があるようです。
― この作品がどんどん広まって、またどこかで奇跡のような、心が震えるような出会いがあるのでしょうね。次の作品の構想はあるのでしょうか。
川瀬 笑えるものが作れるといいなと思っています。今の時代、暗さや不安が進んでいる気配がありますから、明るい映画がいいかなと。いまはフィールドワークばかりで、日本中をうろうろして各地の伝統工芸や神楽を見て歩いています。
― 次回作を楽しみにしています。本日はありがとうございました。
【インタビュアー】
公益社団法人日本フィランソロピー協会
理事長 髙橋陽子
(2022年10月19日 オンラインにて)
公益社団法人日本フィランソロピー協会
理事長 髙橋陽子
機関誌『フィランソロピー』特別インタビュー/2022年12月号 おわり