2018.11.01
第4回/House Vision 2018 in 北京
先週は、北京に行っていた。初めての訪問であったが、システム化が進む大都市、スマホで呼ぶタクシー、清潔な街のトイレ、親切な市民、真っ青な青空、どれも想像で持っていた固定観念を覆す北京の姿だった。ただ、まだまだ国民の意識変革、ライフスタイルの変化などが追い付いていない現実もあった。これだけは予想通りだが、今後を注視しなければならない国であることには間違いない。
今回の主目的は、House Vision 2018 Beijing Exhibition の視察。これは「企業と建築家/デザイナーが協働し、これまで体験したことのない家のあり方を、原寸大で具体化する取り組み」。エネルギーや移動手段、通信、素材開発、AI、シェアリングなど、すべての産業は家とつながっている。従って、「家を考えることは、私たちの未来を複合的に考えること」だというコンセプトの下、中国で躍進する企業と気鋭の建築家/デザイナーが知恵を絞り作りあげた10棟の未来の家を実体験できる場である。建築家の原研哉さんのディレクション。会場の設計は隈研吾さん。今回は、当協会の活動にご協力いただいている土谷貞雄さんのご縁で視察に出向いた。土谷さんは、企画コーディネーターとして、この Exhibition 開催を果たした立役者だ。

北京オリンピックの会場となった有名な“鳥の巣”を背景にした家々を回ってみた。生活に使用し余った太陽光パネルによる発電と風力発電などのエネルギーを利用して、空気を水に転換し、それが水玉となって植物に注ぎ、育てるという仕組みを持つ家。「農」の概念がリセットされると共に、超スローな野菜の生育を媒体に、人と人とのより深いコミュニケーションをめざしている。
次は、火星で暮らす家! 説明によると、「人間の生活環境が整わない極限の地を想定することで、究極のサステイナブルな暮らしを研究できる」。火星移住において、輸送中は折り畳み、できるだけコンパクトにして、火星到着後はスーツケースのように居住スペースを作るというもの。自分の想像力を追いつかせるのに必死で・・・参った!
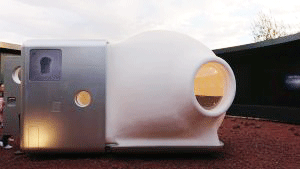
日本でもシェアハウスに関心が高まっているが、中国型新しいシェアハウス。個に分断された暮らしと住まいから、再びコミュニティを創りだす方法として考えられたもの。しかも、新たに建てるのではなく、空きビルや空き店舗などを再利用する。日本だとせいぜい10人単位だが、中国だと100人単位になりそう。そこで、起こりうるプライベートとパブリックの境界、家具などの私有と共有の混在など、面白い実験場となりそうだ。
公共の問題を考えたり、行動に移す場合、自分の暮らしのイメージの中で可視化してみることで、リアリティあるものとなる。未来の暮らしと人々の関係性に新たな地平が見えてくるような予感。なかなか濃密で刺激的な北京だった。ついでに報告すると、あまり関心のなかった北京ダックが、北京で食べて好物になった。