2019.02.01
第7回/石巻日日新聞に見るメディアの責任
先週は、嵐の活動休止宣言で大騒ぎだった。大野リーダーはじめ、5人のメンバーの記者会見の対応の何と素晴らしかったことか。どんな職業も、その道を究めた人は、プロフェッショナルとしての矜持があり、若いミュージシャンたちに大いに学ばせていただいた。片や、政治家のお粗末な会見を見るにつけ、自らの誇りと職業人としての矜持を示してほしいと国民の一人として切に思う。同時に、メディアの扱いには違和感を覚えた。全国紙がいずれも、嵐の休止宣言について写真入りで1面に取り上げている。かろうじて、日経新聞は社会面での扱いであったが。昨今、メディアの責任が言われているが、報道の扱い方、報道した内容のフォロー、いずれも首を傾げざるを得ないことが多々ある。政治家のレベルもメディアのレベルも国民のレベルを表していると言われている。健全な民主主義を考える時、大事な材料としたい。
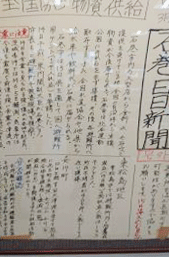
ところで、先日、セミナー開催のため、久しぶりに石巻を訪れた。町は、震災直後の、すべてがひっくり返っていた灰色の様相から、落ち着いた町に戻っていた。セミナーの始まる前、石巻日日新聞が震災翌年に創立100周年を記念して設立した「石巻NEWSee」を訪問した。
大正元年(1912年)の創刊、昭和16年(1941年)の「新聞統制」による「一県一紙」指令により、同紙は廃刊するか、河北新報に統合されるかの道を選ばざるを得なくなった。だが、同社はそれを拒否した。紙の配給が停止されると、家にあった藁半紙に鉛筆で記事を書き、地域に配ったという伝説がある。
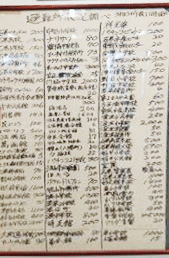
同紙のもう一つの伝説は東日本大震災発災直後。震災で町のほとんどが水没、電気・ガス・電話もネットも止まった中、紙の新聞が発行できなくなったが、手書きの「壁新聞」で、新聞発行を継続したのである。新聞社も浸水。水没を免れた新聞用ロールをカッターで切り出し、原稿を当時の報道部長、武内宏之氏が読み上げ、社長の近江弘一氏がフェルトペンで書いていく。6枚の同一の壁新聞を書き上げると、胸まで水に浸かりながら、手分けして6か所の避難所に貼りに行った。電気が通じるまでの1週間、出し続けた新聞が壁に貼られている。避難所にいる人の人数が貼り出されている。この数は単なる数字ではなく、家族が生きてそこにいるかもしれないという希望であった。地域メディアの矜持を示す石巻日日新聞の6枚の壁新聞は、圧倒的な熱量の記者魂とねがい・・・を思い起こさせてくれる。