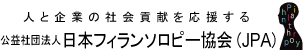2022.01.15
第32回/企業フィランソロピー大賞・元選考委員への追悼
昨年(2021年)は、フィランソロピー始動30周年記念で、『共感革命』出版やシンポジウム開催など、これまでの30年とこれからの30年の結節点としての意味を込めた事業を展開したが、その合間に、日本経済新聞夕刊での『人間発見』のコーナーに5日間の連載で、これまでの活動を取り上げてもらった。そんなこんなで、コロナ禍の収束が見えない中でもあり、あっという間に時が過ぎて、年が明けてしまった。
今年度(2021年度)も 企業フィランソロピー大賞 の受賞企業が決まった。
そんな中で、かつてこの顕彰事業を支えてくださったお二人が亡くなった。
 2012.2.16 第9回企業フィランソロピー大賞贈呈式
2012.2.16 第9回企業フィランソロピー大賞贈呈式
前列右端が木全ミツさん
(クリックすると拡大します)
お一人は、当協会の評議員・理事・顧問として、本当に長年にわたりお世話になった木全ミツ(きまた みつ)さん。
30年近く、実にいろいろ教えていただいたが、一貫して、人としてどう生き、どう仕事をするかということだった。企業フィランソロピー大賞候補企業への訪問の際も、選考委員会でも、全くぶれずに地球環境のために、女性活用のために、弱者の人権のために、時に厳しく意見をおっしゃった。東日本大震災後には、80歳までは頑張るとおっしゃって、被災地の女性の自立支援のために何度も現地へ赴き、いろんなアイディアで励まし続けられた。
当協会の 誕生日寄付 にも、ご自分なりにアレンジして協力いただいていた。ご家族・友人のお誕生日に胡蝶蘭を贈り、その一部を寄付するという仕組みにしたいとおっしゃって、昨年春に1年分の贈り先と費用をいただいた。そして、昨年夏の終わり、ご自身は随分弱っておられたのに、「来年の新しいアイディアを考えたので、来春にはまた相談しましょう」とメールをいただいた。このあと、春までに4人の方々にお贈りしなければならない。木全さんらしく、律儀に1年分をしっかり託して逝かれた。父上に言われ続けたという「人のお世話をするように、人のお世話にならぬよう」(後藤新平)を貫いた一生だった。不肖の押しかけ弟子としては、語り尽くせぬぐらい多くの教えと叱咤激励をいただいた。
もうお一人は、経済評論家の内橋克人(うちはし かつと)さん。企業フィランソロピー大賞の創設にあたって、その構想段階から2003年の第1回募集開始に至るまで、様々な観点からのご指導をいただいた。その後も、何かにつけて気にかけてくださり、「あの企業はいいね」とか、寄付をした個人を顕彰する「まちかどのフィランソロピスト賞」の受賞者を称える手紙をいただいたりしていた。経済格差による弱者への深い思いが根底にあったと思う。
お二人とも、人間への愛情(すなわちフィランソロピー)にあふれていたし、個への温かい眼差しが原点におありだった。感謝を込めて、ご恩に報いるためにも、使命をしっかり果たさなければと思う。
心よりご冥福をお祈りしたい。
そんな中で、かつてこの顕彰事業を支えてくださったお二人が亡くなった。

前列右端が木全ミツさん
(クリックすると拡大します)
30年近く、実にいろいろ教えていただいたが、一貫して、人としてどう生き、どう仕事をするかということだった。企業フィランソロピー大賞候補企業への訪問の際も、選考委員会でも、全くぶれずに地球環境のために、女性活用のために、弱者の人権のために、時に厳しく意見をおっしゃった。東日本大震災後には、80歳までは頑張るとおっしゃって、被災地の女性の自立支援のために何度も現地へ赴き、いろんなアイディアで励まし続けられた。
心よりご冥福をお祈りしたい。
※ 木全ミツさんへのインタビューを、機関誌『フィランソロピー』No.384/2018年2月号 に掲載しています。(全文を公開していますので、ぜひご一読ください。)

2021.10.08
第31回/誕生日寄付に寄せて
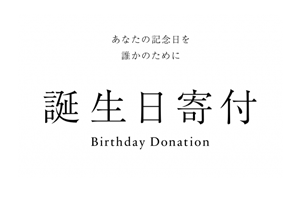
東京都内/都下の児童養護施設などで暮らしたり、経済的に苦しいながらも進学を望んでいる子どもたちに、月3万円(5年前から人数の増加により一人2万円に減額)の学費の援助をしている基金である。当協会が主宰していた「まちかどのフィランソロピスト賞」の受賞者・西脇麻耶さんが、若くして亡くなられたご主人の遺志を活かし、基金を創設なさった。その後、希望者が増え、とても個人では賄えきれないので、支える会というボランティア組織ができ、年々増加する進学希望者の夢を応援している。また、この基金は、西脇さんの、「人間は、どこで花が開くかわからない、従って、進学したいという希望者には選別せず皆に渡したい」という思いを受けているので、希望者は多い。昭和62年に西脇基金を創設し、初年度の応募は3名。その後、少しずつ増え続け、令和2年度は240人、令和3年度は269人を支援している。支える会では、毎年秋にはコンサートなどチャリティイベントを開催して資金を集めているが、昨年と今年は、コロナ禍で中止になった。なかなか厳しい状況である。子どもたちも厳しい。だから今年も寄付集めに奔走している。
人口減少、少子高齢化、コロナ禍、頻発する自然災害、社会の活力の低下で、ますますハンディのある人は振り落とされがちである。そういう人たちの希望を応援する一人ひとりのささやかな寄付も、合わせれば、今こそ持続可能な大きな力になる。「ちょっと痛い」寄付が、「ちょっと嬉しい」つながりになるかもしれない。
川淵三郎さんの「ちょっと痛い金額」のお話は、機関誌『フィランソロピー』2018年12月号 に掲載しています。(全文を公開しています。)

2021.08.16
第30回/固定観念から解放される「アナザー・イベント」
前回のブログ の最後に、「多様性を、もう少し広く自由に捉えられるようになれば、もっと楽しめることがあるように思う」と書いた。今回は、その実例をご紹介したい。
先日、東京演劇集団風(かぜ)のバリアフリー演劇「Touch」の通し稽古を観せてもらう機会を得た。同劇団が持つ、群馬県月夜野にあるアトリエ近くの村の旅館の体育館で開催された。従来のイベントでのバリアフリーと言えば、車いす対応の座席、手話や字幕、音声ガイドなどの情報保障を言う。しかし、「風」のバリアフリーとは、それに加えて、それを超えるもの。即ち、舞台と客席のバリアをなくすこと。たとえば、知的障がいや発達障がいのある人が、舞台を見ていて、乗ってきて踊りだしたり、舞台に上がってきたりすることも想定される。その際、役者は、ひるんだり戸惑うことなく、観客と共に創り出す“アナザーな芝居”をバリアフリー演劇と言っている。
これまで、福祉関係者、演劇人が共に議論を重ねながら作り上げてきたそうだ。「Touch」は、原題を「ORPHANS(孤児)」という。孤児の兄弟が、不思議な大人に出会い、励まされ、勇気づけられながら孤独から抜け出し、成長していく物語である。登場人物は、兄弟と、ハロルドという男性の3人。のはずが、もう一人女性がいるのだ。どうも手話通訳者らしいのだが、舞台上で、登場人物の動きや会話に呼応するように動いている。こういう手話通訳者の動きを「舞台手話」というそうだ。
役者は、手話通訳者はいないものとして芝居をする。あるいは、その状態も含めてそれに心奪われたり、動揺せずに芝居をする。これは、障がい者が舞台に上がってきたときも同じというわけだ。舞台と観客席のバリアをなくす、とはそういうことなのかと、違和感を覚えながらも少し理解する。
これから、盲学校や聾学校、特別支援学校などでも公演が決まっているそうだ。それもいいけれど、実は、健常者と言われている一般の人向けのものではないかと思う。目からうろこの、「誰も取り残さない」を実証する、そして心震える芝居であった。
これまで、福祉関係者、演劇人が共に議論を重ねながら作り上げてきたそうだ。「Touch」は、原題を「ORPHANS(孤児)」という。孤児の兄弟が、不思議な大人に出会い、励まされ、勇気づけられながら孤独から抜け出し、成長していく物語である。登場人物は、兄弟と、ハロルドという男性の3人。のはずが、もう一人女性がいるのだ。どうも手話通訳者らしいのだが、舞台上で、登場人物の動きや会話に呼応するように動いている。こういう手話通訳者の動きを「舞台手話」というそうだ。
役者は、手話通訳者はいないものとして芝居をする。あるいは、その状態も含めてそれに心奪われたり、動揺せずに芝居をする。これは、障がい者が舞台に上がってきたときも同じというわけだ。舞台と観客席のバリアをなくす、とはそういうことなのかと、違和感を覚えながらも少し理解する。
これから、盲学校や聾学校、特別支援学校などでも公演が決まっているそうだ。それもいいけれど、実は、健常者と言われている一般の人向けのものではないかと思う。目からうろこの、「誰も取り残さない」を実証する、そして心震える芝居であった。


もう一つのイベントは、六本木の森美術館で開催している「アナザーエナジー展:挑戦しつづける力―世界の女性アーティスト16人」という展覧会。16人は、72歳から106歳の女性作家たち。若者のエネルギーとは一味違う、戦争や差別など、苦難な時代を生き抜いてきた人の鋭さと柔軟さ、そして、それを内在しつつ、いろいろな垢や情念をそぎ落としたようなシンプルで、それでいて深い眼差しと沈殿もある力強い作品たち。日本の前衛美術家の一人1932年生まれの三島喜美代さんの言葉もかっこよかった。「ゴミを陶器で表現する」三島さんだが、「命がけで遊ぶ」ことが身上らしい。魅せられた。世代による画一化は結構根強いが、年輪を重ねてこそ、同時にその相剋を超えて。機関誌の次号(2021年10月号) は「アール・ブリュット」をテーマに企画している。それもご期待いただきたいが、彼女たちの作品展、是非観て、エネルギーを感じていただきたい。
コロナ禍で、アナザー・バケーションを送っている方々も多いと思うが、それも新たな時代の幕開けにしたいものだ。
2021.06.01
第29回/多様性という名の画一化を超えて
以前観た映画「チョコレートドーナツ」を、宮本亜門が演出して昨年舞台化した。その制作過程のドキュメンタリーをテレビでやっていた。ゲイの男性二人が、親に育児放棄されたダウン症の少年を家族として受け入れ暮らし始める。しかし、ゲイのカップルが養子を迎えるということは、1970年代のアメリカでも受け入れられない社会の現実と、法の壁があった。そして、バッドエンドという筋書き。
この舞台化に向けての日々を丁寧に追いかけたドキュメンタリーだった。少年役は、ダウン症の少年二人のダブルキャスト。言葉の意味が分からずもがく。何度もダメ出しをされて落ち込む。それを忍耐強く支えるサポーター役。そして、お母さんを喜ばせたいと必死にがんばる少年。二人の少年は、演技を終えて、コロナ禍での肘タッチ。ここには、障がいというレッテルはない。個性をぶつけ合い、相手の個性を尊重しつつ切磋琢磨していく過程に、釘づけになった。
最近、多様性の尊重ということが言われるが、障がい者対健常者 高齢者対若者 貧困対それ以外 LGBT対それ以外 というように、対立構造でとらえられることが多い。もちろん差別に立ち向かい権利を勝ち取るには属性で闘うことは有効だ。しかし、暮らしの中で、レッテルを貼り、属性で一括りに捉えることには違和感を覚える。
パラリンピック種目になっているボッチャは、脳性麻痺の人向けに開発されたものと聞いており、理解促進と共に、健常者も一緒に楽しもうということで、リオ・パラリンピックの少し前、企業のCSR担当者向けのセミナーで、ボッチャの選手にも協力してもらい、ボッチャの体験をしたことがある。これは健常者も楽しめると大いに盛り上がった。リオ・パラリンピックで日本勢が銀メダルに輝き、誇らしく思ったことも懐かしい。
ボッチャはイタリア発祥のスポーツだそうだが、ちょうど、テレビでイタリアの村をルポする番組があった。そこで、なんと、老婦人たちが集まって、ボッチャを楽しんでいた。日本で見かけるゲートボールのような感じで、昔から続いているらしい。ボッチャは、障がい者スポーツと思い込んでいたが、そんな決めつけは必要ないことに目からうろこだった。
そこで、私のお気に入りのユニバーサルスポーツを紹介したい。卓球バレーというもの。卓球なの? バレーなの? どっちなの?と言われそうだが、ルールは6人制バレーボールをもとに考えられている。卓球台を使い、ネットを挟んで、1チーム6人ずつが、いすに座ってピン球を転がし、相手コートへ3打以内で返すというゲームだ。視覚・聴覚・肢体・知的の障がいのある人も、もちろん高齢者も、健常者も、誰でも楽しめる。面白いのが、椅子から腰を浮かしては反則になること。障がいのない人で、かつ勝気な人は、つい真剣になると、遠いボールを取りに行こうとして立ち上がってしまい反則を取られる。車いすの人、高齢者にそのリスクはない。案の定、負けん気の強い人が何度も反則を取られて皆で笑いあったものだ。逆転の発想だ。是非、試していただきたい。
こんな体験を通して、多様性を、もう少し広く自由に捉えられるようになれば、もっと楽しめることがあるように思う。
この舞台化に向けての日々を丁寧に追いかけたドキュメンタリーだった。少年役は、ダウン症の少年二人のダブルキャスト。言葉の意味が分からずもがく。何度もダメ出しをされて落ち込む。それを忍耐強く支えるサポーター役。そして、お母さんを喜ばせたいと必死にがんばる少年。二人の少年は、演技を終えて、コロナ禍での肘タッチ。ここには、障がいというレッテルはない。個性をぶつけ合い、相手の個性を尊重しつつ切磋琢磨していく過程に、釘づけになった。
ボッチャはイタリア発祥のスポーツだそうだが、ちょうど、テレビでイタリアの村をルポする番組があった。そこで、なんと、老婦人たちが集まって、ボッチャを楽しんでいた。日本で見かけるゲートボールのような感じで、昔から続いているらしい。ボッチャは、障がい者スポーツと思い込んでいたが、そんな決めつけは必要ないことに目からうろこだった。
2021.04.19
第28回/『共感革命 フィランソロピーは進化する』出版に寄せて
1991年4月1日にフィランソロピー推進を始めた。前職は、横浜の私立中・高校のスクールカウンセラーだった。生徒や教師、保護者の相談に乗っていた1980年代半ば、お父さんがおかしいなー、ということを問題意識として持っていた。お父さんが悪いということではなく、多くのお父さんが働く企業などの過度な経済効率性・生産性の偏重という価値観が、学校にも家庭にも色濃く影を落としているということだった。そんなことを漠然と考えている時、新聞紙上で「フィランソロピー」という言葉に出会った。何の根拠もなく、調査もせず「これだ!」「フィランソロピーが呼んでいる!」と思った(笑)。もちろん、誰も誘ってくれたわけでもなく、単なる思い込みと妄想だった。“世間知らず”も後押しして、フィランソロピーに関わることになった。
 1991年、仕事はじめとして、東海岸・西海岸以外のアメリカの企業フィランソロピーの実態調査のためにジョージア州アトランタを訪問。アトランタ・ジャーナル社で記念撮影。
1991年、仕事はじめとして、東海岸・西海岸以外のアメリカの企業フィランソロピーの実態調査のためにジョージア州アトランタを訪問。アトランタ・ジャーナル社で記念撮影。
コカ・コーラ本社、AT&T社等アメリカ企業や日系企業の「企業市民」を学んだ若き日(!?)の筆者
それから30年、紆余曲折あったが、大きな流れとしては、社会貢献と言う言葉も、1990年代には、まだまだ言葉にするのが気恥ずかしいようにとられていたが、今では、日常会話の中で使われる当たり前の言葉となってきた。しかし、一方、自然環境の著しい悪化、経済格差の拡大によるさまざまな課題噴出、先進国の中でも非常に低い青少年の自己肯定感の低さなど、不安を増幅させる時代になっていることも考えると、30年の総括において、反省点も多く、今後は、機運醸成だけではなく、もう一歩踏み込んだメッセージと活動が必要な時期が来たという思いも新たにしている。
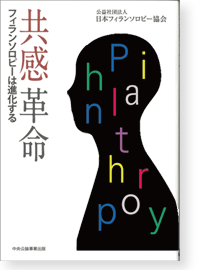 表紙をクリックすると、
表紙をクリックすると、
詳細内容をご覧いただけます。
30年という節目に、少し立ち止まって、次につなげるフィランソロピーの意味を捉えなおしてみようと思い、『共感革命 フィランソロピーは進化する』として、一冊の本にまとめてみた。寄付の推進を軸に、個人の社会貢献、それを牽引する企業フィランソロピーを推進する事業をさまざま展開してきたが、拡がりは一筋縄ではいかなかった。そして今、少し立ち止まって、フィランソロピーというものをリベラルアーツとして捉え、伝えてみようと考えた。各分野の第一線で活躍する方々のインタビューを中心に、そして、フィランソロピーや寄付の歴史を概観し、映画の中で、市井で観られる個人のあり様などについても読み物として楽しみながら考えてもらいたいという思いで企画した。そのキーコンセプトを『共感』とした。出版までの過程で、多くの方に寛容と温かさでご協力いただいた。その出会いが新たなアイディアや構想を生み、さらなる出会いにつながっていったように思う。感謝しかない。
次に向けた役割を思うとき、属性を超えた人間としての共感を、普遍的な価値として力にしつつ、次代を創り、次世代にバトンを渡したいと思う。
コロナ禍が長引く中、そして正解が見つからない今、面倒でも、まどろっこしくても、一人ひとりの意志と行動を社会化していくことが、健全な民主主義社会の創造には不可欠であることを、今、改めて痛感している。そのための役割を模索しながら、果たしていきたいと思う。但し、ゴールは遠い。だからこそ、プロセスを大切にし、何より出会いと気づき、そして葛藤や困難も楽しみながら、一歩一歩、スタッフはじめ仲間と共に進んでいきたい。

コカ・コーラ本社、AT&T社等アメリカ企業や日系企業の「企業市民」を学んだ若き日(!?)の筆者
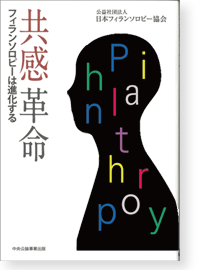
詳細内容をご覧いただけます。
次に向けた役割を思うとき、属性を超えた人間としての共感を、普遍的な価値として力にしつつ、次代を創り、次世代にバトンを渡したいと思う。
「理事長・髙橋陽子のブログ/2021年度」おわり